|
2 航空従事者の養成
航空縦事者のうち操縦士以外の者については,会社内での訓練機関における養成等でほぼ要員の確保が可能なのに対し,操縦士についてはその養成に莫大な経費と長い期間を要するため,国が積極的な施策を講じて養成および指導に当つている。なかでも多数の旅客の生命をあずかる定期航空運送事業に従事する操縦士については,とくに高い水準の訓練が要求され,これらの者はつぎのような機関で養成されている。
運輸省の附属機関である航空大学校は,昭和29年にわが国民間操縦士の唯一の養成機関として発足し,今日までに488名の卒業生を出している。養成規模は操縦士の需要の増大に伴つて逐次拡大され,現在135名の養成を行なつている。教育施設としては,宮崎本校,仙台分校に加えて新に47年度から帯広分校を開設した。
定期航空運送事業者は,自社で採用した操縦士要員を防衛庁に委託して,約1年の訓練を実施している。
航空大学校,防衛庁委託養成および防衛庁割愛によるほか定期航空運送事業者はみずから操縦士の養成を行なつている。訓練方式は各社において相違があるが,おおむね260時間ないし270時間の飛行訓練を実施している。その規模は操縦士不足の状況を反映して年々増加し,47年度は約300名である。
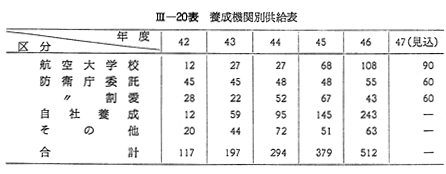
不定期航空運送事業および航空機使用事業関係操縦士の養成は主として民間の養成機関によつて行なわれており,その他防衛庁からの転出者があるほか,若干の自社養成も行なわれている。なお,回転翼航空機については年間12名の防衛庁委託養成を行なつている。そのほか,航空従事者の養成制度として45年6月の航空法改正により指定航空従事看養成施設の制度が設けられた。これは航空従事者の資格ごとに一定の訓練基準を定め,これら基準に適合する施設を運輸大臣が指定するもので,その施設を修了したものに対しては,試験の全部または一部が免除されるのである。これにより,主として事業用操縦士等の養成の効率化,合理化が図られる。
|