|
1 物流拠点施設の整備
トラツクターミナルは,中長距離のトラツク輸送において,都市間幹線輸送と都市内集配輸送の結節点として,貨物の積み替え,仕分け,混載等の機能を果たすものである。
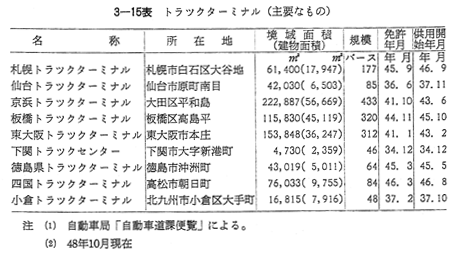
過去10年間に,総貨物量が20億トンから58億トンヘと伸びたのに対し,鉄道貨物輸送量は約2億トンのままで停滞を続けている。この理由としては,鉄道が輸送需要の高度化,多様化に対処できなかつたことが指摘されよう。しかしながら,今後の物流量の増大と,労働力のひつ迫化,道路容量の不足等から自動車輸送に限界が予想されるため,これからの鉄道は,高速性,大量性,確実性などという鉄道輸送本来の特性を生かし,陸上貨物輸送において重要な役割を果たすことが期待されている。
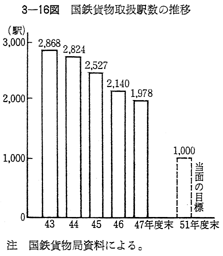
これらの整備にあたつては,単なる駅の集約化に終ることなく,その配置については,港湾,道路などとの関連を十分に考慮に入れる必要があろう。
全国の港湾で取扱われる貨物量は年々増加の一途をたどつており,入港船舶も大型化,専用船化するなどの変貌をとげながら,やはり増加の傾向にある 〔3−17図〕。
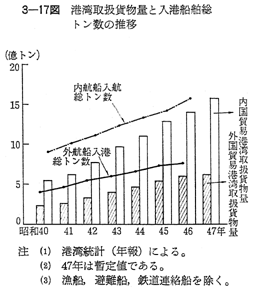
こうした輸送量の増加と新しい輸送形態の進展に対応すべく,運輸省は港湾整備5か年計画に基づいてその整備を進めているが,水域施設,外郭施設,係留施設等の港湾施設の整備は港湾取扱貨物量の増加に追いつかず,依然として施設不足の状態にある。
営業倉庫には,普通倉庫,冷蔵倉庫,水面倉庫の3形態がある。これらの整備状況は 〔3−18表〕のとおり,割合順調に行われているが,倉庫需要の伸びが著しいため,大都市,大港湾地域等では慢性的な庫腹不足に悩まされている。冷蔵倉庫については,国民の食生活の変化,コールドチエーンの普及による需要の増加に対応して,庫腹の整備が図られている。
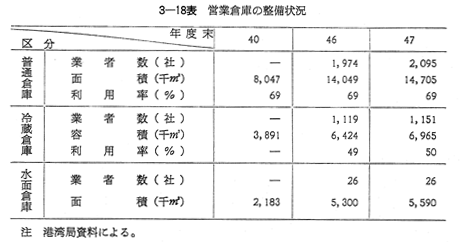
倉庫は,従来保管機能に重点がおかれていたが,消費需要の多様化,在庫管理の高度化等に対応して配送拠点としての機能を具えた流通倉庫が逐次整備されつつある。更には,コンピユータにより入出庫作業,在庫管理を行う自動化倉庫も出現している。今後も物流量の増大に伴い,倉庫の保管需要の増加と同時に,このような新しい形態の倉庫に対する需要は更に増加することが予想され,これに応じた庫腹整備が必要であろう。
我が国の航空貨物輸送量は 〔3−19図〕のとおり年々爆発的な勢いで伸びている。航空貨物は従来旅客機の下部貨物室を利用して,付随的に輸送されていたが,近年の傾向として,航空コンテナ貨物を積載できる貨客混合機,貨物専用機,ジヤンボ機等による輸送の比率が高まつている。47年度の東京国際空港における日本出入航空貨物輸送量の74%はこれらの機種によつて輸送されている。 〔3−20表〕。
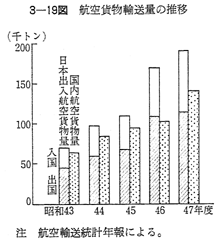
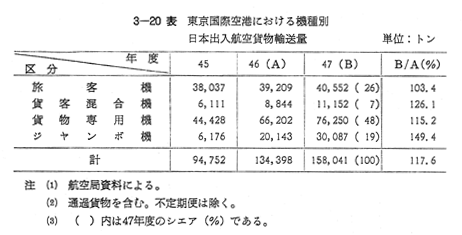
一方,空港の整備は空港整備5か年計画に基づき着々と進展しているものの,東京及び大阪の両国際空港では過密状態を呈しており,航空貨物の伸びを制約することが懸念されている。
トラツクターミナル,鉄道駅,倉庫,卸売業施設などの流通業務施設は,個々に独立して都心に集中して設けられることが多く,これが流通機能の低下と,道路交通の渋滞の一因となつていた。このため,流通機能の向上と道路交通の円滑化を進め,都市の機能の維持,増進を図ることを目的として制定された「流通業務市街地の整備に関する法律」に基づいて流通業務団地(いわゆる流通センター)が整備されてきた。この整備状況は, 〔3−21表〕のとおりであり,この代表例と目される東京南部の流通業務団地には,トラツクターミナル,倉庫,卸売センター等が集約して立地しており,物流拠点施設としての機能を果たしつつある。
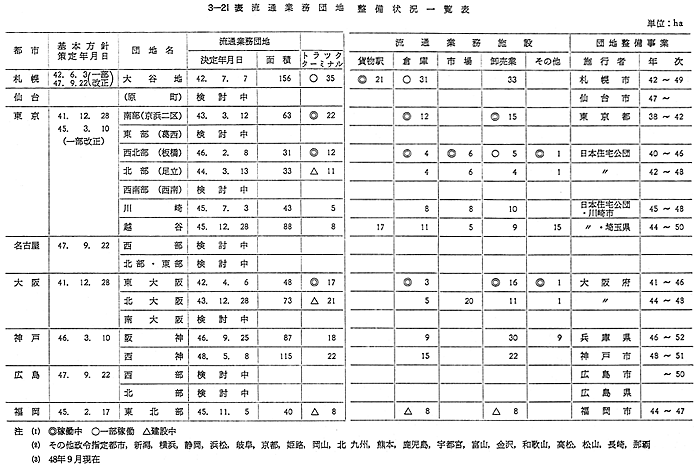
しかし,流通業務団地の整備は,都市機能の純化を図るという,都市計画的な視点に重点がおかれて行われており,流通業務施設相互間の有機的な連携や,道路,港湾など他の施設との連携が必ずしも十分とは言い難い。今後の流通業務団地の整備に際しては,このような点に留意し,異種の輸送機関を出来るかぎり有機的に組み合わせ,協同一貫輸送に適するよう複合ターミナルの構想を導入することが必要であろう。
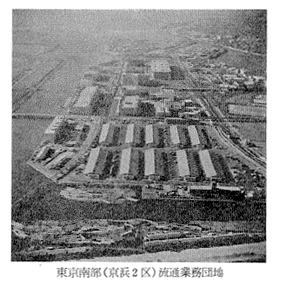
|