|
1 一貫輸送の進展と物流企業の対応
国内のコンテナ輸送の大部分を占める鉄道コンテナ輸送は,フレートライナー網の拡大により年々20%以上の増加を続けている。また国際海上コンテナは,主要航路でのコンテナ化率が60〜70%となり,在来定期船貨物を合わせた雑貨輸送全体でも16%を占めるまでになつている。このように,一貫輸送はコンテナ輸送を中心として華々しく開花しているが,なお,トラツクによる端末輸送などに問題がある。国鉄のコンテナの端末輸送は都市の交通混雑の影響を受けて集配効率は非常に悪くなつており,また,海上コンテナ等の大型コンテナの内陸輸送については,通行可能な道路が限定されていることや,トレーラの騒音,振動公害の発生等の問題がある。以上の問題に対応するには,道路の整備や現在ほとんど道路輸送に頼つている海上コンテナの内陸輸送の鉄道輸送への転移等が必要となろう。
一貫パレチゼーシヨンを実施している通運事業者は,45年度において事業者数で全数の12%であり,取扱量でも 〔3−23表〕のように47年度で全取扱量の1.7%を占めるにすぎず,しかも伸び率は近年停滞している。我が国において一貫パレチゼーシヨンの進展がおくれているのは,包装の標準化が行われていないこと等のために,JIS規格の一貫輸送用標準パレツトが普及しないこと,空パレツトの返送に問題があること,一貫パレチゼーシヨン実施によるメリツトが直接荷主にあらわれないことなどに原因があると思われる。
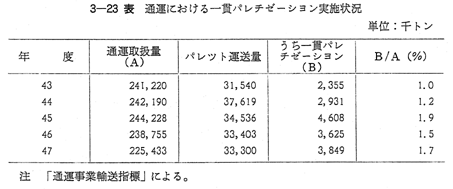
しかし,現在の人手に頼る荷役方式は,早晩限界に来るものと予想され,物流コスト低減の見地のみならず,荷役作業の労働条件の改善のためにも一貫パレチゼーシヨンの必要性はますます高まつている。このため46年にパレツトプール会費が設立され,更に48年1月の通運料金の改定により一貫パレチゼーシヨン貨物の割引制度が適用となるなど,条件は次第に整備されつつあり,今後一層の進展が期待される。
輸送方式の多様化,都市内集配の困難性の増大等により,物流業に対する荷主の要望もよりシステム化されたサービスを求めるようになつてきている。これには一貫輸送において輸送手段の選択を中心とする業務を物流業者に一任しようとする方向と,輸送・保管・荷役・包装等の物流サービスを一括して委任しようとする方向とがあり,このような新しいサービスを提供する一貫運送取扱人や総合物流業に対する荷主側の要望も強まつている。
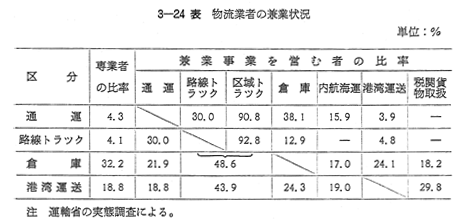
既に総合物流業化した一部の大企業ではコンピユータによるオン・ライン網を通じて,受注から出荷,輸送,保管,配送までの物流を一括して請け負つている例もあるが,一般には既に営んでいる事業を基盤としつつシステム化された物流機能の提供へと進んでいくであろう。こうして総合物流業化の傾向は今後一層進むものと考えられるが,一方,個別業界に分かれた物流業においては,お互いの協調体制が不十分で伝統的な業界の枠内から容易に脱皮できないなどの問題がある。
|