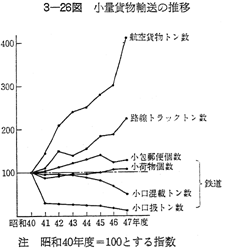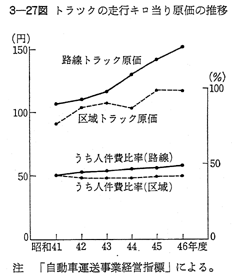|
2 小量貨物の輸送
小量貨物輸送は,1回の出荷量が経済輸送単位に満たないため,運送事業者ではこれらの小量貨物を仕分,混載して一定の大きさの経済輸送単位に仕立てて輸送する形態をとる。
このような小量貨物運輸サービスを種類別に一覧すると, 〔3−25表〕に示すようになつている。

小量貨物輸送は,生産,消費活動を通じた雑多な輸送需要に対応しており,路線トラツクを中心に年々かなりの伸びをみせている。しかし,種類ごとにその推移をみると, 〔3−26図〕のように路線トラツクと航空貨物の伸びが大きいのに対し,鉄道小量貨物は停滞しており,小量貨物輸送ではトラツク輸送の比重が高い。
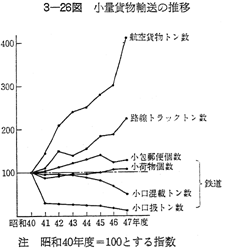
路線トラツクによる輸送個数を品目別にみると,1次産品はわずか7%を占めるに過ぎず,日用品(18%),食料工業品(17%),化学工業品(14%),機械(12%),などが高い比重を占めており,消費生活に関連のあるものが多くなつている。
小量貨物輸送の問題は,集配,仕分,混載,荷役等の端末サービスの作業に多くの人手を要し,更に輸送単位が小さく,相対的に荷主が多数存在すること,荷姿の不統一,都市の交通混雑等により近代化や合理化が困難であり,その結果これら端末作業のコストが急速に上昇していることである。 〔3−27図〕は混載貨物を扱う路線トラツクと1車単位の貨物を扱う区域トラツクの走行キロ当り原価を比較したものであるが,ターミナルや集配にコストのかかる路線トラツクが区域トラツクに比べて46年度で30%も上回つており,費用構成においても路線トラツクの人件費比率が高くなつている。このような小量貨物輸送のコスト上昇は当然経営を圧迫することとなる。また,小量貨物には,季節的な波動が大きいことなどの不安定要因がある。前述したように,小量貨物輸送は生活に関連のある物資を多く扱つており,公共輸送としての性格が強く,サービスを維持する必要がある。
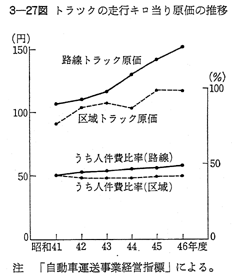
|