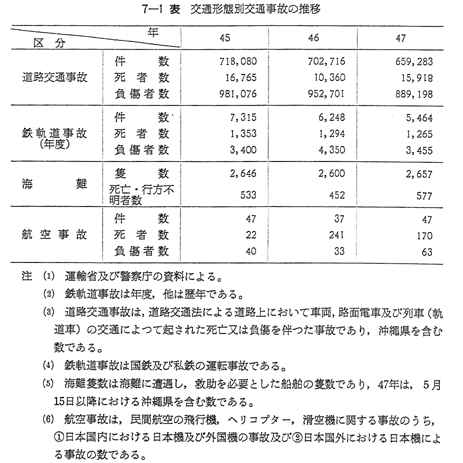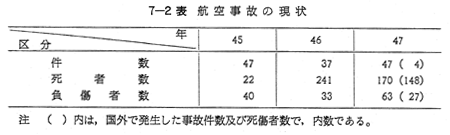|
1 交通事故の現状
交通事故対策の進展により,事故発生件数は昭和45年をピークにその後は減少の傾向にあるが,絶対数は依然高水準で推移しており,また,高速化,大型化等により,1事故当りの被害も増大している。
交通形態別にみた最近3か年間の交通事故の推移は 〔7−1表〕のとおり,道路交通事故及び鉄軌道事故は年々減少してきているが海難及び航空事故は,横ばい状況で推移している。
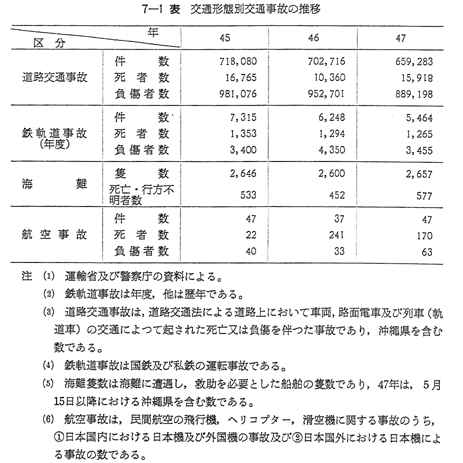
(1) 道路交通事故
47年中に発生した道路交通事故は,約66万件であり,これらの事故により約1万6,000人が死亡し,約89万人が負傷した。これを前年と比較すると発生件数は6.2%,死者は2.7%,負傷者は6.7%,それぞれ減少している。
事故の発生状況を地域別に見ると人口密度が高く,かつ経済活動の中心として自動車交通量の多い東京,名古屋,大阪,神戸,福岡等大都市及びその周辺において多発している。しかし,これらの地域における事故件数は絶対数は多いが,45年以降徐々に減少している。一方その他の地域においては,事故件数は絶対数こそ少ないが横ばいないし増加の傾向を示している。
また,事故の発生状況は類型別にみると車両相互の事故が約45万件で全事故の68%も占めており,次いで人対車両の事故が約10万件で24%,車両単独の事故が約5万件で7%となつている。これを前年と比較すると車両相互の事故は6.7%,人対車両の事故は4.7%,車両単独の事故は6.8%,それぞれ減少している。
事故のうち死者を出した死亡事故について類型を人対自動車,自転車対自動車等いわゆる「走る凶器」型の事故と自動車等相互及び自動車単独のいわゆる「走る棺桶」型事故に分け,それらの発生状況を見ると「走る凶器」型の事故が全死亡事故の48.1%,「走る棺桶」型の事故が47.1%とほぼ同比率となつている。
(2) 鉄道事故
47年度における運転事故の発生状況は,5,464件であり,4,720人が死傷している。これを前年度に比較すると件数は12.6%,死傷者数は16.4%それぞれ減少している。
しかし,運転事故は,ここ数年減少の傾向がみられるものの,その反面,事故の大型化により死傷者数の変動が著じるしい傾向がみられる,47年度においても,47年11月国鉄北陸本線「北陸トンネル」内での列車火災事故では死傷者744人という大惨事を招いている。
また,踏切事故防止対策の強化により,踏切事故は36年度をピークに年々減少傾向にあるものの各年度における事故総数のなかでの割合は高く,47年度においても約半数を占めている。
(3) 海難
47年中に発生した要救助船舶(救助を必要とした船舶)は46年に比べ57隻増加し,2,657隻であつた。また,これら船舶の海難により577人が死亡・行方不明となり失われた船体,積荷等の損害額は206億円に及んだ。
要救助船舶の海難を種類別にみると,例年と同様に乗り揚げが555隻と最も多く,次いで機関故障(554隻),衝突(407隻)浸水(348隻)の順となつており,これら4種の海難で全体の70%を占めている。
また,これを発生海域別にみると船舶交通のふくそうする港内及び3海里未満の沿岸海域において1,873隻発生し,海難全体の70%を占めている。なかでも東京湾,伊勢湾及び瀬戸内海の3海域においては959隻の海難が発生し,全海難の36%,沿岸海域の海難の51%を占めている。
一方,要救助船舶の海難の原因についてみると操船不適切,見張不十分等の運航過誤によるものが50%を占めており,この運航過誤に機関取扱不良,火気不燃物取扱不注意及び積載不良を加えた,いわゆる人為的原因によるものが77%を占めている。
(4) 航空事故
47年中に発生した民間航空機の事故は47件であり,これらの事故により170名が死亡し,63名が負傷した 〔7−2表〕。このうち4件は,外国において発生した事故で,6月14日のニユーデリー事故(死亡86名,重傷3名),9月24日のボンベイ事故(重傷2名),11月2日のアンカレツジ事故(人員の死傷なし),11月28日のモスクワ事故(死亡62名,重傷14名)である。運輸省としては,かかる一連の事故にかんがみ,尊い人命をあずかる航空運送事業者の使命と責任を再認識して,安全運航を最優先させるよう指導を行い,航空安全対策の強化を図つている。
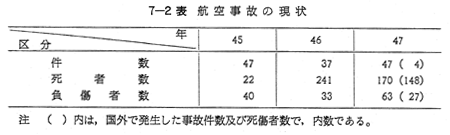
|