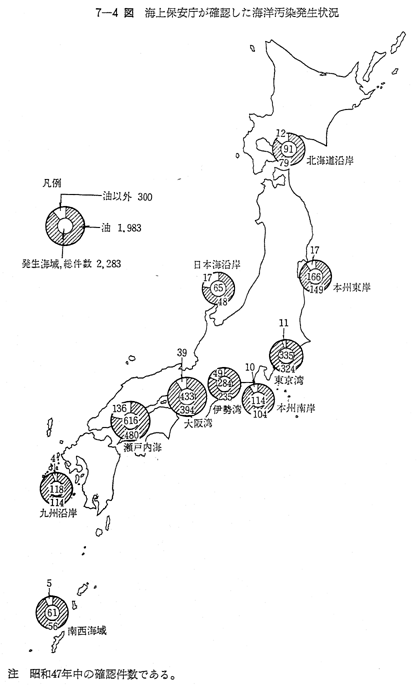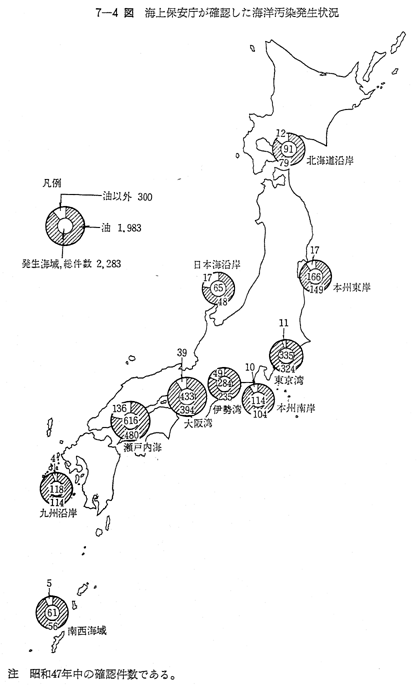|
2 交通公害の現状
交通活動は,陸上,海上,空中において多量の自然環境資源を消費して行われており,市民生活に密接した場において,騒音,大気汚染,海洋汚染等の公害をひきおこす原因の一つとなつている。
交通機関毎に問題になつている公害について概観すれば次のとおりである。
自動車による公害には,排出ガスによる大気汚染,騒音,廃車公害などがある。
排出ガスによる大気汚染については,東京都内の道路沿い3測定点の測定結果によると, 〔7−3図〕のように規制措置のとられた一酸化炭素濃度は44年度以降低下してきているが,窒素酸化物は依然として高い水準にあり,炭化水素についても高水準に推移していることが観測されている。

光化学反応による大気汚染は,窒素酸化物と炭化水素が原因物質とみられており,次第に広域化する傾向にある。
騒音については,48年に東京都が行つた世論調査によると,自動車による公害が附近で起きていると答えた者のうち,騒音による被害をあげた者は,排出ガスによる被害をあげた者と並んでいる。また,自動車の廃車台数が年々増加しており,欧米のように廃車処理に関する公害が問題となつてきつつある。
鉄道では,高速走行時に発生する新幹線騒音が問題になつており,営業区間について所要の対策が要望されているほか,新幹線建設に反対する沿線住民の運動が盛んになつてきている。
航空機騒音については,ジエツト機の離着陸時の騒音は,飛行場周辺において80ホン以上に達し,周辺住民の日常生活の障害となつているため,市街地と接する飛行場の周辺では特に問題となり,大阪国際空港及び東京国際空港付近の住民から国を相手に訴訟が起されていたが,東京国際空港に係る訴訟は各種の対策が講じられたことによつて48年2月に取下げられた。
海洋汚染では,47年中に海上保安庁が把握した海洋汚染発生件数は2,283件に達している。汚染発生の分布を見ると,我が国のほとんどすべての沿岸海域にわたつているが, 〔7−4図〕に見るとおり,東京湾,伊勢湾,大阪湾及び瀬戸内海での汚染発生件数が全体の73%を占めている。また,全発生件数の87%が油によるものとなつている。内海,内湾等における赤潮の発生,タンカー等からの流出油によるものとみられる廃油ボールの我が国沿岸への漂着も依然として続いている。
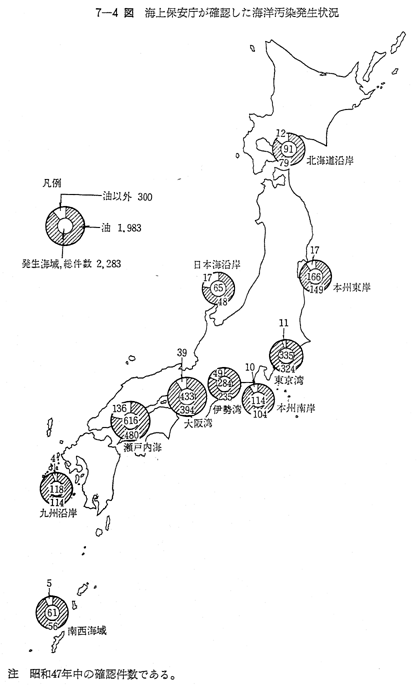
|