|
2 日本の国際航空輸送状況
47年度の我が国の国際航空輸送実績は, 〔III−3表〕のとおりであり,国際航空輸送量は,前年度に比べ若干増加し,同輸送量のバロメーターである有償トンキロの増加率は,前年度並みの24.2%であつた。これを貨客別にみると,旅客輸送量については,旅客人員の伸びは前年度を下回つたが,日本人団体旅行客の長距離旅行化を反映して,旅客人キロの伸びは前年度をかなり上回つた。また,貨物輸送量については,46年度が米国西海岸港湾ストの影響により異常な伸びを示したため,47年度の伸び率は,前年度に比べ,低い水準にとどまつたが,それでも,航空貨物需要には,根強いものがうかがわれる。
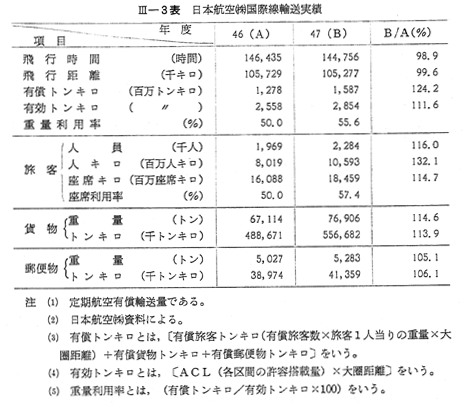
次に,輸送力についてみると,飛行時間,飛行距離は,前年度とほぼ同じであつたが,新たに北回り欧州線及び東京-グアム線にジヤンボジエツト機(B-747)を導入したため,有効トンキロは,11.6%増加した。
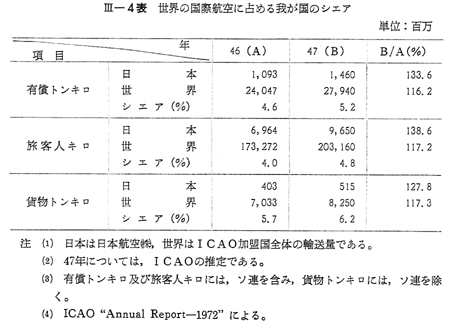
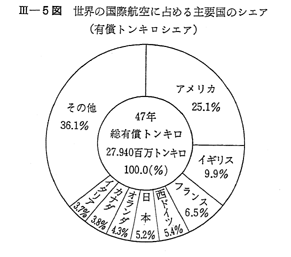
47年度の日本航空(株)の国際線旅客輸送量は,旅客人員228万4,000人,旅客人キロ105億9,300万人キロであり,前年度に比べ,旅客人員16.0%増,旅客人キロ32.1%増であつた。これは主として北回り欧州線,太平洋線を中心とした日本人団体旅行客が大幅に増加したためであり,日本人の旅行が徐々に長距離化してきていることを示している。また,旅客座席キロは,B-747の投入等によつて46年度に比べて14.7%の増加となつたが,前述のように旅客人キロがかなりの伸びを示したため,座席利用率は,46年度より7.4ポイント上昇して57.4%となつた。
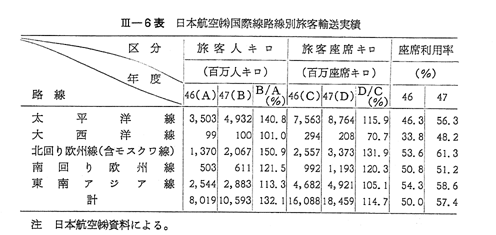
次に,47年度の我が国出入旅客について日本航空(株)の積取比率をみると 〔III−7表〕のとおりであり,前年度に比べて低下した。日本人,外国人別の積取比率をみると,日本人は48.5%で前年度をかなり下回つたが,外国人は22.4%で若干上昇した。
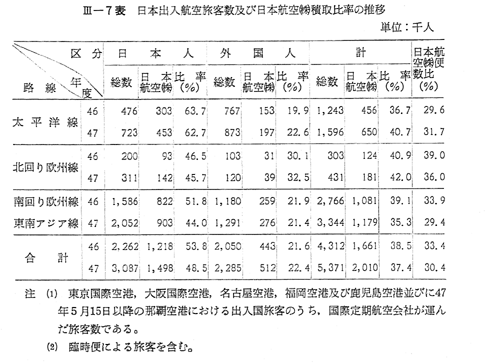
日本人旅客の積取比率は,特に東南アジア線において大きく低下しているが,これは,主として,47年5月の沖縄の本土復帰に伴い,それまで国際線であつた沖縄関係の路線が国内線に編入されたためである。
47年度の日本出入航空貨物量は, 〔III−8表〕のとおり前年度に比べ12.6%の伸びで,46年度の伸び率の54.4%に比べてかなり低かつた。これは,主として,米国西海岸の港湾ストにより,貨物が航空へ大幅に転移したという特殊事情があり,46年度の伸び率が非常に高かつたためであるが,国際航空貨物需要には,依然として根強いものがうかがわれる。
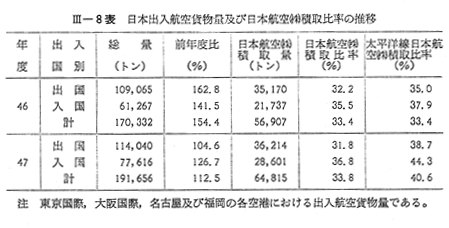
日本出入航空貨物を出入別にみると,47年度における輸入促進政策の影響もあつて,出国が前年度比4.6%の伸びに対して,入国が同比26.8%の伸びとなつている。日本航空(株)の積取比率は,全体として前年度と同水準となつているが,太平洋線における積取比率は,40.6%で前年度より大幅に上昇している。これは,米国西海岸の港湾ストの影響による貨物需要の伸びに輸送力が対応しきれず限界に達したことにより,46年度の日本航空(株)の積取比率が低かつたためである。
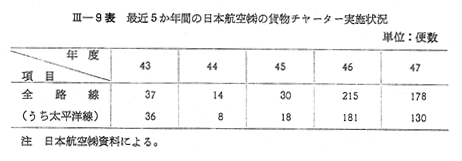
47年度における我が国の航空関係国際収支は, 〔III−10表〕のとおり1億3,600万ドルの赤字となつた。これは,主として出国日本人旅客(特に団体旅行客)の急増により旅客運賃の支払いが増加したことによるものであり,46年8月から新設された航行援助施設利用料によつて港湾経費の受け取りがかなり増加したにもかかわらず,全体として,赤字幅は前年度より増加した。
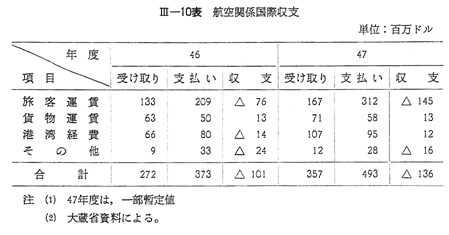
|