|
1 航空運送事業
日本航空(株)の昭和47年度の収支は, 〔III−14表〕のとおりである。常業収入は,前庫度に比べて16.2%増の2,208億5,900万円であり,これに営業外収入を加えた総収入は,同15.3%増の2,363億700万円であつた。一方,総費用が同13.8%増の2,226億2,200万円であり,経常利益は,136億8,500万円となつた。これを売上高利益率(経常利益/営業収入×100)でみると,47年度は,6.2%であり,46年度の4.9%に比べやや良くなつているが,45年度の9.3%,44年度の16.9%には及ばず,全体として年々下降の傾向にある。これは,ジエツト化,大型化のもたらす生産性向上による費用増の吸収余力が少なくなつてきていることを示している。
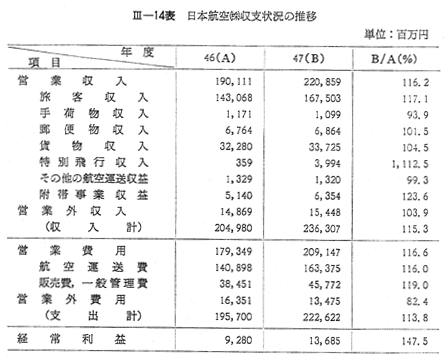
47年度の営業収入をみると,国際線については,旅客人員及び旅客人キロが,それぞれ前年度比16.0%,32.1%の増加となつているのに対し,大幅割引運賃を使つた団体旅行客の割合が増大したこと,また,国際通貨変動の影響により円換算運賃が下つたことにより実収単価が低下し,旅客収入の伸びは前年度比15.3%増にとどまつた。また,貨物については,貨物トンキロが,同13.9%の増加を示しているが,旅客同様実収単価の低下があり,貨物収入は前年度並みにとどまつた。
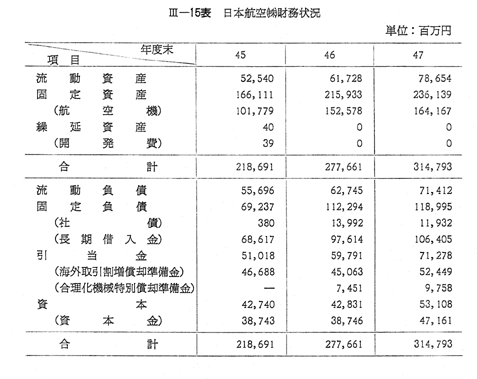
なお,日本航空(株)を除く国内線定期航空運送事業者別の収支状況は, 〔III−16表〕のとおりである。全日本空輸(株)は,機材の大型化,ジエツト化を図つた結果,旅客輸送実績が向上し,更に航空機処分益,為替差益等の特別利益があつたため,税引前当期利益は63億円となつた。しかし,東亜国内航空(株)は,YS-11型機の生産性の低下及びジエツト化の推進に伴う先行投資の増大等により経常損益で33億円の赤字となつた。
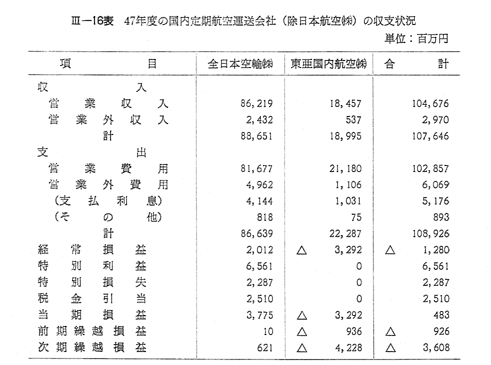
国内定期航空運送事業の最近数年間の利益率の推移は, 〔III−17図〕のとおりであり,43年度までは急速に収益性が高まりつつあつたが,44年度から低下のきざしがみえ,47年度は,東亜国内航空(株)の不振が大きく,売上高営業利益率ではマイナスとなつた。
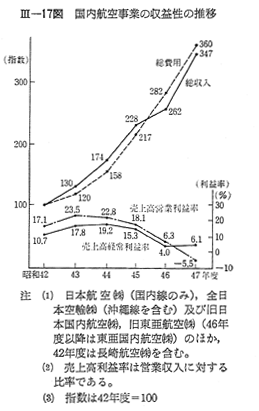
日本航空(株)は,47年度においても,46年度に引き続きかなりの業績を示したが,今後,同社は大型機就航による本格的大量輸送時代を迎え,また,シベリア線の門戸開放による欧州企業の進出等により,ますます激化する国際競争に直面せざるを得ず,今後とも経営基盤の強化等に努めることが必要である。
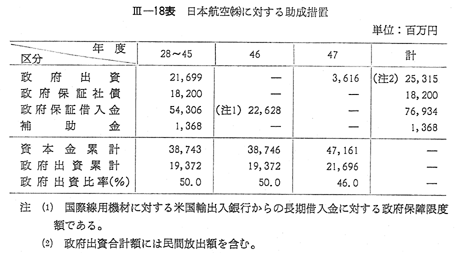
イ 出資
ロ 債務保証
従来,日本の航空企業が米国から輸入する航空機の購入資金については,購入価格の80%相当分を米国金融機関からの借款によりまかなつてきた(購入価格の40%については米国輸出入銀行,40%については米国市中銀行)。この借款の債務保証は,主として日本開発銀行が行つてきた(日本航空(株)が購入する国際線用機材の米国輸出入銀行からの借款部分については,43年度から政府保証が認められた。)。
国内線における航空運賃は,幹線については30年,ローカル線については41年の運賃水準がほぼそのまま維持されてきたが,46年8月から航行援助施設利用料の徴収による負担増,47年4月から新規賦課されることとなつた航空機燃料税(47年度5,200円/kl,48年度10,400円/kl,49年度以降13,000円/kl)の負担増,更に,その他の諸経費が高騰していることを理由として,47年1月,国内線定期航空運送事業3社から,旅客運賃を平均23.0%,貨物運賃を平均21.1%値上げする旨の運賃改訂申請がなされた。この申請に基づき,航行援助施設利用料並びに航空機燃料税の負担増分に見合うものとして,旅客運賃を平均9.5%(幹線7.5%,ローカル線11.8%),貨物運賃を平均8.6%(幹線7.5%,ローカル線11.6%)増とする改訂を認め,47年7月15日から実施することとなつた。
|