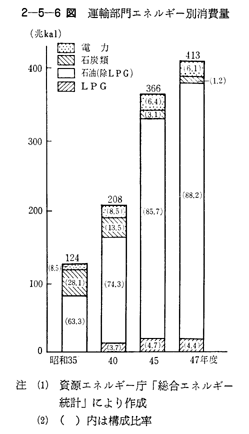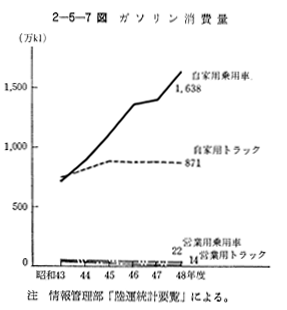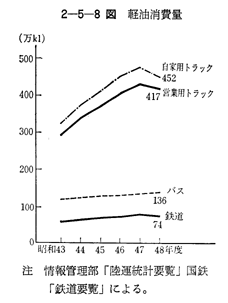|
2 運輸部門におけるエネルギー消費
我が国の運輸部門でのエネルギー消費量は,47年度で,全体の12.9%に当たる413兆キロカロリーであった。種類別にみると 〔2−5−6図〕のとおり石油の割合が高くなっており,LPGを含めると全体の92.6%に及んでいる。
需要構成については,鉄道の電化の進展による電力の増加及び石炭類の減少と,モータリゼーションの進展や航空機輸送の発達による石油の増加により昭和30年代以降大きく変化している。また,LPGも,近年のLPG車の普及により増加を示している。
次に,エネルギーの使用量を各輸送機関別に分析することにする。
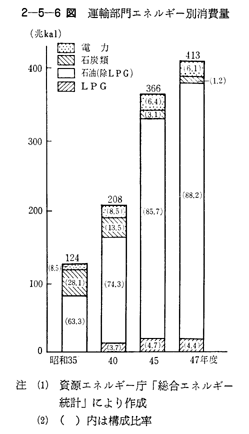
(1) 自動車
自動車が使用する燃料は,ガソリン,軽油,LPGである。特にガソリンは運輸部門が全体の98.3%を消費しているが,その大半が自動車によるものである。
車種別にみると,自家用乗用車では,消費燃料のほとんどが,ガソリンであり,その量も自家用乗用車の普及を反映して急速に増えており,48年度は,1,638万klとなっている。
これに対し,営業用乗用車では,LPGの価格が,ガソリンに比べて低廉であったため,ガソリンからLPGへの燃料の転移が著しく48年度の消費量は176億Kcal(148万トン)となっており,ガソリンの19億Kcal(22万kl)の約9.3倍に達している。
営業用トラックでは,大型車の比率の増大により,軽油消費量が急増してきたが,48年度は輸送活動の停滞により消費が落ちこみ417万klとなった。一方,ガソリン消費量は,39年度をピークとして,年々減少し48年度は14万klとなっている。
自家用トラックでは,ガソリン消費量は横ばい,軽油消費量は増加の傾向にあったが,48年度は軽油も減少し,ガソリン消費量871万kl,軽油消費量452万klであった。
バスについては,営業用では,100%近くが軽油を使用しているが,量的にはあまり増加していないのに対し,自家用では,消費の絶対量は少ないが,ガソリン,軽油ともに増加が著しい。
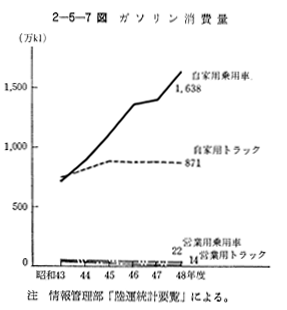
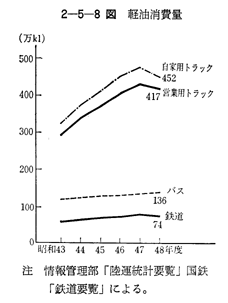

(2) 鉄道
国鉄の運転用燃料消費量を種類別にみると,軽油は年々漸増していたものの48年度には減少し,72万klとなっている。
石炭消費量は48年度が76万トンと40年度の約8分の1になっており,減少が著しい。この傾向は無煙化の進展とともに今後とも続くものと思われる。
電力消費量については,電化の進展に伴い,年々増加してきたが,新幹線の開業した39年度以降,特に著しく増加しており,48年度は74億kwhとなっている。
民鉄については,貨物輸送では軽油の割合が大きく,旅客輸送では,電力への依存度が非常に高い。48年度の消費量は,貨物,旅客を合わせて,軽油1万3,000kl,電力43億kwhとなっている。
(3) 内航海運
内航海運では,48年度に運輸部門全体で消費した重油の94.5%に当たる763万klを消費している。内訳は,A重油が350万kl,B重油が374万kl,C重油が40万klである。
(4) 航空
航空機で使用する燃料の大半はジェット燃料であるが,ガソリンも若干使用されている。ジェット燃料の消費量は航空機の急速な発展を反映して著しく伸びており,48年度は132万klと40年度の約4.6倍の水準になっている。
なお,以上のほかに,外航船舶や国際線の航空機によるボンド油(保税油)の消費がある。48年の消費量は,邦船及び外国船による内地調達分の重油が1,930万kl,邦機及び外国機による内地調達分のジェット燃料が208万klである。
|