|
2 施設整備の方向
以上述べたような幹線交通の動向に対応して,鉄道,道路,港湾,空港等の整備が数次にわたる長期計画等に基づいて実施され,また,内航海運,フェリー等についても,その整備増強が図られるなど新しい幹線交通ネットワークの形成が進められてきた。
新幹線鉄道については,49年度までに東京―福岡間約1,069キロメートルが完成したほか,全国新幹線鉄道整備法に基づき,現在,東北,上越,成田の各線(合計約831キロメートル)が国鉄及び日本鉄道建設公団により建設されている。また,在来線についても主要幹線の整備増強を図った結果, 〔2−2−6図〕のとおり複線化率は40年度末の16.9%から49年度宋には25.2%へ,また電化率は同じく20.4%から34.9%へと向上し,その結果,特急の設定キロ数が40年度から49年度までの間に3.7倍となるなどスピードアップが可能となった。また,貨物輸送についても,その近代化・合理化に努め,44年から開始したフレートライナー網が全国的に拡大し(49年度末の設定本数120本), 〔2−2−7図〕のとおりそのシエアを伸ばすなど協同一貫輸送を推進するとともに,石油,セメント等については専用ターミナル等の整備を図ることにより物資別専用輸送を推進するなどの合理化が進められてきた。
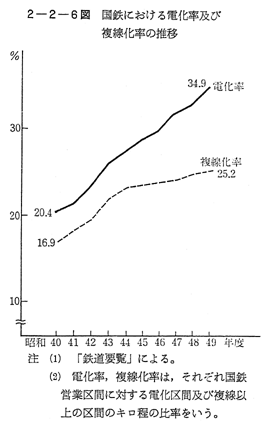
以上のうち,49年度中には,新幹線岡山・博多間の開業(50年3月)のほか,羽越本線,外房線等6線区30.1キロメートルの複線化,日豊本線,総武本線等5線区339.3キロメートルの電化,盛岡貨物ターミナル等の新設 〔2−2−8表〕などがあった。
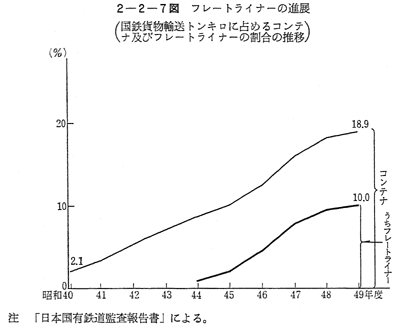
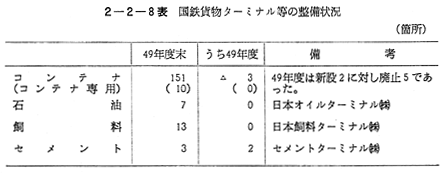
しかしながら, 〔2−2−9図〕でみられるように,主要線区における列車本数は線路容量の限界に達しており,この種線区での列車の増発余力,時間帯選定の自由度が失われ,旅客輸送のみならずフレートライナー等貨物輸送の増強にとっても隘路となっている。その改善のため,現在工事中の東北,上越の各新幹線の建設工事,東京−小田原間の線路増設工事等の促進を図る必要がある。さらに,東京−大阪間の輸送力についても新幹線,在来線とも既に限界に近づきつつあるので,その対策についても検討する必要があろう。
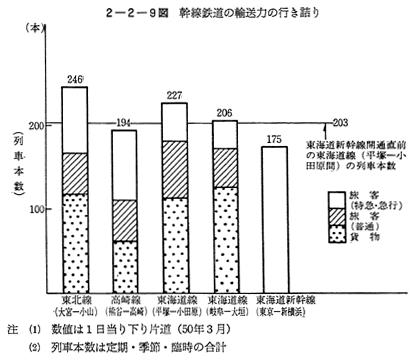
また,施設整備の遅れている鉄道貨物輸送については,鉄道の特性の発揮できる分野に重点を置く等その効率化のための施策を推進することが必要となろう。
道路については,数次にわたる道路整備5か年計画に基づき道路整備が進められた。この結果,一般国道は40年度末から49年度末の間に改良率は66.5%から85.5%に,また,道路舗装率は59.0%から90.6%へと向上した。高速自動車国道については,日本道路公団によりその整備が進められ,49年度末までに名神,東名等1,519キロメートルが供用され,現在,東北縦貫,中央,中国縦貫等約3,300キロメートルについて施行中である。このうち,49年度中に供用開始されたものは,中国縦貫自動車道西宮北―福崎間等305キロメートルである。
海運関係では,港湾整備5か年計画に基づき港湾の整備を進めており,この結果,港湾岸壁延長(水深9メートル以上のものであって民間その他の者の管理する施設を含む心)は,48年度末には19万3,000メートル(40年度末の2.1倍)へと拡大した。この間,物流体制の整備に資するため,コンテナ埠頭,フェリー埠頭及び一般公共埠頭の整備を推進した。42年度以降49年度までに京浜,阪神の面外貿埠頭公団により,外航コンテナバース20,外航定期船バース18を供用したのを始め(うち49年度中に完成したものは外航コンテナバースが京浜,阪神各2,外航定期船バースが京浜5,阪神4バース),46年度以降各港ごとにフェリー埠頭公社を設立し,49年度末までにフェリー埠頭15バースの整備を完了している。また,港湾荷役の機械化による合理化も進展しており,港湾荷役機械の保有状況は 〔2−2−10図〕のとおり,大型荷役機械,フォークリフトが大きく伸びており,クレーンは移動式への代替が進んでいる。
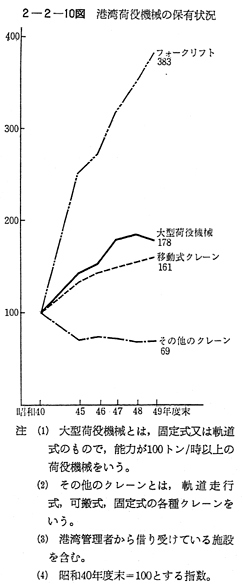
なお,49年度の港湾取扱貨物量の伸びはほぼ横ばいであったが, 〔2−2−11図〕にみられるように,主要港湾の混雑は依然として高い水準に推移した。
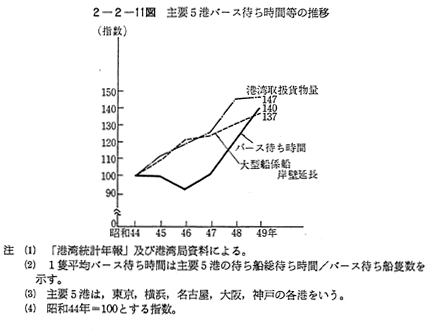
次に,外航船舶は,貿易物資の安定的な輸送を目的とし計画造船を中心として整備が進められ,49年年央には大型タンカー,コンテナ船,専用船等3,300万総トンと世界第2位の船腹量を持つに至った。
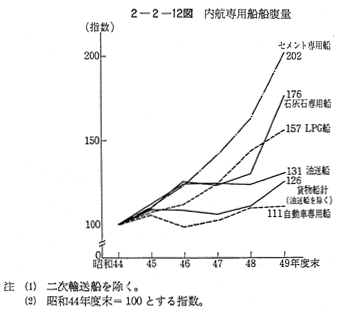
また,旅客船では長距離カーフェリーの発達が著しく,43年に第1船が就航して以来,49年度末の長距離フェリー航路就航船舶は55隻約41万総トンに達し, 〔2−2−13図〕のとおり輸送量も増大している。
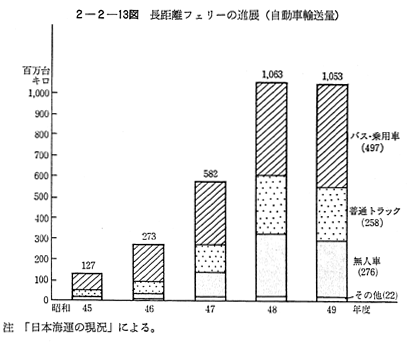
航空については,空港整備5ケ年計画に基づき空港の整備を進めた結果, 〔2−2−14表〕のとおりジェット機就航空港が45年度の7空港から49年度には16空港となるなどローカル空港を中心にその整備が進展し,40年度から49年度までの間に国内線座席キロが5.4倍に達する等輸送力の大幅な増強が図られた。また,増大する輸送需要に応えるため,関東地区については41年に新東京国際空港公団を設立し,千葉県成田地区に新空港を建設中であり,また関西地区については,航空審議会答申に基づき,大阪湾南東部の泉州沖に関西国際空港の計画を進めている。このほか,49年度以降にあっては,騒音問題を考慮した初の本格的な海上立地空港である2,500メートルの滑走路を備えた長崎空港が50年5月に開港し,また,函館空港の滑走路延長工事が実施されるなどローカル空港の強化が図られた。
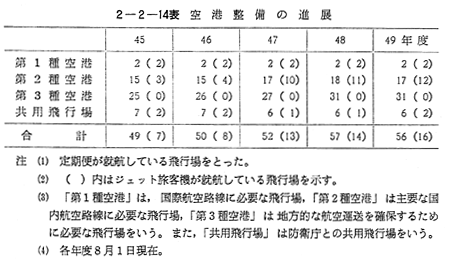
しかし,以上述べたローカル空港の整備の進展にもかかわらず,我が国航空路線網の中心である東京及び大阪国際空港は, 〔2−2−15図〕にみられるように,外国機をも含め騒音問題から着陸回数等の規制を実施せざるをえないこともあって,数年前からその能力の限界に達しており,国内航空輸送網の整備の隘路となっているだけではなく国際線の増便も抑えざるを得ない等の問題が生じている。
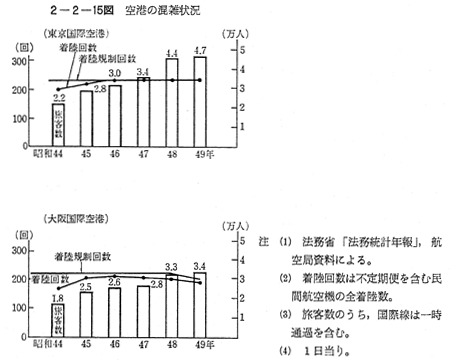
以上のような直接的な輸送施設の整備に加えて,需要の量的拡大とその高度化,多様化の要請に対応してサービス水準の向上を図るとともに,併せて安全の確保あるいは業務の効率化を進めるため,各分野でコンピューターの導入が進んでおり, 〔2−2−16表〕のとおり国鉄座席予約システム(MARS),新幹線運転管理システム(COMTRAC),航空会社の座席予約システム(JALCOMII)等の通信回線を利用した情報システム化の進展が著しい。
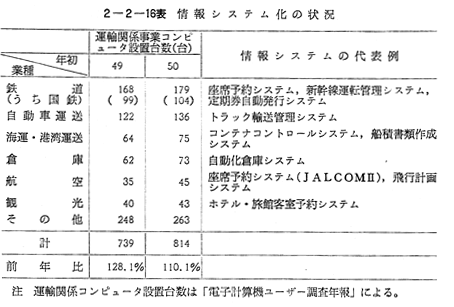
|