|
1 輸送の動向大都市圏における人口の集中は,近年鈍化の傾向がみられるものの依然として続いている。すなわち,首都圏,中京圏,京阪神圏の三大都市圏の人口は, 〔2−2−17図〕のとおり49年度末には5,106万人と45年度末以降372万人増加した。これは,この間の全国総人口の増加分641万人の58.0%を占めており,その結果三大都市圏の人口が全国総人口に占める割合は46.0%となった。
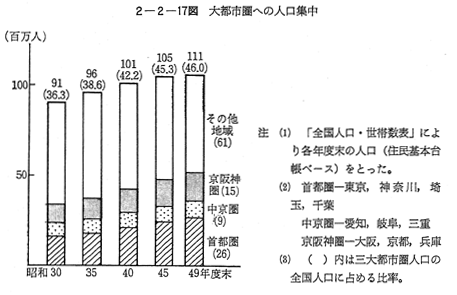
また,都市における人口分布のドーナツ化現象が顕著となっており, 〔2−2−18図〕のとおり都心部の事業所化による夜間人口の減少と郊外部人口の急増がみられる。
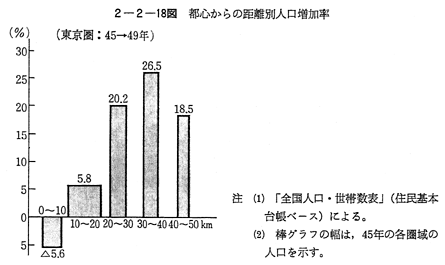
このような現象は,都市交通にもさまざまな影響を及ぼしている。まず三大都市圏について旅客輸送をみると, 〔2−2−19図〕のとおり域内輸送量は増加を続けているが,輸送機関別にみると,最近においては,地下鉄,民鉄輸送量の増勢に支えられて鉄道輸送量が増加しており,バス・タクシー等は減少傾向にある。また,40年代前半に急速な伸びを示した自家用乗用車の伸びが鈍化している。
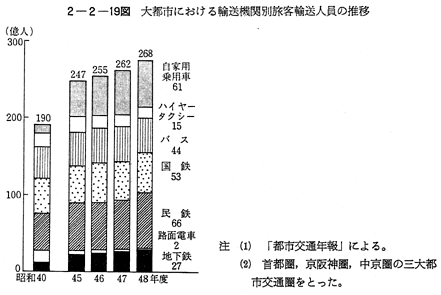
49年度においても 〔2−2−20図〕のとおり,概ねこのような傾向が続いており,前年度に比べ旅客輸送では鉄道輸送量が増加し,バスが横ばい,自家用自動車及びタクシーが減少している。
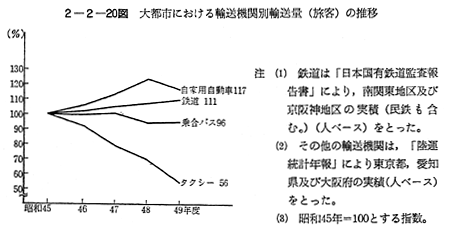
次に,三大都市圏における貨物輸送量についてみると, 〔2−2−21図〕のとおり40年代前半までは旅客輸送量の伸びを大幅に上回って増大してきたが,最近では頭打ちの傾向にある。輸送機関別では自動車による輸送量が大半(48年度で全体の93.4%)を占めている。49年度においては,経済不況の影響を受け, 〔2−2−22図〕のとおり貨物輸送量は大幅に減少したが,なかでも自家用トラックの落ち込みが著しかった。
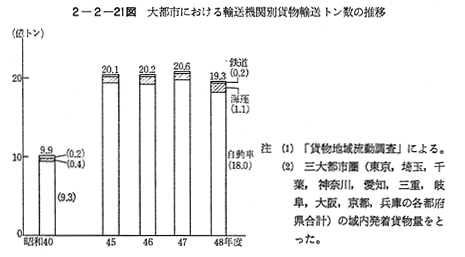
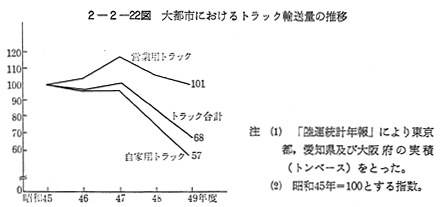
|