|
2 施設整備の方向
大都市圏への人口集中とドーナツ化現象の継続に伴って,高速鉄道による旅客輸送量は増大の一途をたどるとともに平均輸送距離も長距離化の傾向がみられる。

しかしながら,ラッシュ時における混雑率は,なお高水準にあるうえ,最混雑時における都市鉄道の運転状況をみると, 〔2−2−24表〕にみられるように列車回数は物理的限界に達しているものが多く,また,車両の長編成化も駅施設からみて限界に近い。このため,民鉄のラッシュ時の急行,快速の運転速度は通常時の20〜30%減となっている。したがって,新線建設,在来線の線増工事等をなお一層進める必要があるが,最近においては,沿線地域における環境保全の要請,用地取得難,建設・営業経費の高騰による採算性の悪化等から困難さが増している。また,輸送力増強に関連する高架化についても公共事業抑制,地方公共団体の財政難等のため遅れが目立っている。
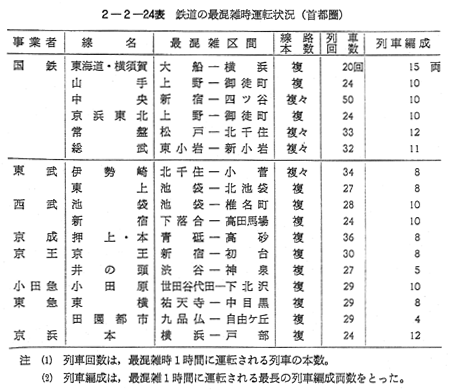
なお,都市における新しい交通機関として道路混雑,交通公害等の諸問題に対処するとともに新しい輸送需要に応えるため,在来型の交通体系の補完改良を主な目的として新交通システムの開発が進展している。
首都高速道路公団及び阪神高速道路公団により,49年度末現在それぞれ首都圏において108キロメートル,阪神圏において91キロメートルの都市高速道路が供用されており,141キロメートルが施工中であるのを始め,都府県等によって一般道路の整備も進められているが,都市における道路の新設拡張は非常に困難となってきており, 〔2−2−25図〕及び 〔2−2−26図〕のとおり道路交通の混雑状態が続いている。この結果,バス,タクシー等の路面公共輸送機関は,運行速度の低下や定時性の確保難等から都市交通機関としての信頼性を失い,これが利用客減少傾向の一因をなしており,またトラック輸送においても輸送効率が低下している。

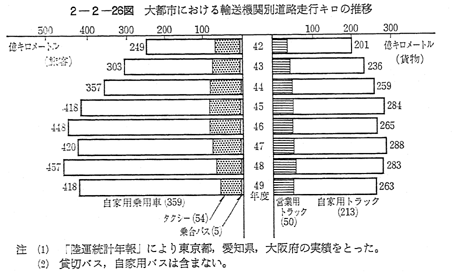
以上のような道路交通の実情にかんがみ,運輸政策審議会答申「大都市におけるバス・タクシー輸送のあり方及びこれを達成するための方策について」(46年)等に基づき,バス路線網の再編成,バス優先・専用レーンの設置 〔2−2−27図〕,深夜バスの運行 〔2−2−28図〕,終車時刻の延長,ミニバス,デマンドバス,停留所施設の整備等によるバスの信頼性の確保及びサービスの向上を図るとともに,48年度より新住宅地バス路線開設費補助,49年度より大都市バス施設整備費補助を行っている。他方,タクシーについても,東京と大阪にタクシー近代化センターを設置し,また,乗合タクシー制度の拡充を図る等サービスの改善を図っているが,49年の大幅な運賃改定以降は需要が一段と減退している。
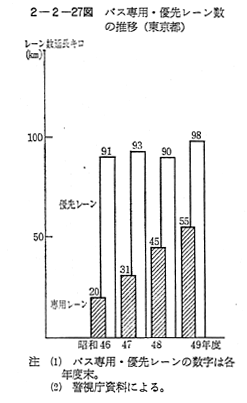
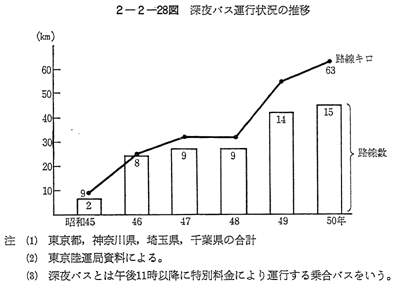
次に,都市内における貨物輸送の大半を担っている自動車による貨物輸送については,旅客輸送の場合と異なり,その鉄道への転換はほとんど考えられず,道路混雑の影響は深刻である。すでに述べたように,トラックの集配効率は大幅に低下し,また労働集約性が高く省力化にも限界があることからコストアップが顕著となっており,流通合理化の見地からも問題となっている。
|