|
第3節 地方交通大都市圏以外の地域の人口は, 〔2−2−17図〕のとおり30年代以降減少を続けてきたが,最近では増加に転じており地方における人口の定着化傾向がみられる。 しかし,各地方圏についてみると, 〔2−2−29図〕のとおり人口20万人クラス以上の地方都市の発達が顕著となっている反面,依然として過疎地域にあっては人口の減少傾向が続いている。
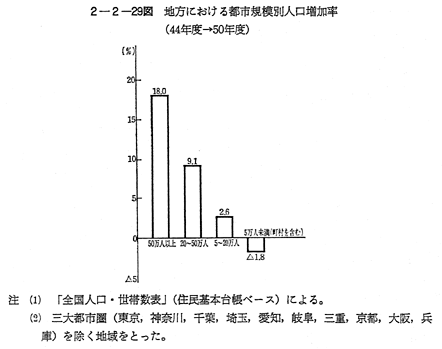
まず,人口が増加している地方都市では,最近, 〔2−2−30図〕のとおり地方圏において急速な普及を示している自家用乗用車を中心とする自動車の増加によって,大都市の場合と同様,道路交通の混雑をみせているところもあり,増加する輸送需要に対処するため,都市によっては鉄道等の大量公共輸送機関の整備を図ることが必要となっている。このため,すでに札幌市においては46年より地下鉄(12キロメートル)が営業を開始し,50年4月現在13キロメートルを建設中であるほか,福岡市においては地下鉄(15キロメートル)の建設が進められ,また北九州市においてはモノレールの建設が検討されている。さらに,50年8月には仙台市及び広島市について,地下鉄の整備を図るべきである旨の地方陸上交通審議会の答申が出されている。
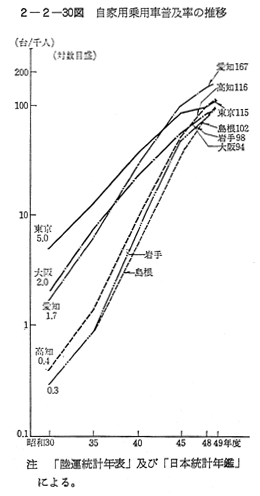
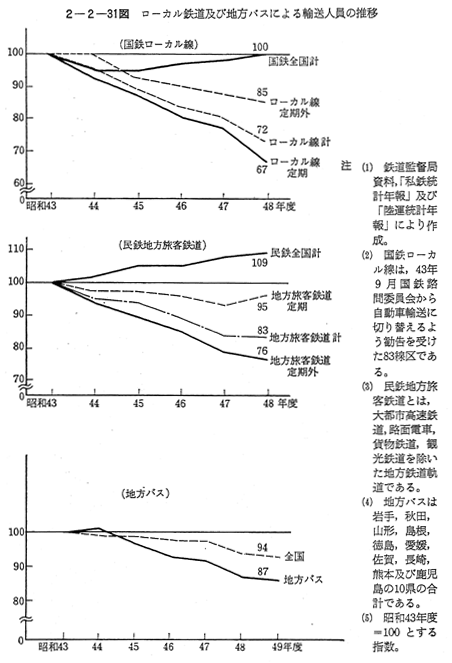
このため,人件費等コストの大幅な上昇もあってこれら交通機関の多くは不採算化しており,運行回数の削減,路線の休廃止等サービスの悪化をもたらし,営業の維持すらも困難になっているものが多い 〔2−2−32表〕。また,離島航路や離島航空においても,輸送量の減退等から経営状況が悪化している。
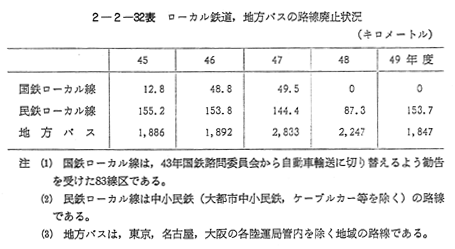
|