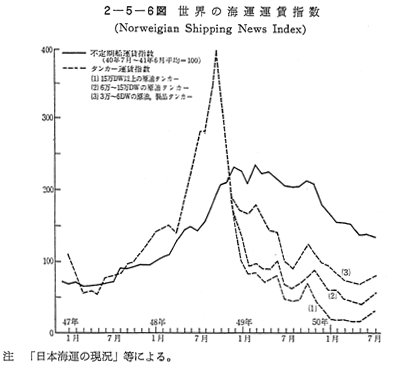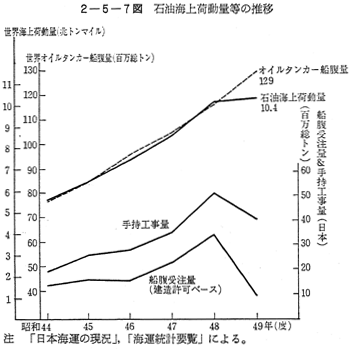|
2 海運・造船
海運及び造船業は,産業の発展と世界貿易の拡大を背景としてその経営は比較的順調に推移してきたが,石油危機を契機として深刻な事態に直面することとなった。
49年度の海運業の経営状況は,外航海運をみると石油,木材等の輸入量が減退ないし伸び悩んだものの,48年から49年にかけての好市況時に締結された高運賃水準の運送契約が持続したこと等のため大幅な増収となり,(2-5-1表)にみるように,人件費,燃料費を中心とする大幅な経費増にもかかわらず経常利益も増加した。
しかし,世界の海運市況は, 〔2−5−6図〕にみるように,49年に入ってから,まずタンカーが急速に低下し,50年に入っても低迷を続けている。その後不定期船も急速に低下し,不況の様相を一層強めている。これは原油価格高騰に起因する原油の海上荷動き量の停滞と世界的な経済不況によるものであるが,停滞は,一時的な景気後退というよりも原油価格の高騰による世界の経済構造の変化に基づくものであり,その影響は長期かつ深刻なものがあると予想される。
すなわち, 〔2−5−7図〕のとおり世界の石油海上荷動き量は,48年までの過去4年間トンマイルベースで年平均16%の伸び率で推移してきたが,49年には前年比1%台の横ばいになったのに対し,世界のタンカー船腹量は,過去5年間重量トンで年平均12%の伸び率で推移してきており,49年にも依然として12%の高い伸び率を続けている。この結果,タンカーの船腹過剰が表面化してきており,世界のタンカー船腹量約2億4,000万重量トンのうち50年年央には2,700万重量トンを越える船腹が係船されている。加えて,石油危機前の好況期に造船所に発注されたタンカーは49年度末現在約1億5,600万重量トンあり,事態を一層深刻なものとしている。
また,不定期船市場には,タンカー不況により,かなりの鉱油兼用船が流入しており,さらに発注中のタンカーのバルクキャリアーへの転換の動きが大きいこと等からみて,不定期船市況の急速な回復は難しいものと思われる。このような市況の低迷は,今後,高運賃水準の運送契約が切れていくに従い,我が国海運企業の経営を大きく圧迫することとなろう。
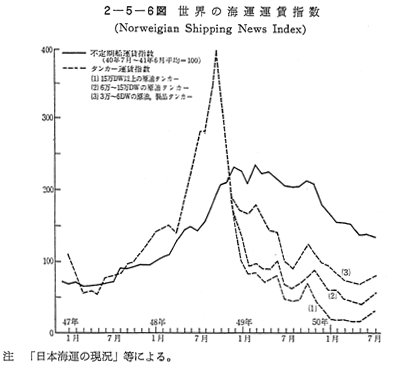
一方,国内景気の後退から木材輸入需要が激減し,船腹過剰の状態となっている近海海運市場の動向が海運経営にとって大きな問題となっている。一般に近海船は,取引の実態,相手国の港湾事情等により中小型船に限定され,船舶の大型化,近代化等の合理化が困難であるため,我が国における船員費を中心とする諸経費の上昇は,この市場での日本船の国際競争力を喪失させ,貸本船主は深刻な危機に立たされている。
内航海運業にあっては国内景気の後退から荷動きはトンキロで前度年比7.7%の減少となったが,運賃の上昇もあって営業損益はほぼ横ばいとなり,営業外損益の好転により経常損益は48年度に比べ好転している。しかしながら49年度後半以降は不況の長期化により厳しい状況になりつつある。
他方,旅客航路事業は,諸経費の高騰及び需要の停滞により49年度の経常収支率は83.4%(前年度90.9%)となり,その経営は悪化している。特に国庫補助対象離島航路にあってはその経常収支率が57.3%(前年度65.0%)となっている。
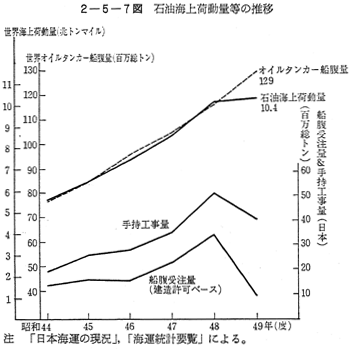
また,進展の著しかった長距離フェリーも貨物輸送の減退による需要の伸び悩みと諸経費の高騰により経常収支率80.9%(前年度90.3%)とその経営状況が悪化してきている。
以上のような情勢に対処して,外航海運にあってはタンカーの減速運転,係船等による船腹調整を行っている。また,内航海運業にあっては新造船の抑制,フェリーを含め旅客航路事業にあっては経費の節減,減便等の対策を講じている。
なお,このような海運における深刻な経営問題が船員雇用にも大きな影響を与え,有効求人倍率の急激な低下,船員養成機関の新卒者に対する海運業からの求人の大幅な減少等例年になく厳しい雇用情勢となっており,船員の雇用対策が必要となっている。
さらに以上のような海運業の動向は造船業にも直接的な影響をもたらしつつあり,特に世界的な規模での船腹過剰の状態は今後長期間にわたるものと予想されており,世界の新造船の約50%を建造している我が国造船業に及ぼす影響も大きい。
我が国造船業の49年度経営状況は,主要大手の生産額が3兆2,000億円余と前年度比25.8%の増加となったが,石油危機前の受注が固定船価方式であり,その後材料費,人件費が大幅に上昇したため経常利益は1,571億円余と約30.5%減少し,一部の企業では赤字を計上した。50年度の賃上げが当初の予想より低水準に収まったとはいえ,固定船価の手持工事は今後も大きな経営圧迫要因となっている。
しかし,今後の造船業にとって最も大きな問題は,工事量の減少による操業度の低下である。我が国の造船業は,49年度末現在約4,000万総トン(主要造船所35工場分)約2.5年分の新造船手持工事量を有しているが,49年度には受注の極端な減少と,一部の既受注船の解約等もあって,前年同期に比べると手持工事量は20%の減少となっている。ちなみに,49年度の新造船受注量(建造許可ベース)は935万総トンで,前年度比72.3%の大幅減であった。現在の見通しによれば,49年度の工事量を100とした場合,51年度は70,52年度は50の工事量に低下するものと予想されている。
このため,造船業界でも,新規採用の中止,残業規制,他部門への配置転換等により余剰労働力の調整を図るとともに新規需要の開拓に努めているが,すでに中小造船業の経営危機等が現実のものとなっており,中小造船業の救済融資等の措置を講じている。
|