|
1 発展途上国に対する運輸関係経済協力
49年の経済協力総額(政府ベース・民間ベース含めてわが国から開発途上国へ流れた資金の総額)は29億6,230万ドルと48年の58億4,420万ドルのほぼ半額となった。この結果,その対GNP比も48年に記録した1.44%を大きく下まわり,0.65%と国際的目標値1%を再び割ることとなった。
運輸関係技術協力は,主として国際協力事業団(JICA)を通じ実施されている。
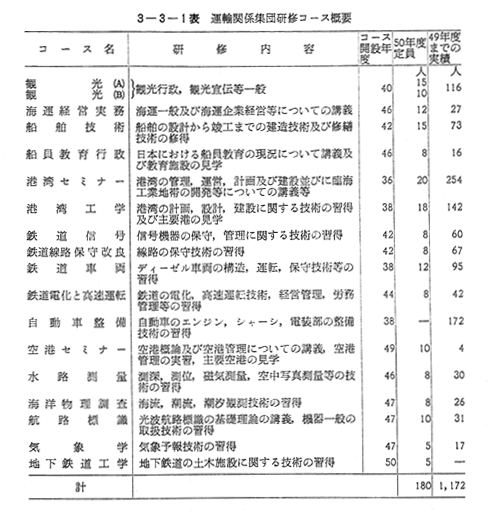
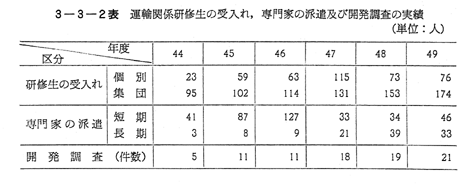
研修生の受入れは,集団研修と個別研修とに分けられる。集団研修は,実施時期,研修内容等が予め定められていて,開発途上国から応募してきた研修生に対して実施されるものである。50年度に実施されている集団研修コースは 〔3−3−1表〕のとおりである。また,個別研修は,開発途上国からの要請によりその都度実施されるものであり,要請内容に応じそれぞれの関係機関で研修が行われる。49年度までの運輸関係研修生の受入れ実績は 〔3−3−2表〕のとおりである。
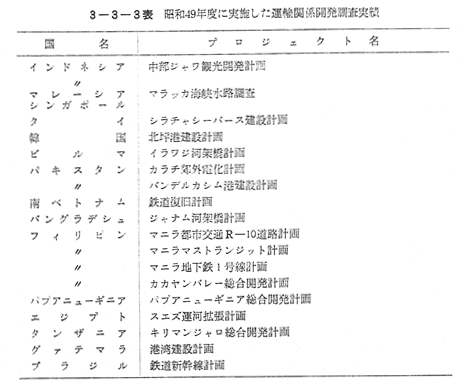
マラッカ・シンガポール海峡における船舶の航行の安全を確保するため44年以降,同海峡の水路精密測量をインドネシア,マレーシア,シンガポールの沿岸3カ国と共同で実施してきたが,49年度に実施された第4次測量事業(49年7月から12月まで測量を実施し,50年1月から3月まで測量データの解析整理を行い,同年4月関係4カ国の最終打合会が開催された。)をもって同海峡の水路測量は全て完了した。なお,本測量事業においては(財)マラッカ海峡協議会が大きな役割を果した。
開発途上国のプロジエクトに対する政府ベースによる資金協力は,各種プロジェクトの完成に必要な資材及び役務の購入に必要な円資金を無償で供与する賠償及び無償援助と長期低利で円資金等を貸付ける円借款に大別される。賠償(賠償に類するものを含む)としては,フィリピン共和国との間の賠償協定に基づく賠償,ビルマ連邦との間の経済及び技術協力協定に基づく協力及び「大韓民国との間の財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力協定」に基づく協力等があり,これらが従来に引き続き行われた。円借款としては,49年8月に締結された対マレーシア円借款協定においてジョホールバール造船所建設等のプロジェクトが約束されたほか,49年9月には対インドネシア円借款協定で内航船,浚渫船等のプロジェクトに132億6,000万円,49年10目には対エルサルバドル角借款協定で新空港建設のために57億円,49年12月には対ケニア円借款協定で空港機材プロジェクトに7億5,300万円が約束された。さらに50年4月には対エジプト円借款協定においてスエズ運河拡張工事のために380億円,7月には対ガボン円借款協定で貨車260両供給のために30億円の資金協力が約束された。
開発途上国との国際協力の一環として,各種の国際会議が開かれ多くの成果を収めた。50年2目にエスカップ総会がニューデリーで開催されたのを初めとして,東南アジア運輸通信調整委員会(49年12月,マニラ),東南アジア開発閣僚会議(49年10月,マニラ),日・タイ経済合同委員会(50年4月,バンコック),エカフェ貿易委員会及び同運輸通信委員会(49年12月,バンコック)等が開かれ,運輸関係プロジェクト及び海運問題等について活発な討論が行われた。
運輸関係プロジェクトに係る経済協力は今後ますます増加する傾向にあるが,運輸関係プロジェクトのように高度にシステム的性格を有する援助について十分な効果をあげるためには計画策定の段階から調査設計,施工監督,運営管理に至るまでの一貫した技術協力を行うことが必要とされる。また,公共性が高く,多額の資金を要する運輸関係プロジェクトについては,よりソフトな条件の借款及びグラント(贈与)による資金協力が必要とされ,今後,この方面の資金協力の充実が望まれる。さらにまた,最近の技術協力の問題点の一つとして民間における技術力の不定がある。このため,港湾など政府の技術水準の高い部門についてはこれらをより活用する方策を検討する必要がある。
|