|
2 日本の国際航空輸送状況
49年度の我が国の国際航空輸送実績は 〔III−1表〕のとおりである。国際航空輸送量のバロメーターである有償トンキロは,29年に我が国の国際定期航空が発足して以来,毎年度15%以上の増加を続けてきたが,49年度は大幅に低下し,0.1%の増加にとどまった。

輸送力についてみると,飛行時間,飛行距離は,前年度とほぼ同じであったが,有効トンキロは,北回り欧州線・東南アジア線のB-747型機の導入をさらに進めたため,6.8%増加した。
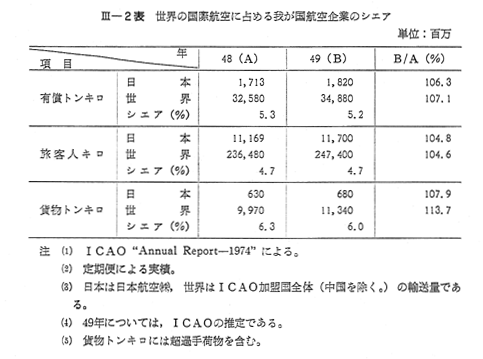
次に,我が国の国際航空輸送量を世界の国際航空輸送量と比較してみると 〔III−2表〕のとおりである。世界的に航空輸送が伸び悩んだ中で我が国も例外ではなく,国際航空輸送はひとつの転機に立たされていると言えよう。世界の国際航空に占める我が国のシェアは,前年に比べ若干低下したが,順位は,旅客人キロで世界第4位,貨物トンキロ及び有償トンキロでそれぞれ世界第5位と前年度と同じであった。
49年度の日本航空(株)の国際線旅客輸送量は,旅客人員228万7,000人,旅客人キロ126億3,800万人キロであり,前年度に比べ,それぞれ11.4%の減少,2.2%の増加であった。過去20年間,人員,人キロとも,10%を超える高い伸びを続けていたのに比べ,様相は一変した。これは,景気の停滞及び消費の減退により全体的な航空需要が落ちこんだことに加え,49年4月以降台北路線が運休となったため,東南アジア方面での競争力が弱まったこと等に起因するものと思われる。一方,旅客座席キロは,北回り欧州線等で大型化を進めたため前年度に比べ5.9%増加し,この結果,座席利用率は48年度より2.1ポイント低下して59.5%となった。
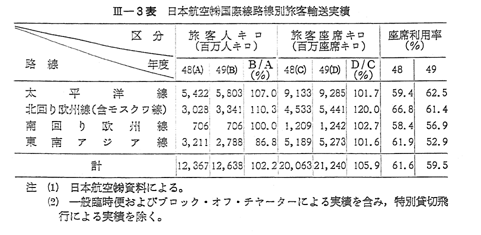
次に,49年度の我が国出入旅客について日本航空(株)の積取比率をみると 〔III−4表〕のとおりであり,日本人旅客,外国人旅客とも前年度に比べ若干低下し,合計で29.9%となった。我が国航空市場の競争の激しさを示していると言えよう。特に,東南アジア線における積取比率の低下が目立つが,これは年間約34万人(48年度)の需要を有した台北路線の運休が響いていると言えよう。同路線は,旅客人員の絶対数が大きいため,最終的積取比率に与える影響が大きい。
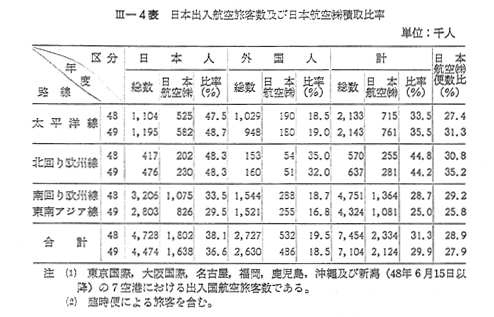
49年度の日本航空(株)の国際線貨物輸送量は,世界経済の停滞を反映して,8万6,000トン,6億5,031万トンキロと前年度に比べ,それぞれ8.8%,4.5%の減少となり,48年度においては重量,トンキロでそれぞれ22.9%,22.3%の増加を示した航空貨物についても,情勢は一変することとなった。また,日本出入航空貨物量も 〔III−5表〕のとおり,48年度の26.1%の増加から一転,4.3%の減少となった。これらは,内外経済の停滞により,貨物需要が落ちこんだことによるものと思われる。
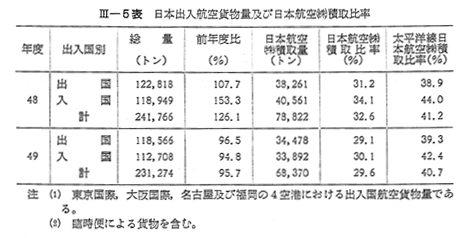
日本航空(株)の積取比率は,出国,入国とも前年度に比べ若干低下した。これは,台北路線の運休及びそれによむ東南アジア方面における競争力が弱まったことが影響していると言えよう。
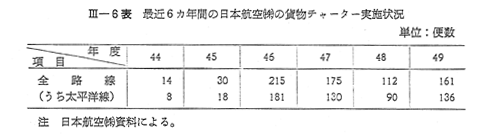
なお,国際航空貨物輸送に係る複雑な手続事務を迅速かつ正確に処理し,国際航空貨物の物流の改善等を図るための情報システム化が必要となっているが,運輸省では,48年度から民間団体である国際航空貨物輸送情報システム開発協議会(JACIS)の協力を得て,国際航空貨物輸送情報シスムの整備に着手しており,現在,輸入業務を対象として情報処理システムの開発を先行的に進めている。
49年度の我が国の航空関係国際収支は 〔III−7表〕のとおり,4億3,700万ドルと,前年度に引き続き大幅な赤字となった。項目別にみると,旅客運賃の赤字が大きな比重を占めている。これは,日本人の海外旅行者が多い反面,日本航空(株)の積取比率が低いことによる。又,港湾経費が赤字に転じているが,これは燃油費の上昇によるものと思われる。
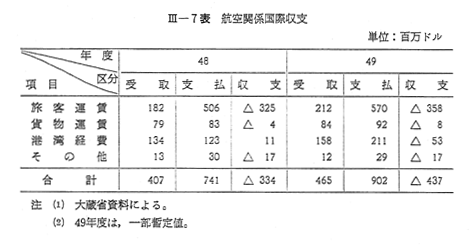
|