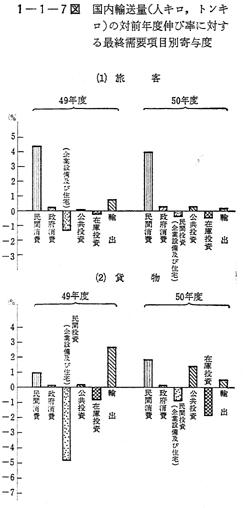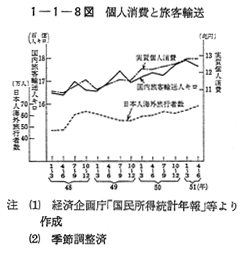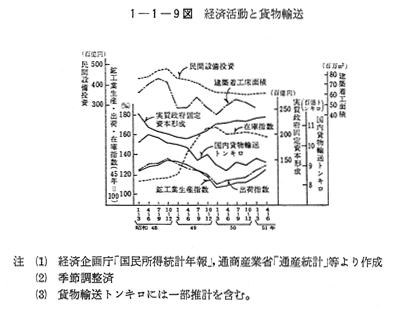|
(3) 国内輸送
国内輸送量の対前年度伸び率に対する最終需要項目別寄与度をみると 〔1−1−7図〕のとおり,旅客輸送については民間消費が49年度,50年度とも増加の主因となっており,50年度においては公共投資の増加に対する寄与度が前年度に比べ大きくなっている。
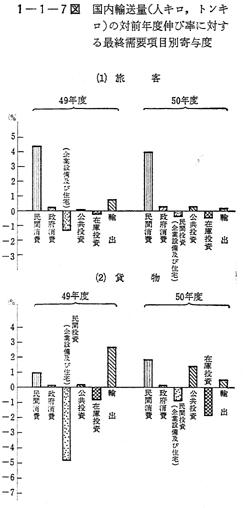
また,貨物輸送については49年度,50年度とも民間消費と公共投資が増加要因となっており,一方民間投資と在庫投資が減少の要因であった。民間投資は49年度においては,減少の主因となっていたが50年度においては住宅投資の堅調により減少寄与度が小さくなり,代って50年度は在庫投資が減少の大きな要因となった。
なお,49年度中に好調を持続した輸出は50年度には停滞し,旅客,貨物とも増加要因となったもののその寄与度は,49年度に比べ小さくなった。
旅客輸送量は石油危機のあと48年度,49年度の両年度において低い伸びにとどまっていた自家用乗用車の輸送量が50年度において大幅な増加を示したものの,他の輸送機関は横ばいないし微減となった。このため,総輸送量においては,前年度を上回ったものの伸び率は前年度に引き続き低いものとなった。
一般に国内旅客輸送量は実質個人消費の動きと深い関係をもつが,49年10月-12月期に一たん減少した実質個人消費は50年に入ると期を追ってゆるやかな上昇を示し,一方,旅客輸送量も,前記自家用乗用車の送量増に支えられて実質個人消費の動きとほぼ軌を一にして推移した 〔1−1−8図〕。
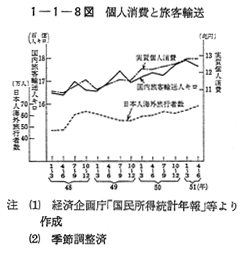
次に貨物輸送については,49年度に前年度比で輸送トン数11.0%減,輸送トンキロ7.7%減のあと,50年度は我が国が景気の回復過程にあったのにもかかわらず輸送トン数は前年度比1.1%減,輸送トンキロは同40%減となった。
国内貨物輸送量は我が国の産業構造における第三次産業のウエイトの増大,輸送量にわずかしか反映しない高価格品の生産の増加及び我が国の輸出依存度の増大等により,ここ数年GNPの伸びとかい離をみせている。さらに50年度においては,公共工事の堅調を反映して輸送距離の短かい砂利・砂・石材の輸送量が横ばいであったため,トン数の減少幅は小さかったが,トンキロについては鉱工業生産指数の前年度比3.6%減とほぼ見合ったものとなった。
この結果,貨物輸送トン数は3年連続,輸送トンキロは2年連続の減少となり,輸送トン数は45年度の水準,輸送トンキロは46年度の水準を下回るまでに後退した。
貨物輸送の動きを期を追ってみると,48年7-9月期から減少を始めた貨物輸送トンキロは期を追って減少し,50年4-6月期にはボトムとなった。その後生産,出荷の増加及び政府の数次にわたる不況対策により,実質政府固定資本形成は50年中砥増加傾向を維持したが,民間設備投資の不振等により貨物輸送トンキロは増加基調にありながらも51年-3月期まで増減をくり返した。なお,51年度に入り4〜6月期には再び減少となっている 〔1−1−9図〕。
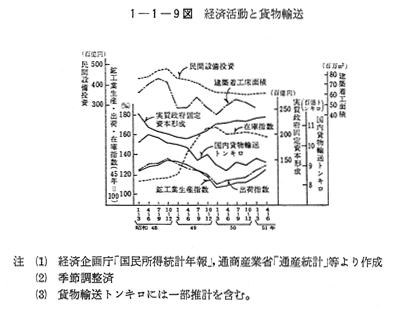
|