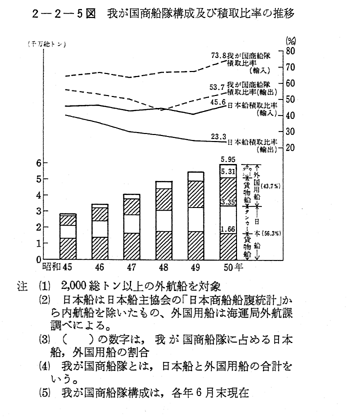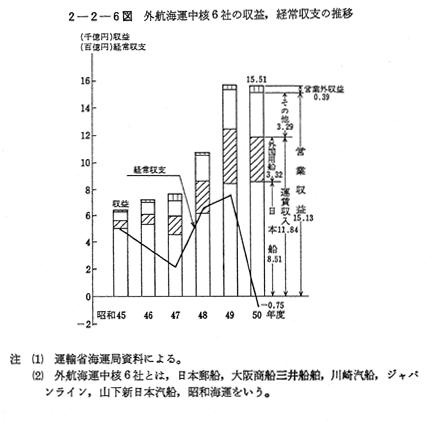|
1 我が国商船隊の構造変化
(1) 日本海運の意義
我が国は重要資源の多くを遠く海外に依存しており,このように資源を海外依存する依存度は,他の主要国に比べて極めて高く,しかも,その資源の輸入先はあまねく世界にわたっている。したがってその輸送のほとんどすべてを長大な距離の海上輸送によっている。さらに,我が国は,これら資源を加工して高い付加価値を有する工業製品を生産し,さらにそれら製品の多くを,再び海上輸送によって世界の各地に輸出し,これによって高い所得を得るとともに所要の外貨を獲得している。
このように我が国経済は,基本的に外航海運に対する依存度が極めて高い構造を有しており,したがって安定的な海上輸送体系の確保が,強い国民経済的要請となっている。
我が国海運は,過去数十年にわたって,計画造船を軸として整備された日本船を中心とする商船隊を自ら保有することにより,このような国民経済的な要請に直接的に応え,もって我が国の経済発展に寄与してきたが,一方こうした商船隊の存在は,間接的には,我が国貿易全体の運賃水準の大幅変動に対する抑止力としても,大きな意義を有してきた。 我が国の経済は,この間に例をみないような高度成長を遂げ,その経済基盤も著しく強化された。そして石油危機を経た今日では,その基盤を踏まえて,一転して安定した経済を指向しようとしている。しかし,今後我が国がこのような安定成長時代を迎えても,その重要資源の多くを海外に依存し,それを加工した製品を海外に輸出するという我が国経済の海外依存度は,依然として大きいと思われるから,このような物資の安定輸送という我が国海運に対する国民経済的な要請も,変わるものではないといえよう。
また,更に現在は,我が国全体の国際収支が黒字基調にあり,積極的な外貨節約に対する国民経済的なニーズはややうすれているものの,我が国商船隊が輸送を受け持つことにより実質的に年間数十億ドルもの外貨が節約されており,長期約にはこの面での我が国海運の意義もまた今後とも大きいものがあるというべきであろう。
(2) 日本船の競争力低下と外国用船の増大
(1)で述べたごとく我が国の経済活動に依然として重要な意味をもつ我が国商船隊(外国用船を含む。)の構成は,ここ数年日本船が伸び悩んでいるのに対し,外国用船の増大が目立っている 〔2−2−5図〕。昭和50年6月末の外国用船量は2,600万総トンと,我が国商船隊の実に43.7%を占めるに至っており,なかでもタンカー以外の貨物船にあっては,外国用船船腹量が日本船船腹量を上回るに至った。
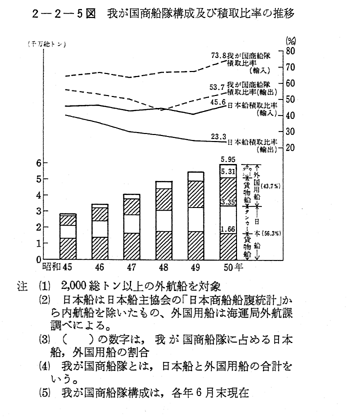
このように元来限界的な部分において,日本船の補完的な役割を担うべきものとされていた外国用船が,現在では我が国商船隊のほぼ半分を占めるに至ったのは,近年の輸送需要の急激な増大に我が国海運企業の投資能力が追いつかなかったこともその一因であるが,最大の原因は日本船の競争力低下にある。すなわち,近年船員費を中心とする諸経費が大幅な上昇を示し,特に船員費の上昇は発展途上国の低賃金の船員を配乗した外国船との格差を大きくし,日本船の国際競争力を著しく低下させるに至った。コンテナ船,大型タンカー,大型鉱石専用船等の資本集約的な船舶にあっては,この影響は比較的小さく,なおある程度の国際競争力を維持しているものの,コストに占める船員費のウエイトが大きい近海船などの中小型船においては,国際競争力の低下が深刻な問題となっている。
さらに,これらの外国用船の中には,単純な外国用船のほかに,いわゆる仕組船(日本の海運会社が長期間用船する目的で日本の造船所の船台を外国の船主に斡旋し,建造させた船),チャーター・バック船(諸経費の上昇により採算の悪化した日本船を海外に売船し,発展途上国の船員を配乗することにより,コストの低減を図ったのちに,日本の海運会社が再び用船するもの)と呼ばれるものが含まれており,近年それらの増加が著しく,現在では外国用船のうちかなりの部分を占めるに至っている。
一方,このような日本船の国際競争力低下を反映して,船員費の低減を目的として日本船に発展途上国船員を配乗した船舶がここ一,二年の間に急速に増大している。これは,日本の海運会社が所有する日本船を外国に裸用船に出し,これに外国の用船主が配乗権をもって発展途上国船員を配乗したものを,日本の海運会社が再び用船するもので,日本船ではあるものの本質的には仕組船,チャーター・バック船と同一の背景をもつものといえよう。
このような我が国商船隊の船隊構成の変化は,ここ一,二年の国際海運の景気の後退によって一層強められ,にわかに表面化するに至った。
すなわち,資本集約的な船舶以外の船舶の,このような国際競争力の低下は,既に40年代の半ばかり次第に顕在化しつつあったが,50年代に入るまでは世界経済の好調に伴い外航海運は概ね好景気を続け,このような国際競争力の低下した船舶の減益を好調な部門の収益でカバーし,全体として黒字の中で維持することができたので,船員の雇用との関連もあり,近海船部門を除いてあまり急速に表面化してこなかった。しかし,48年末の石油危機を契機とする世界経済の不況とこれに伴う海上荷動きの停滞は,我が国海運業の経営に大きな影響を与え,海運企業は空前の好決算となった49年度に比べ,50年度は 〔2−2−6図〕にみられるごとく大幅な減益を示し,これに伴い各企業は企業全体の採算維持のため,これら国際競争力の低下した不採算船への思いきった対策を迫られることとなった。その結果,これらの船舶を海外売船し,代ってコストの低い外国船や仕組船を用船したり,チャーターバックするケースが相次ぎ,さらにはこれらの船を裸用船に出し,外国船員を配乗後再用船する形も登場するに至った(日本船の海外売船量は,49年度の137隻106万総トンから,50年度には160隻205万総トンヘと増加した。)。一方これに伴い,我が国船員の配乗すべき船舶は伸び悩み,その結果,助成対象外航海運40社の平均予備員率は,51年3月末現在69.1%という高い率を示すに至った。
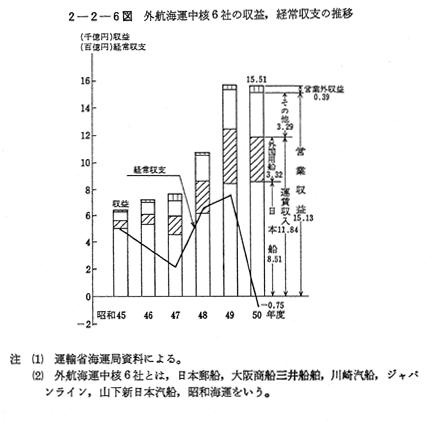
(3) 今後の方向
(1)で述べたごとく,我が国海運は我が国経済の要請に応え,その発展に寄与してきた。特に,日本船はそうした我が国商船隊の中核としてこれまで重要な役割を担ってきたといえよう。そして,このような日本船の意義は,安定成長時代に入った我が国経済にとっても,今後とも基本的には変わらないものと思われる。したがって,我が国貿易物資の輸送を安定的に行うためには,今後もできるだけ多くの船舶を我が国のコントロール下に置くことが望ましく,このような観点から,今後とも一定量の日本船を確保していくことが我が国経済にとって必要であると思われる。特に国際情勢は今後とも政治・経済の両面において激動することも予想され,我が国をとりまく状況はいかに変化するか予想し難い。そのような場合において,我が国の経済社会を維持するためには,貿易物資を確実安定的に輸送することができる日本船の確保はナショナルセキュリティ上是非とも必要であると思われる。
しかし一方,海運界は国際的に自由で開放的な体制のもとに厳しい国際競争下に生きてきており,我が国海運はこうした競争に打ち勝って自らの経営安定を図っているのである。したがって,このような経済合理性を追求していく限り,各海運企業が国際競争力の低下した日本船に比べコストの安い外国用船の活用に頼ることはある程度やむを得ないであろう。しかし,そのような場合にあっても,安定輸送の確保の観点からみれば,外国用船の中でも単純な外国用船よりその運航について我が国の支配が安定的に及ぶ仕組船等を極力利用することが望ましいといえよう。
もっとも,このように我が国の海運業がその企業合理化の立場から外国用船などの活用を進めるという状況が更にこれ以上増大していくと,やがて日本船は我が国海運の中の極めて限定的な分野においてのみ保有されることともなりかねず,これは前述の如き我が国商船隊に課された我が国貿易物資の安定輸送という使命からみて看過し得ない問題であると思われる。
このような情勢にかんがみ,我が国海運が今後とも一定量の日本船を保有しつつ国際競争に耐え,発展していくためには,従来の発想を転換し,船員の配乗制度,予備員制度のあり方等の船員問題について抜本的に検討すべき時期にきているものと思われる。
またそれとともに我が国海運としては資本集約度の高いコンテナ船等,国際競争力の比較的強い部門の拡充,超自動化船等の導入,競争力ある新規分野の開拓等により高収益部門の積極的拡充による体質強化を図り,全体としての国際競争力の維持に資していくことが期待されよう。
|