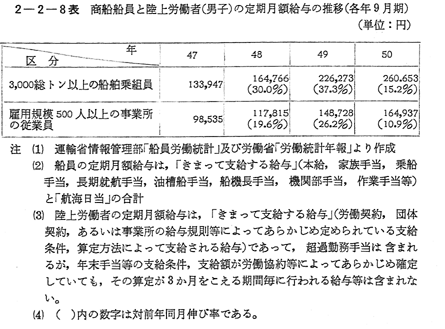|
2 船員の雇用不安
(1) 雇用の現状
戦後のわが国外航海運の急速な回復と発展過程において,日本人船員が,その優秀な技術等により果してきた役割は大きなものがあった。
この間の我が国経済の高度成長下における船賃の需給は,ひつ迫していたが,最近の雇用状況は 〔2−2−7図〕でみるとおり,商船船員の有効求人倍率は,47年に急落してのち,48,49年と低迷を続けた。さらに50年から51年8月にかけては一層の落ち込みを見せ,51年8月には0.27と1.0を大幅に割り,一般産業の0.67よりも著しく低いものとなっている。また,50年度の船員職業安定所における船員失業保険受給者実数は,漁船船員を含み,対前年度比39.0%増となり,51年3月における失業保険初回受給者数は,対前年同月比29.5%増となっている。
一方,出勤待機,有給休暇等の予備船員の状況を示す予備員率も, 〔2−2−7図〕でみるとおり,46年から漸増傾向を示し,50年には急激に上昇し,50年10月1日現在,外航船員予備員率は,64.8%の高率に達している。

このような船員労働力の需給バランスの逆転は,海運企業が,前述のように,不経済船の海外売船,あるいは船舶の大型化,自動化等による合理化対策を進めるとともに, 〔2−2−8表〕のとおり人件費が高騰している日本人船員を避け,低廉な発展途上国船員を乗り組ませた外国船を用船する傾向が強まったこと等により,雇用需要が大幅に減少したことが,主な要因と考えられる。
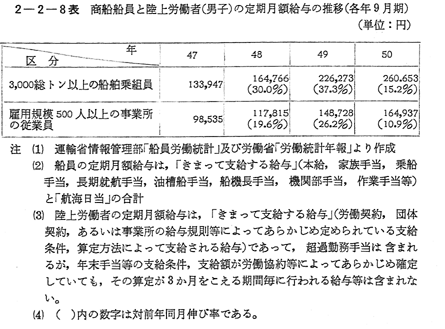
諸外国海運の競争力確保策をみると,英国をはじめとする先進海運諸国にあっては,船員の雇用形態において我が国の終身雇用制及び予備員制度とは異るものが多く,さらに自国船員との混乗という形で,発展途上国の船員を導入し,船員費の低減を図ること等の方法により,我が国と同様の高賃金社会の中にあって自国海運の国際競争力の維持に努めているのが実情である。これに対し,これまで我が国海運企業においては,日本船に代えて外国用船を活用することによりコストの低減を図っていることが特徴的であるといえる。
(2) 雇用不安への対処
このような船員雇用をめぐる厳しい情勢に対処するため,運輸省においては,当面の雇用安定対策として,近海部門からの離職者に対する個別延長給付制度,中高年令船員に対する個別延長制度及び職業補導延長給付等の失業保険制度の活用により,失業船員の生活保障と再就職の促進を図るとともに,船員職業安定所の窓口において職業相談,就職指導等の雇用相談業務を実施している。
以上,当面の雇用安定対策のほか,運輸省としては,最近における船員労働力の需給基調が変化してきていることにかんがみ,51年度において船員雇用対策基本計画(5か年計画)を策定することとし,長期的な展望にたった船員需給見通しを明らかにしつつ,今後の船員雇用の安定のための基本的考え方を盛り込むこととしている。
一方,近年の世界における船舶の技術革新には目覚ましいものがあり,近い将来において船舶は,その運航経済性・安全性の一層の向上及び船内労働の軽減等を目的とした超自動化船へ推移して行くことが予想される。
これが船員の技能及び雇用の問題に与える影響も少なくないものがあり,船員の資質の向上のための再教育,船内就労体制の見直し等解決のための諸施策が必要となろう。
さらに,今後の安定成長下における海運業にあっては,企業体質の改善,国際競争力の維持等のため,我が国船員と発展途上国船員との混乗を含め,現在の船員の配乗制度,予備員制度等の再検討の動きがますます強まることとなろうが,これら問題の検討に際しては,常に船員の雇用の安定ということを念頭に置く必要がある。
以上述べた問題は,いずれも労使間において相互信頼の上に立って十分話し合うことにより,具体的な解決の方法を見出すことが下可欠であるが,同時にこれを踏まえつつ,効果的な船員雇用対策を確立していくことが望まれる。
|