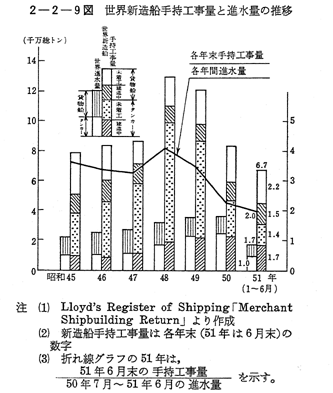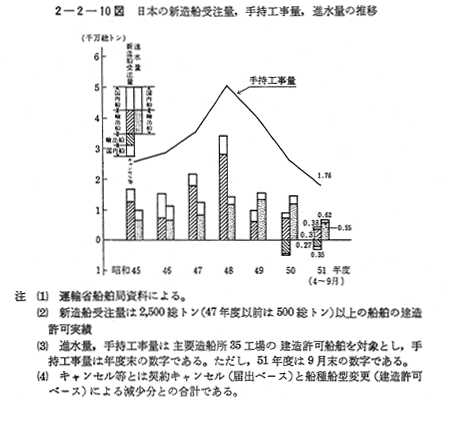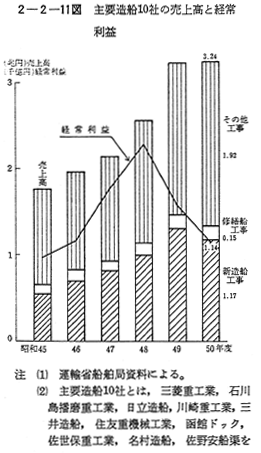|
3 我が国における造船不況の深刻化
(1) 新造船受注量及び手持工事量の減少
最近における世界海運の不況は,世界造船業にもその影響を直接及ぼし,世界の新造船受注量は激減し,新造船契約のキャンセルとも相まって, 〔2-2-9図〕のとおり手持工事量は,51年6月末現在で6,710万総トンと45年当時の水準を下回るまでに落ち込んだ。一方,進水量は,48年以前の大量受注を背景に,49年以降も高水準を維持している。このため51年6月末の世界の手持工事量と年間進水量との比は2.0と48年末の4.1に比べて激減した。
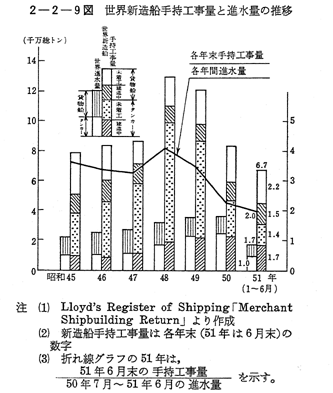
次に,我が国造船業についてみると, 〔2-2-10図〕のとおり世界とほぼ類似の傾向をたどっているが,わが国造船業では世界に比べタンカー,特に超大型タンカーの占める割合が大きいため,タンカー不況の影響を大きくこうむっている。
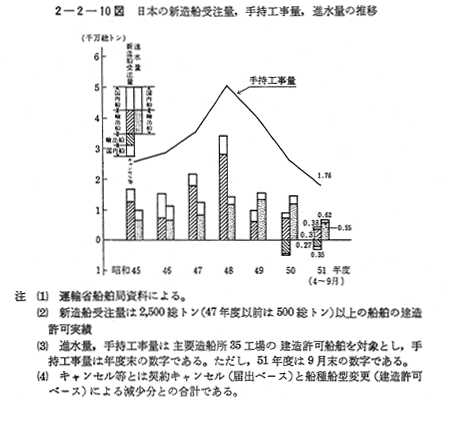
すなわち,新造船受注量(建造許可実績)は48年度から一転して49,50年度は激減し,特に従来その大宗を占めていたタンカーは,50年度にわずか60万総トンの受注と,48年度の2.2%に過ぎない。これに加え新造船キャンセルは,49年度~51年度(4~9月)合計で86隻,580万総トンに達し,このほか,船種船型変更による減少分(360万総トン)を加えると,計940万総トンの手持工事が消滅したことになり,51年9月末現在の主要造船所35工場の手持工事量は1,760万総トンと落ち込んだ。
一般に船舶は注文生産品であり,造船所の安定操業のためには先物の工事を確保する必要があるが,51年6月末現在のAWES(西欧造船工業会)の12か国と我が国の手持工事量を比較すると,前者は年間進水量の2.2倍であるのに対し,我が国のそれは1.4倍と下回っており,我が国の方が厳しい状況にあるといえる。
(2) 経営の悪化
最近における造船業の売上高と経常利益の推移を主要造船10社についてみると 〔2-2-11図〕のとおりであり,売上高は,45年度以降年々増大し,50年度においても49年度をわずかに上回っている。このうち新造船工事部門についてみると,49年度をピークとして50年度は減少しているもののなお48年度を上回っている。これは,そのほとんどすべてが石油危機以前に契約した新造船の建造による売上げが寄与したものとみられる。一方,陸上プラント等造船以外のその他部門は,逆に毎年増勢を続けており,50年度においては,造船部門の売上げ減を補った。
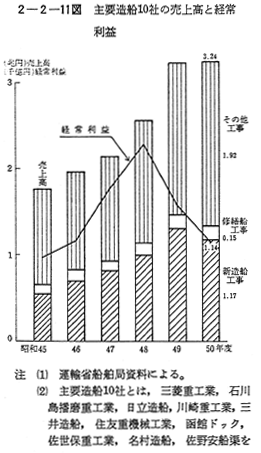
また,主要造船10社の経常利益は,売上高の増加にもかかわらず,48年度をピークとして激減しており,長納期工事を抱える造船企業が,石油危機後の諸物価高騰の影響を大きく受けていることがうかがえる。
51年度以降については,今後の工事量を表わす新造船起工量が50年度には対前年度比40%減と大幅に減少しており,このことからみて,今後の売り上げ及び経常利益は減少することと思われ,経営は悪化していくものと思われる。
一方,船舶にとう載する機器を製造する造船関連工業は,50年度においてはまだ造船の工事量が概ね確保されたために,全体としてはほぼ前年度なみの操業を維持することができたが,50年度後半に入ると,造船不況の影響を受けて,大型タンカーにとう載される蒸気タービン,ボイラ,ポンプ,バルブ等を生産している一部関連工業の工事量が減少しはじめている。
船舶は,従来から鉄鋼,自動車と並んで我が国の三大輸出商品の一つとして外貨獲得に貢献してきており,50年には約60億ドルの輸出実績をあげている。
また,造船業は日本の基幹的な重工業の一つであり,造船所が存在している地域社会においては,造船業を中心として造船下請業,造船関連工業等が発達し,雇用,生産等の面において地域経済に占める比重は非常に大きなものがあるところから,今回の造船不況に基づく造船業,造船下請業,造船関連工業の経営悪化は,地域社会を中心に雇用調整問題など,深刻な問題をひき起こしている。
(3) 不況への対処
上述のような造船不況に対処するため,政府は当面の対策として輸銀資金の拡充,各種融資の斡旋,雇用対策等各種の対策を講じてきている。
一方,今後の方向づけの一環として,運輸大臣の諮問機関である海運造船合理化審議会は,諮問第62号「今後の建造需要の見通しと造船施設のあり方について」のうち,長期計画について,51年6月に答申を行ったが,これによれば,①55年における世界の船舶建造需要は石油ショック以前に比して大幅に減少し,特に大型タンカーの需要は皆無に近いと考えられる。このような情勢の中にあって,我が国造船業の55年における建造需要量は約650万総トン程度と見込まれる。②上記建造需要量に見合う操業度(工数ベース)は49年比65%程度と見込まれるのでこれを目途として将来の需要の質的動向を勘案しつつ造船能力の所要の調整を因る必要がある。③この調整を行うにあたっては,これによって発生する雇用、地域経済等に与える影響に十分配慮するとともに,需要の創出及び施設の有効利用の見地からの技術開発の推進,他部門への転換,適正な船価の維持等に努め,特に企業体力の弱い中小造船業等については,新市場の開拓,技術力のかん養,事業転換等について十分配慮する必要があるとされている。
一方,我が国の輸出船受注をめぐる国際情勢は,世界的な造船不況の中で,一段と厳しさを増している。
こうした情勢の中で,我が国造船業が国際的摩擦を回避しつつ,造船不況の深刻化に対処するためには,今後共上記答申の趣旨を尊重しつつ,操業度の調整,技術開発,新市場開拓,事業転換,雇用対策等,各種の施策を講じていく必要があろう。
また,我が国造船業が,引き続き我が国の経済発展に重要な役割を果すとともに世界の主要造船国としての地位を保持していくためには,最近における海運造船をめぐる内外情勢の変化に対応して,船舶の性能の改善及び船舶の建造に関する技術の高度化等を図り,より技術集約的な造船業へ移行する必要がある。
|