|
2 部門別動向
50年度における運輸事業の業種別損益状況は 〔2−4−6表〕のとおりで,まず国鉄は,貨物輸送量の5年連続の減少と不況の影響による旅客輸送量の減少に加え,運賃改定の遅れ,度重なる争議行為等による輸送障害,合理化の遅れなどから9,100億円にのぼる巨額の欠損を計上した。民鉄は輸送量が伸び悩んだにもかかわらず運賃改定の寄与もあって,大手民鉄では14社中10社が営業利益を計上したのをはじめ経常損益でも3社が黒字をだすなど,一部の企業を除き業績は改善をみせた。また中小民鉄は58社中48社が,公営鉄道は11社全社が経常損益で赤字を生じたが,いずれもその赤字幅を縮小するなど民鉄は総じて前年度より経営を改善した。しかし51年度に入ってからは,輸送力増強・安全確保工事費の増加が見込まれるほか,6月から8月にかけ平均23.1%の電力料金の値上げがあるなど,経営の圧迫要因が生じているため,現在行っている保守作業の機械化,出改札の自動化,変電所の無人化等の省力化をはじめとする経営合理化を一層進めていく必要がある。
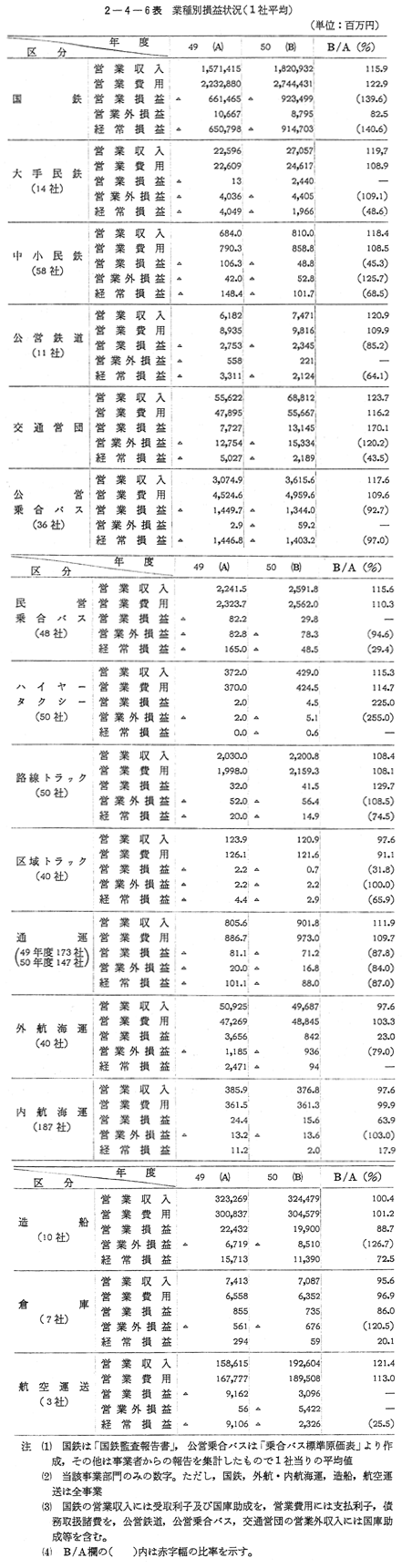
自動車運送部門にあっては,乗合バス,タクシー等の旅客輸送量が減少傾向にあり,また貨物輸送量も減少が続いたにもかかわらず,運賃料金の改定が実施された結果,乗合バス,路線トラック,区域トラック及び通運で赤字幅を縮小した。しかし,前年度まで僅かに黒字を計上していたハイ・タクは赤字に転化し,自動車運送部門の全業種が赤字を計上するに至った。したがってバスのワンマン化,トラック事業の荷役の機械化,構造改善による事業の集約化等の合理化を今後とも引続き行っていく必要がある。
次に財務状況をみると 〔2−4−7表〕のとおりである。まず自己資本比率は,一部の業種を除き各業種とも20%未満で他人資本に大きく依存した資本構成となっている。また運輸業はサービス業としての性格上流動資産の発生する余地が少なく,主として固定資産により事業活動が行われているため,固定比率は他産業に比べて総じて高い。このような財務構成であることから,鉄道事業のように特に巨額の固定設備を要する部門にあっては金融費用の経常費用に対する割合が他産業と比較して著しく高くなるなど一般に資本に対する利子負担が大きくなっている。しかし,自己資本に長期借入金などの固定負債を加えた長期資本に対する固定資産の割合である固定長期適合率をみると,公営業種と航空運送を除き概ね100%程度またはそれを下回る水準どなっており財務は長期的には比較的安定している。なお公営の鉄道や乗合バスのそれは民営よりも高い値となっている。流動比率についてみると,極端に低い公営業種を除くほかは,倉庫,民営乗合バス,大手民鉄等の業種が他産業を上回っているとともにその他の業種も概ね100%程度の水準となっていて,財務は短期的にも比較的安定している。
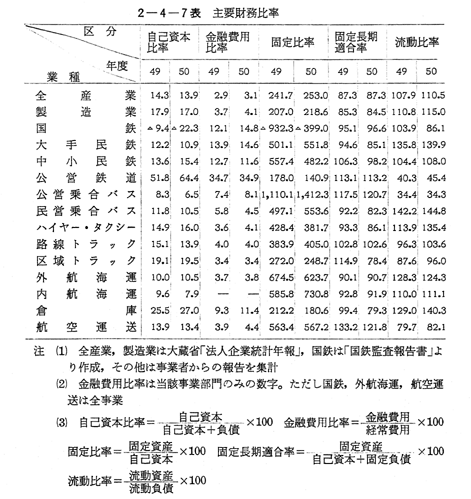
生産性を付加価値指標でみると 〔2−4−8表〕のとおり,従業員一人当たりでは,巨額の固定設備を有し労働装備率の大きい鉄道部門,外航海運,航空運送が他産業より比較的大きい付加価値額であるのに対し,労働集約性が強く労働装備率の小さい自動車運送部門は他産業並かそれより小さい付加価値額となっている。なお,国鉄の場合は低い運賃水準により大幅な赤字を余儀なくされたことが大きく影響して付加価値額が小さくなっている。また,付加価値額に占める人件費の割合である労働分配率では,外航海運,航空運送等が全産業を下回っている以外は運輸事業の労働集約性を反映して各業種とも全産業を上回った値となっている。なかでも国鉄と公営乗合バスは100%を超えており,付加価値額で人件費さえも賄えない状態に陥っている。
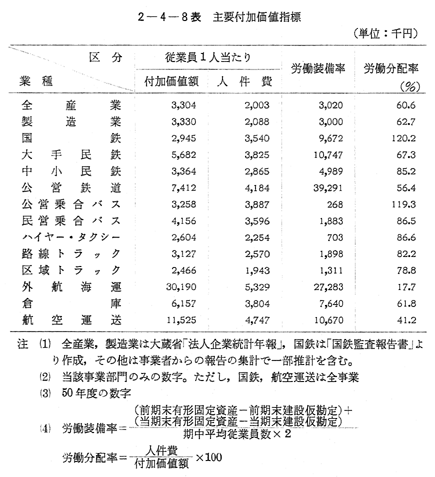
最後に賃金水準を月平均現金給与総額でみると 〔2−4−9表〕のとおりで,運輸業の賃金水準は他産業に比べて高く,50年については全産業の1.14倍となっているこれは 〔2−4−10表〕のとおり,他産業に比して雇用者の平均年齢が高いこと,専門的技能を要すること,労働環境が厳しいこと等運輸業の特殊性によるものである。
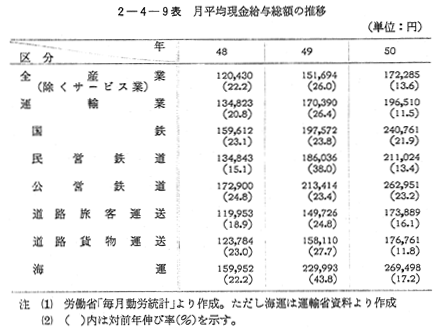
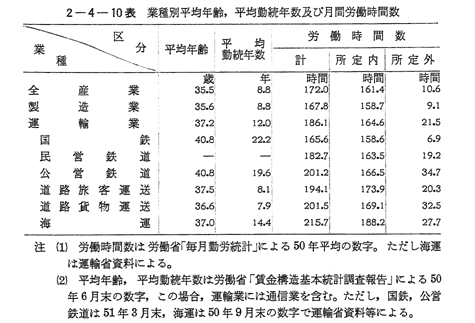
|