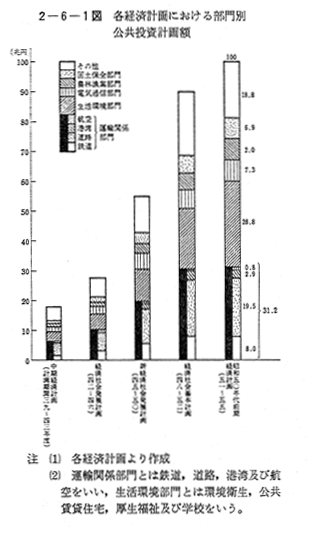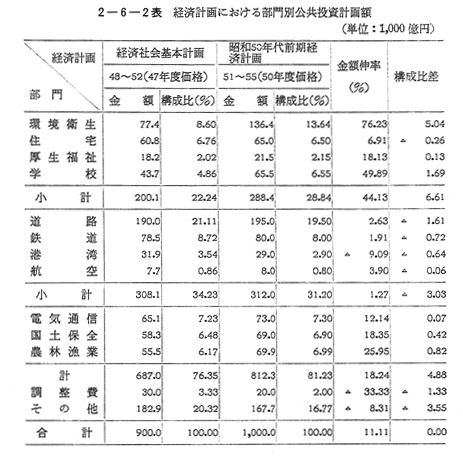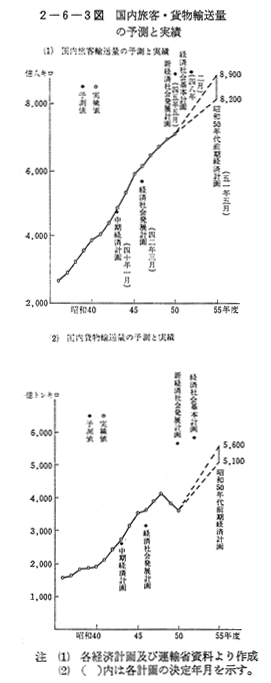|
1 施設整備の方向
戦後四半世紀にわたる世界にも例をみない高度経済成長の過程においては,飛躍的に増大する輸送需要に対する社会資本投資の立遅れの解消,全国土の均衡ある発展の促進等を目標として,運輸関係施設の整備に多額の資金が投入されてきた。
しかしながら,我が国経済はこれまでの高度成長路線から安定成長路線へと移行しつつあり,運輸関係施設整備もこの転換期に当り,新たな対応を迫られているといえよう。
(1) 昭和50年代前期経済計画
昭和51年5月に決定された昭和50年代前期経済計画(以下「新計画」という。)は,安定成長路線への円滑な移行を目指したものであるが,これを施設整備の面からこれまでの諸経済計画と対比しつつみてみると,第一に,高度成長期の経済計画が経済の量的拡大を指向した成長中心のものであったのに対し,新計画は,世界経済の構造変化と資源有限性の強まり,安定した生活の確保と住みよい環境の形成を求める等生活の質的向上を重視する国民意識の変化を踏まえ,我が国経済の安定的発展と充実した国民生活の実現を指向しており,計画の目標に基調の変化がみられる。
第二に,40年代の経済計画をみると,いずれも8〜10%程度の高い実質経済成長率を想定しており,実績でも40年代前半までは,民間設備投資と輸出の拡大を軸として平均10%強の高度成長を続けてきたが,新計画では今後は,経済及び社会の内外環境条件が変化し,技術進歩の緩慢化も予想されること等のため,成長率は低下するとみており,50年代には,各種需要項目がバランスを保った6%程度の成長路線へ移行するものとしている。
第三に,51〜55年度の計画期間中の公共投資総額としては,概ね100兆円と予定しているが,これは,48年2月に決定された経済社会基本計画(以下「前計画」という。)の90兆円の1.1倍にとどまり,実質値でみると約4分の3の規模に縮少している。すなわち,新計画における政府固定資本形成の対GNP弾性値は1.17で,前計画の1.72に比べかなり低くなっている。なお,このように公共投資の伸び率が低下せざるを得ないので,新計画では投資分野の選択,重点化が必要であると強調している。
第四に,新計画では生活関連社会資本の分野はもとより,他の分野においても国民生活の質的充実に深くかかわっているものに重点を置いており,運輸関係施設についても,生活道路,通勤鉄道の整備を重視している。
鉄道,道路,港湾及び航空を合計した運輸関係部門の投資配分は,31兆2,000億円と前計画の30兆8,100億円に比べ1.3%の増加にすぎず,鉄道,道路,航空の投資額はいずれもわずかながら増加したものの,港湾は約1割の減少となっている。また,公共投資合計に対する構成比では,鉄道8.0%,道路19.5%,港湾2.9%,航空0.8%で,前計画に比べ,道路が1.61ポイントの減となるほか,鉄道が0.72ポイントの減,港湾が0.64ポイントの減,航空が0.06ポイントの減となる 〔2−6−1図〕 〔2−6−2表〕。
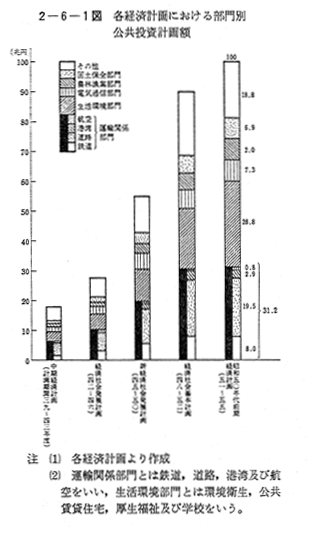
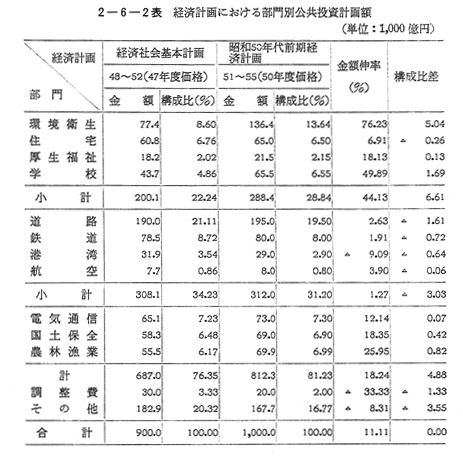
新計画は,このような基本的な枠組の中で55年度の輸送需要を,49年度実績に比べ,旅客3割,貨物4割程度の増加と見込み,次のように運輸関係施設の整備を進めることとしている。
第一に,環境対策として,航空機,新幹線,高速道路等の騒音対策及び港湾の水質汚濁防止等に必要な施設の整備を推進するほか,道路,港湾の緑化対策及び生活道路の整備を行う。
第二に,安全対策として,踏切りの立体交差,航路,航空標識,航空保安施設等の整備を行う。
第三に,都市の交通混雑の緩和を図るため旅客輸送においては,既存鉄道及び地下鉄網を充実し,輸送効率の高い大量公共交通機関及び連絡施設の整備を行う。
第四に,地方部では,道路整備を行うとともに,バス路線の確保や運行改善及びタクシーの活用を図るほか,辺地,離島における空港及び港湾の整備を行う。
第五に,幹線交通網の整備については,緊急度の高い路線に投資の重点を置くこととし,長期にわたって計画的に着実な整備を行う。(ちなみに,この幹線交通網の整備については,前計画では,国土空間の再編成を図る上で先導的役割を果すものとして,最重点事項とされていたのに比べ,相当の基調の変化がみられる。)
幹線交通網の整備のうち主要なものとしては,
ア 新幹線については,計画期間中に東北,上越両線の開業(注,前計画では60年度までに約7,000キロメートルを目途に,東北,成田,上越の3新幹線を開業し,既設線を含めて52年度末までに,約1,900キロメートルを供用することを予定)
イ 高速自動車国道については,55年度末に概ね3,200キロメートルの供用(注,同じく60年度までに約1万キロメートルを整備することを目途に,52年度末までに3,100キロメートルを供用することを予定)
ウ 港湾については,流通拠点港湾及び外貿港湾の重点整備
エ 空港については,国際空港の整備とジェット機の就航に対応した国内空港の整備をあげている。
第六に,物的流通の効率化を図るため,次の施設の整備を行うこととしている。
ア 幹線物流については,その基盤整備を図るため,物流拠点を含め幹線交通ネットワークを着実に整備することとし,特に海路利用を促進するため所要の流通港湾の整備等を行う。
イ 都市内物流については,交通混雑の緩和にも資する輸送の共同化を推進するほか,流通施設の計画的配置や道路網の体系的整備を行う。
(2) 施設整備の問題点と今後の方向
このような運輸関係施設整備を進めるに当っての問題点と今後の方向を考察することとする。
まず,これまでの高度成長の過程で,運輸関係社会資本の整備水準はかなり引上げられ,新幹線鉄道,高速道路,ジェット航空輸送をはじめとする優れた輸送サービスも提供されるようになったが,今後は,このようなサービス水準を確保し,厖大な運輸関係施設を維持していくだけでも相当な費用を要する。
また,新計画は,前述したように旅客3割,貨物4割程度の増加を見込んでいるが,これは増加率としてはかなりの低下を示すものであるが,ベースとしての経済規模が大であるため,増加量としては40年代前期と大差ない規模である 〔2−6−3図〕。このような輸送の需要増に対応し,隘路となる部分の施設を強化し,あるいは新規の運輸関係施設を整備していくためには巨額の資金を必要とする。
次に,所得水準の向上に伴い国民意識が多様化し,旅客輸送において高速性,快適性等質的向上に対する国民の欲求が強まるとともに,産業構造の高度化によって,貨物輸送においても確実性,機動性等物流の効率化の要請が高まってきており,これらに対応して輸送サービスの質的充実を図っていく必要がある。
さらに,今後運輸関係施設を維持し,また整備していくに当っては,公害の防除,環境の保全のための対策を実施し,ないしは,施設を整備する等の配慮をすることの必要性がますます高まってきている。また運輸事業にとって,安全を確保するために施設ないし体制を充実し,強化する必要があることはいうまでもないところである。
このような課題と諸要請に対応し運輸関係施設の整備を行っていく必要があるが,今後とも費用負担の適正化を図るとしても,現実には国及び地方公共団体の財政は悪化しており,また企業採算性の悪化今回のインフレによる企業体力の脆弱化によって運輸事業の設備投資余力も著しく低下してきており,加えて,空間,環境,資源等の制約も強まってきているため,全ての分野において急速かつ大幅に運輸関係施設整備を進めていくことは困難となってきている。
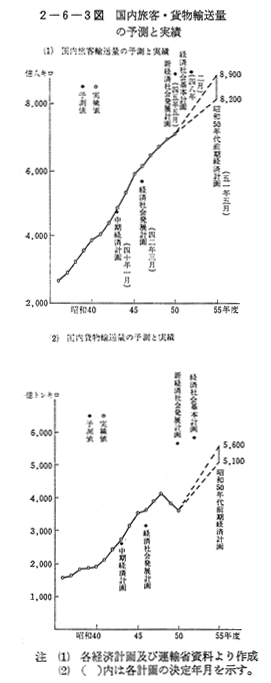
このため,今後は特に新計画のいうように投資分野の選択,重点化が不可欠となってきており,公共投資,その他の財政措置もこの方向にそって推進されるべきものと考えられる。
なお,新計蓮ではこのようなことを考慮し,前述したように運輸関係施設の重点整備を基本方針としているが,交通密度が高く,かつ,代替可能な分野において,大量公共交通機関を充分に活用した交通体系が望ましいと述べている。
ともかく,これまでのように輸送手段を豊富に整備することはもはや困難となってきており,新しい考え方で交通体系を見直す時期にきているといえよう。
すなわち,50年代前期といった中期的な交通政策の基本的方向としては,既存交通施設の活用を中心として,その輸送効率を高めることにより,需要増に対処するという原則にのっとった効率的交通体系の形成を目標にすべきものと考えられる。
また,このような効率的交通体系の形成には,利用者による交通手段の自由な選択を基礎として各交通機関がその特性からみて適合する需要分野を分担すること及びそれぞれの運営の合理化,効率化を徹底するとともに,相互の有機的な連携を確保することも必要であろう。
次に,今後の施設整備を進めていく上で,特に留意しなければならない問題として,地域社会との調和・調整の問題があげられる。
鉄道,空港,港湾等の整備,運用に関して,関係地元住民との間で,環境,公害問題をはじめとして,各種の問題が生じており,各所で施設整備事業の着手の遅延や運行の制約が生じている。特に,新幹線,国際空港等広域的利用に供され,国民生活の発展に寄与するものであっても,沿線や周辺地域の交通に直接の利便を生じない場合に,その傾向が顕著である。
したがって,運輸関係施設整備に当っては,今後とも環境保全,公害防止等に十分配慮していくことはもちろんであるが,その一環として,環境に与える影響の大きい事業にあっては,その計画の立案等の段階で環境影響評価を行う必要があり,第7章で詳述するとおり,このための評価の手法の充実等の検討を推進すべきである。
また,施設整備に当っては地域の土地利用計画との調和に十分配慮するとともに関係地方公共団体の意向を適確に把握し,当該運輸関係施設が国民の経済社会活動に果している公共的役割及び広い目でみた地域社会に与える便益等につき地域社会の十分な理解を求め,施設整備への協力を得るよう努力を積み重ねることが肝要であろう。
|