|
(2) 四半期ごとにみた旅客輸送の動向
一般に旅客輸送は個人消費との関連が深いが,50年度には,実質個人消費支出は実質国民総支出の伸びを上回って増加し,それなりに景気回復の下支えとなっていた。しかし51年度には,消費支出の6割を占める勤労者世帯で実収入が前年度比1桁の伸び(9.5%増)にとどまったことなどを反映して,前年度比3.7%増と実質国民総支出の伸び(58%増)を下回る緩やかな上昇にとどまった。
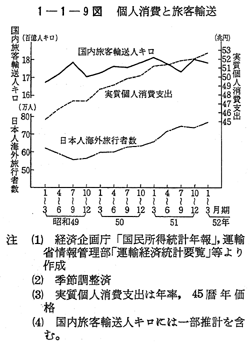
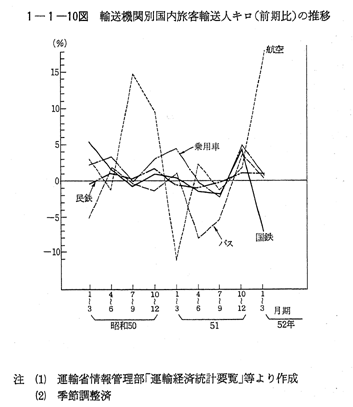
|
|
(2) 四半期ごとにみた旅客輸送の動向
一般に旅客輸送は個人消費との関連が深いが,50年度には,実質個人消費支出は実質国民総支出の伸びを上回って増加し,それなりに景気回復の下支えとなっていた。しかし51年度には,消費支出の6割を占める勤労者世帯で実収入が前年度比1桁の伸び(9.5%増)にとどまったことなどを反映して,前年度比3.7%増と実質国民総支出の伸び(58%増)を下回る緩やかな上昇にとどまった。
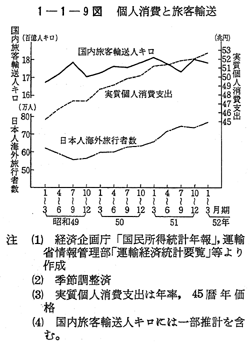
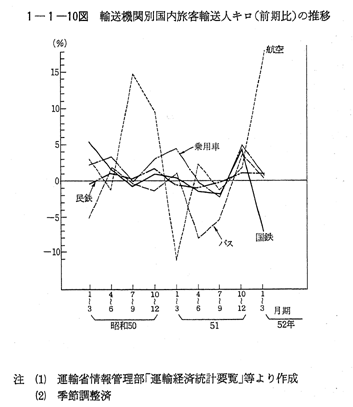
|