|
2 進展する輸送構造の変化
国内貨物輸送量の推移をみると, 〔2−1−8表〕のとおり,40年度から48年度までの8年間に,トンキロで2.19倍となり,この間の年平均伸び率は10.3%と高い伸びを示している。
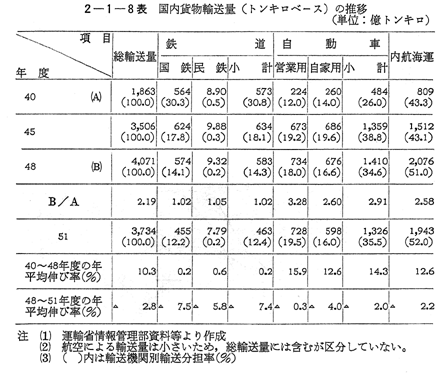
また,これを輸送機関別にみると,この間,自動車が2.91倍,内航海運は2.58倍と高い伸びを示した。一方,鉄道は1.02倍とほとんど横ばいに推移している。
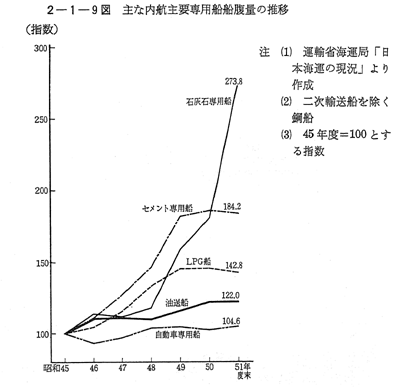
一方,鉄道貨物輸送の衰退の原因についてみると,石炭から石油へのエネルギーの転換,資源の海外依存度の増大等により,大宗貨物であった石炭等の鉱産品木材等の一次産品の減少,大都市周辺部の臨海コンビナートの建設を中心とする産業立地の変化による輸送距離の短距離化,我が国の産業構造の変化による二次産品の輸送需要の増大等,そもそも鉄道にとってその特性を発揮しにくい方向に経済構造が変化したことが大きく影響している。また,国鉄貨物輸送については,相次ぐ争議行為が輸送の安定かつ効率的な提供を妨げ,荷主の信頼を低下さ世,これに拍車をかけたこと等が指摘される。
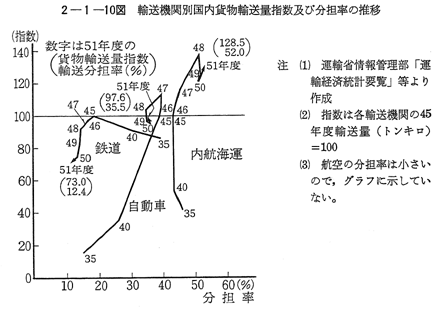
まず,自動車は,30年代後半から40年代前半までの高度成長期を通じて,前述のような要因により,輸送量及びシェアを拡大したが,45年度以降輸送量の伸びは鈍化し,47年度をピークに以後,概ね減少傾向にあり,また,分担率も同様の動きを示している。これは,48,49年度以降の公共投資及び民間設備投資を中心とする投資活動の伸び悩みに伴い,自動車輸送のかなりの部分を占める骨材等建設資材関係の輸送量が減少したこと,耐久消費財等自動車のシエアの高いいわゆる雑貨輸送需要が伸び悩んだこと等に起因していると考えられる。なお,自動車の輸送トンキロを営業用及び自家用の別でみると,40年度には国内貨物輸送量に占める割合がそれぞれ12.0%対14.0%で自家用が上回っていたが,45年度を過ぎると営自ほぼ同量を輸送するようになり,最近の動向をみると,自家用トラックの輸送量がピーク時の47年度と比較し,2割以上減少し,なお下げ止っていないのに対し,51年度の営業用トラックの輸送量は同じくピーク時の47年度に比し5%減にとどまっており,同じ自動車輸送にあっても,自家用トラックの不振が目立っている。
地域間及び地域内輸送量をみると, 〔2−1−11表〕, 〔2−1−12表〕のとおりで,東海道3地域(関東7都県,東海4県,近畿6府県)に係る輸送量の全地域間輸送量に占める割合は50年度で77.3%と大きく,また,全地域内輸送量に占める割合も47.4%と50%近いものとなっている。しかしながら,産業の地方分散化も進んでおり,東海道3地域以外の地域間及び地域内輸送量は,40年度から50年度までの10年間にそれぞれ2.43倍,2.15倍と伸び,全体に占める割合もそれぞれ18.6%から22.7%,46.6%から52.6%と増加しており,そのウエイトを高めている。
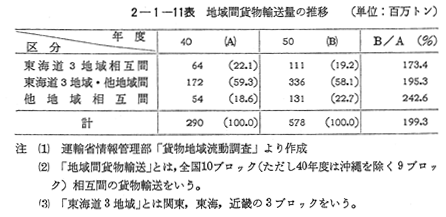
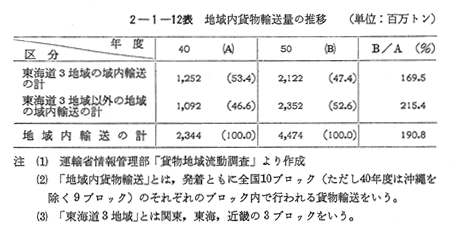
また,これらを輸送機関別にみると, 〔2−1−13図〕, 〔2−1−14図〕のとおりである。
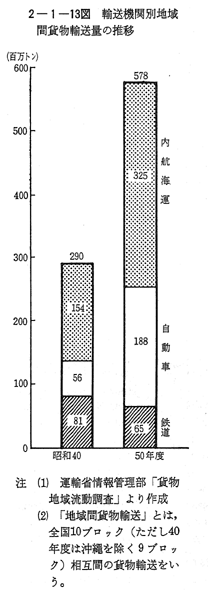
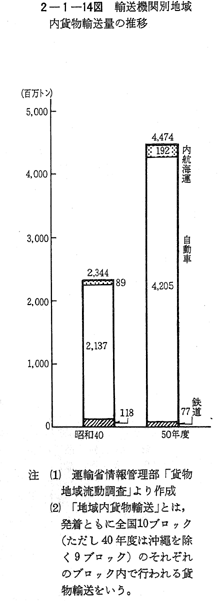
主要品目別に貨物輸送量の推移をみたものが 〔2−1−15表〕である。
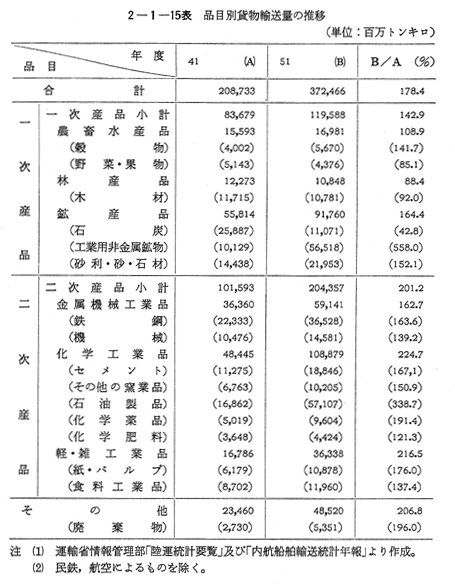
産業構造の高度化により二次産品が似年度から51年度にかけて,トンキロで約2倍に伸びている。このうち,特に,石油製品の伸び(3.39倍)を中心とした化学工業品(2.25倍)や軽・雑工業品(2.17倍)の伸びが目立ち,鉄鋼,機械を中心とする金属機械工業品は1.63倍となっている。一次産品は鉱産品が1.64倍に増加したものの,農畜水産品が横ばい,林産品が減少した(0.88倍)ため,1.43倍の伸びにとどまっている。また,エネルギーの転換が進み,鉱産品のうち石炭が0.43倍と大幅な減少を示し,石油製品の大幅な伸びと対照的である。
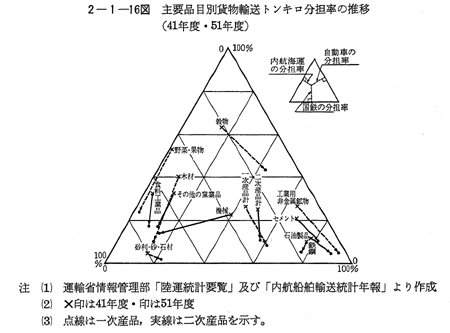
輸送機関別距離帯別輸送トン数の分担率の推移を示したものが 〔2−1−17図〕である。
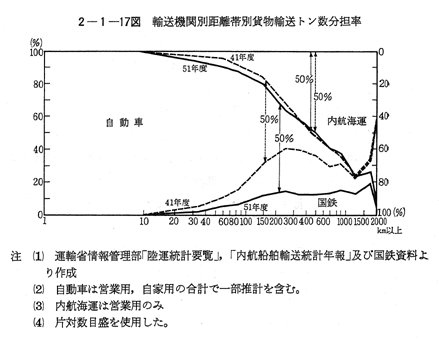
国鉄は全距離帯にわたってそのシェアを縮小し,自動車は近距離において圧倒的シェアを占めているのみならず全距離帯においてそのシェアを拡張し,特に,中長距離への進出が著しく,41年度と51年度を比較すると全輸送機関中で自動車の分担率が50%を占める分岐点は,160キロメートルから220キロメートルヘと移動している。内航海運は中短距離で若干シェアを拡張しており,特に長距離ではその強みをみせている。
|