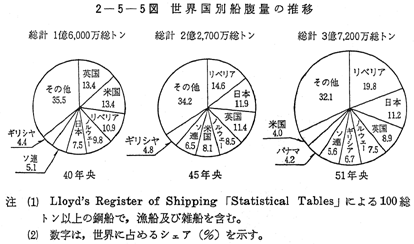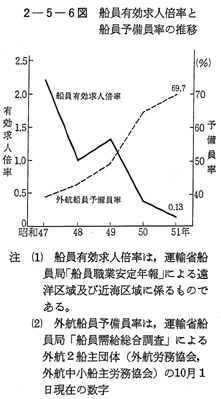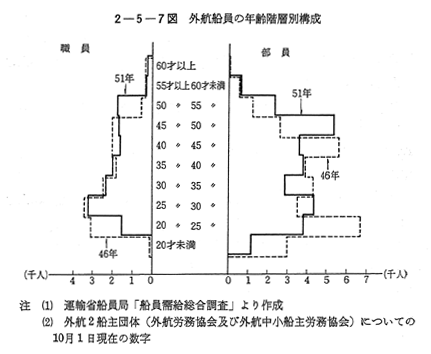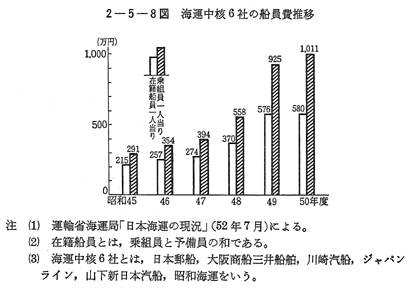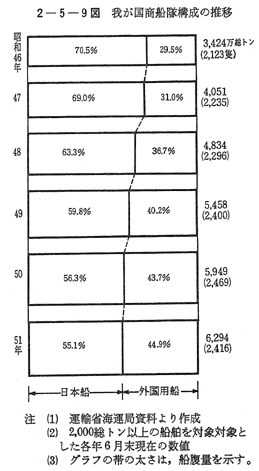|
2 転換期にある我が国海運と船員の雇用問題
(1) 外航海運の動向
我が国商船隊の51年の輸送量(トンベース)は,51年度の貿易額が過去最高を記録したこともあって,輸出で対前年比17.9%増輸入で同7.4%増とともに増加しており,部門別では輸出の好調を反映してコンテナ船の輸送量が大幅に増加しているのが特徴的である。
一方,51年度の世界海運市況は,タンカーにあっては構造的な船腹過剰が続いているため,前年度よりやや上向いたとはいえ,ワールドスケール(1万9,500重量トン型のタンカーに関する基準運賃率を100とした場合の,各船型についての実際の成約運賃率の指数)30前後(15万重量トン以上の場合)と採算点を大幅に下回る水準に低迷した。また,不定期船にあっては,不定期船運賃指数(40年7月から41年6月までの平均運賃率を100とした場合の,実際の成約運賃率の指数〉は,50年度末に最低を記録したのち時持ち直しをみせたが,55年に入ってから5月に128.9と再び50年の平均水準(142.1)以下に落ち込んでいる。
このようにダンカー及び不定期船市況は総じて低迷裏に推移'したものの,輸出の好調を反映してコンテナ船や不定期船部門のうちの自動車専用船などが活況を呈したため,我が国外航海運企業の経営状況は,大幅な減益決算を余儀なくされた50年度と比較して,過半の企業が業績の回復を示した。具体的には,助成対象外航海運企業40社合計の経常損益は50年度37億円の赤字計上から,51年度160億円の黒字へと好転している。しかしこの決算においては,部門別の好不況がはっきり現われるに至ったため,船腹構成の差などにより,業績の回復には企業間でかなり明確な格差がみられたのが特徴的となっている。
次に,我が国商船隊の規模についてみると,まず我が国の51年央における2,000総トン以上の外航船船腹量は3,465万総トンとなっており,その中でタンカーが増加傾向を続けている反面,貨物船については近年横ばいの傾向にある。ちなみにロイド統計による100総トン以上の鋼船を対象とした日本船船腹量の世界に占めるシェアの推移は 〔2-5-5図〕のとおりであり,便宜置籍国であるリベリアの船腹量増加が著しい中で,我が国の船腹量も増加はしているが,その世界に占めるシェアは45年央の11.9%から51年央の11.2%へと若干低下している。
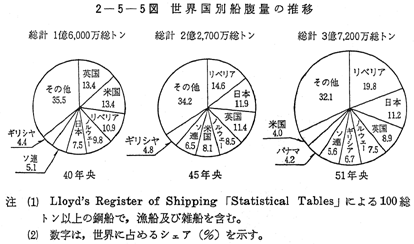
一方,我が国の海運会社が外国から借り入れて運航する外国用船は,51年央において2,829万総トンに達し,我が国商船隊の中で大きなウェイトを占めるに至っている。
(2) 船員雇用の状況
我が国海運の発展には,優秀な資質を備えた日本人船員の寄与してきているところが大であるが,その船員の雇用問題も最近とみに厳しさを増している。
近年の雇用状況は, 〔2-5-6図〕のとおり,有効求人倍率(遠洋区域及び近海区域に係るもり)は,50年に1.0を大きく割り,51年も落ち込みを続けて0.13となるに至った。
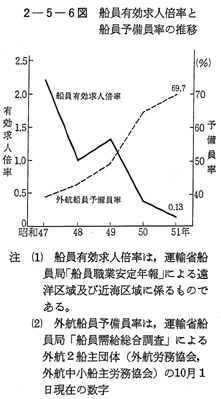
一方,有給休暇,出勤待機等を行っている予備船員の状況を示す予備員率も増加傾向にあり,51年10月1日現在,外航2船主団体における予備員率は69.7%の高率に達している。
このような船員労働力の需給バランスの逆転は,海運企業が不経済船の海外売船を大量に行ってきていること,人件費が高騰している日本人船員を避け,低廉な発展途上国船員を乗り組ませた外国船を用船する傾向が強まったこと等により,雇用需要が大幅に減少したことが主な要因と考えられる。
一方,こうした船員需給の不均衡と並行して,外航船員の年齢構成にも変化がみられ, 〔2-5-7図〕のとおり,46年と51年の比較においては,職員,部員のいずれも,45才以上の中高年齢者の占める比重が高くなってきている。この高齢化の傾向はますます強まっていくことが予想され,第3章第2節で述べたように企業内における処遇,人件費負担増等の高齢化に伴う問題への今後の対応が難しくなるものと思われる。
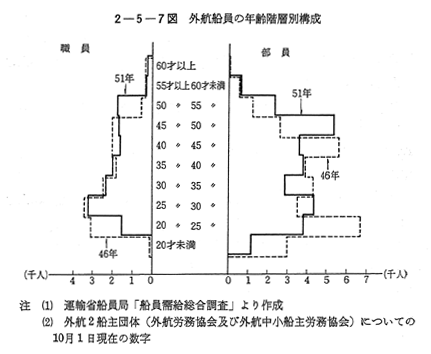
(3) 日木船の国際競争力低下と我が国商船隊の構造変化
近年船員費を中心とする諸経費が大幅な上昇を示し,特に船員費の上昇は,コストに占める船員費の割合が大きい近海船など中小型船の分野を中心として,日本船の国際競争力を著しく低下させるに至った。
例えば 〔2-5-8図〕は海運中核6社の船員費推移を示したものであるが,乗組員と予備員の和である在籍船員1人当たりの船員費及び乗組員1人当たりの船員費はともに上昇しており,しかも両者の差は最近になって特に大きくなっている。このことは,単に賃金水準のアップのみならず,週休2日制度の実施,不経済船の海外売船寺による予備員率の上昇が大きく作用していると思われる。
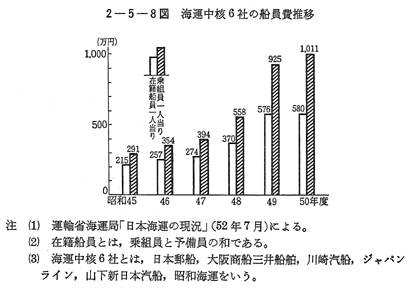
このため,日本船と発展途上国船員を配乗した外国船との間には,コストにおいて大きな競争力の差が生じ,特に近海船では,日本船のコストを100とした場合のこのような外国船のコストは約60という試算もなされている。
このような日本船の国際競争力の低下を反映して,我が国商船隊は大きな構造変化をみせている。
すなわち 〔2-5-9図〕は,我が国商船隊の構成推移を示したものであるが,46年の日本船及び外国用船の割合がそれぞれ70.5%及び29.5%であったのが,51年には同じく55.1%及び44.9%と外国用船船腹量の伸びは著しいものがある。これに加え量的に増大した外国用船についても質的な変化がみられる。すなわち,外国用船の中でも,近年,仕組船(日本の海運会社が長期間用船する目的で日本の造船所の船台を外国の船主にあっ旋し,建造させた船),チャーターバック船(諸経費の上昇により採算の悪化した日本船を海外に売船し発展途上国の船員を配乗することにより,コストの低減を図ったのちに,日本の海運会社が再び用船するもの)と呼ばれるものの増加が著しく,例えば海運中核6社についてみると身この両者は51年央で外国用船の3分の1弱を占めるに至っている。
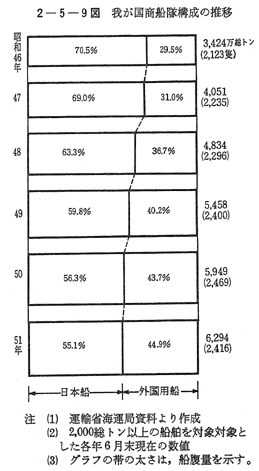
(4) 今後の課題
当面,タンカー船腹の過剰問題については,国際的なタンカー船腹量削減のための合意の促進を図り,また,近海船を主とした国際競争力の低下に対しては,建造調整,事業転換を推進する等の措置を講じている。一方,船賃雇用安定対策としては,近海部門からの離職者に対する個別延長給付制度,中高年齢船員に対する個別延長給付制度及び職業補導延長給付等の失業保険制度の活用が行われている。
こうした対策はもちろんのこと,我が国海運の抱えている問題に対しては,造船業をはじめ我が国経済への波及効果を考えれば,より総合的な対処が必要となっている。
大きな転換期にある我が国海運の今後のあり方と,これに対してなすべき方策を求めるには,①我が国海運が基幹的な産業の1つとして日本経済にいかなる意義を持っているか,②我が国の輸出入物資の安定的かつ低廉な輸送に海運がどのような意義を果たすのか,③我が国の労働人口の中で船員の雇用の果たす意義は何か,④我が国の経済的安全確保,いわゆるセキュリティの面で海運はいかなる意義を担っているか,⑤国際収支改善の上で海運はどのような意義があるか,⑥海上の安全や環境保全に海運がどのような意義を持っているかなどを検討し,しかる後にその意義を果たすのに必要な我が国海運のあり方を究明し,今後の進路を定めるべきであろう。
この際重要なことは,まず,日本人船員による日本船を我が国海運の基本とし,いかにしたら日本人の乗り組む日本船の確保が可能かを検討することであり,それに加えて,日本船の国際競争力の低下という現実を常に厳しく認識する必要があるということである。
我が国外航海運政策に関しては,51年11月に運輸大臣が海運造船合理化審議会に対し,「今後長期にわたる我が国外航海運政策はいかにあるべきか」とする諮問(諮問第69号)を行った。本件は,同審議会海運対策部会において鋭意検討が進められているところであり,これの成果を十分勘案しつつ今後の海運政策を確立することが必要であろう。
また,このような重大な転機にあたり,運輸省としては,52年2月に船員中央労働委員会に対し,今後における船員雇用対策の基本となるべき方針について諮問し,長期的展望に立った船員需給見通しを明らかにしつつ,今後の船員雇用の安定のための基本的方向を定めるとともに,船舶の技術革新に対応して船員制度を近代化し,日本船の国際競争力の確保と,これを通じて雇用の安定を図ることとしている。
|