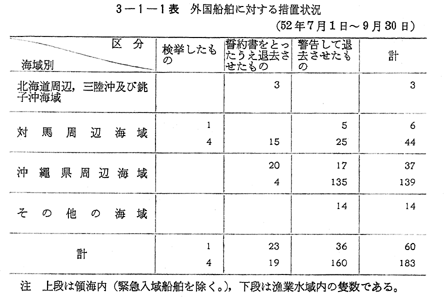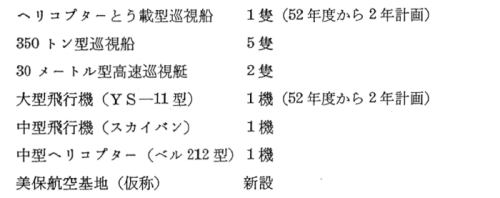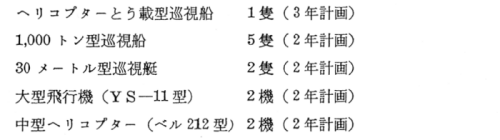|
2 新海洋秩序の下における海上保安業務
(1) 海上保安業務に及ぼす影響
領海法及び漁業水域に関する暫定措置法茄52年7月1日から施行されたことにより,海上保安庁は12海里に拡張された我が国の領海内において,不審な行動をとった外国船舶及び不法操業その他不法行為を行った外国船舶に対する監視・取締業務を行うとともに,広大な200海里漁業水域において外国漁船の不法操業に対する監視・取締業務を行うこととなり,また,ソ連等による漁業水域の設定に伴い,我が国漁船の保護の必要性が高まる等その処理すべき業務は飛躍的に増大することとなった。こうした業務に効果的に対処するため海上保安庁は,外国漁船の操業状況や我が国漁船の被だ捕等の状況を勘案して,領海については,根室海峡,オホーツク沿岸海域,北海道南岸から三陸磐城沿岸を経て銚子沿岸に至る海域及び沖縄県周辺海域を,漁業水域については,特定海域及び北方水域を,それぞれ重点海域とし,さらには,不法操業船等に関する情報の提供を防衛庁等の政府関係機関及び船主協会,全漁連,航空団体等の民間団体に依頼し,その協力を得つつ,現有の巡視船艇・航空機の効果的運用により総力をあげて監視・取締に当たっている。
すなわち,海上保安庁は,海洋2法が施行される直前の10日間,巡視船艇・航空機を多数出動させ,外国漁船による操業の実態を調査し,延べ405隻のソ連,韓国及び台湾漁船に対して領海の拡張及び漁業水域の設定についての事前周知を行い,7月1日午前零時までに全操業漁船を距岸12海里外へ退去させた。
海洋2法施行後は,両法に基づき監視9取締を行ったが,漁業水域に関する暫定措置法第6条から第11条までの漁業許可等の規定が,韓国及び中国の漁船に対しては適用されず,また,ソ連漁船に対しては8月15日まで適用延期されたため,重点海域のうち領海及び特定海域を中心に巡視船艇を増強配備するとともに,航空機により警戒監視飛行を奥施した。
ソ連漁船に対し,漁業水域に関する暫定措置法が全面適用されてからは,北海道南岸沖合を中心とする漁業水域において,領海警備と併せ,大・中型巡視船を増強配備し監視・取締に当たっている。また,「日本国の地先沖合における1977年の漁業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定」(いわゆるソ日協定)に基づくソ連漁船の操業禁止区域については,巡視船による監視・取締行動を強化し,さらに,北方海域全域にわたり大型航空機により警戒監視飛行を実施している。
これらの監視・取締の結果,海洋2法施行以後9月30日までの間に視認した外国船舶は,ソ連,韓国,台湾等の船舶延べ1,568隻であり,その措置状況は 〔3−1−1表〕のとおりである。
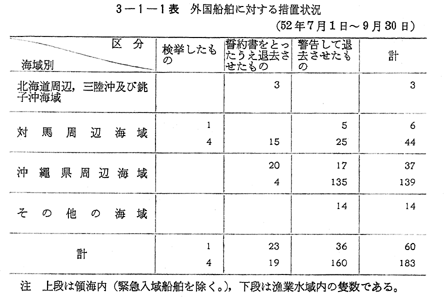
なお,漁業水域に関する暫定措置法施行後,9月下旬に操業を開始したソ連漁船に対しては鋭意立入検査を奥施しているが,10月15日現在,北海道南津沖合において,ソ連漁船3隻の船長を同法違反で検挙し,担保金を支払う旨の保証を得た後釈放した。
このほか,水路業務航路標識業務において,従来から整備を進めてきた沿岸の海の基本図や燈台,電波標識が新海注秩序の時代に正確な領海基線の確定や船舶の安全な運航に大きな役割を果たしている。
(2) 新海洋秩序に対応する海上保安体制
海上保安庁は,海洋2法の施行以来,現有の巡視船艇・航空機により総力をあげて監視・取締に当たっているが,現有勢力で長期間これを続けることは困難であるため,早急に対応体制の整備を進める必要がある。
このため,52年度当初予算において,性能,機動力を飛躍的に増強したヘリコプターとう載型巡視船や広域監視業務に有効な大型航空機及び領海警備のための機動性の高い高速巡視艇やヘリコプターなどの整備増強を図るとともに,現有の巡視船艇のうち老朽化したものの代替を進めている。その具体的内容は次のとおりである。
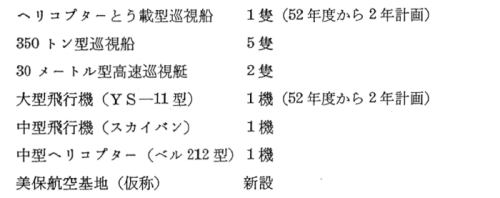
しかしながら,内外の状況により海洋2法の制定・施行が予想を越えた急速な進展をみたため,さらに,52年度補正予算において,次のとおり船艇・航空機の一層の増強が図られることとなった。
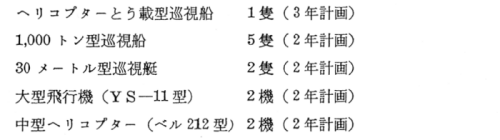
|