|
1 世界的な造船不況第1節で述べた世界的な船腹過剰や長びく海運不況の影響を受けて,世界の先進国造船業は深刻な状況に落ち入っている。 すなわち,今回の海運不況により船主の新造船発注意欲が大きくそがれた結果世界の新造船手持工事量は, 〔2−3−12図〕のとおり,受注の低迷と既契約船の工事消化等により,49年3月末をピーク(1億3,344万総トン)に急激な落ち込みをみせ,53年3月末には,3,344万総トンと,ピーク時より1億総トンも減少した。一方,ロイド統計によろ世界の新造船進水量は,50年までは手持工事消化により増加を続け,3,590万総トンが進水するに至ったが,上記のような状況を反映して,51年からは減少に転じ,52年にはさらに50年に比べ67.3%に当たる2,417万総トンまで落ち込んだ。 さて,世界の新造船手持工事量のシェアをみれば,これは, 〔2−3−12図〕に示されたように,大きく様変わりしている。手持工事量のシェアを日本,AWES諸国(西欧造船工業会加盟の12か国)及びその他諸国に分けた場合,空前の手持工事量を示した49年3月には,日本46.5%,AWES諸国42.4%,その他諸国11.1%であったものが,53年3月末になると全く逆転し,その他諸国37.5%,AWES諸国36.9%,そして日本は25.6%に後退した。その他諸国が首位を占めているのは,これら諸国の多くは閉鎖的な国内市場に支えられて景気変動が小さいのに対し,日本やAWES諸国の需要源である自由な国際市場は,長びく海運不況のため新造船発注が激減し,これら先進諸国の手持工事量が急速に減少したことによるものである。なかでも,日本の後退が大きいのは,日本に円建債務を有する日本の得意先船主が,最近の円高騰に伴い,企業体力を消耗し,新造船発注余力を失ったために新造船受注が激減したことに加え,我が国の工事消化ペースはAWES諸国よりも早く,手持工事量の減少も相対的に早いためである。
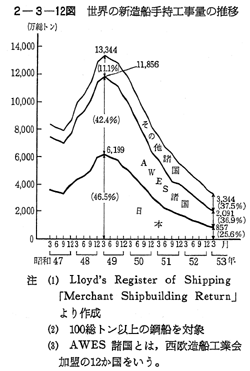
造船をめぐる国際的な動きとしては,経済協力開発機構(OECD)造船部会において活発な討議が行われてきているが,51年5月には,造船不況対策を講じる際各国が遵守すべき事項を定めた「造船政策に関する一般的指導原則」が採択された。その後は同原則の実施状況についての討議が続けられている。なお,52年11月には第40回造船部会が東京で開催された。最近の討議では,西欧諸国が自国造船業に対し行っている助成措置や第三造船諸国の台頭を考慮した上での長期的造船能力の削減などという問題等がとりあげられている。
|