|
2 我が国造船業の状況
我が国における新造船受注量は, 〔2−3−13図〕のとおり,48年度の3,379万総トンをピークに49年度以降は激減し,52年度にはわずかに495万総トンの受注しか得ちれなかった。また,新造船手持工事量も,48年度末の5,010万総トンから一気に落ち込み,52年度末には593万総トンと著しく低下している。こうしたことから,受注量に次ぐ景気の先行指標である起工量(主要35工場)ベースでみた操業度は49年度の1,782万総トンを100とした場合,52年度には,26.5(472万総トン)に落ち込んでおり,今次の造船不況の深刻さを示している。
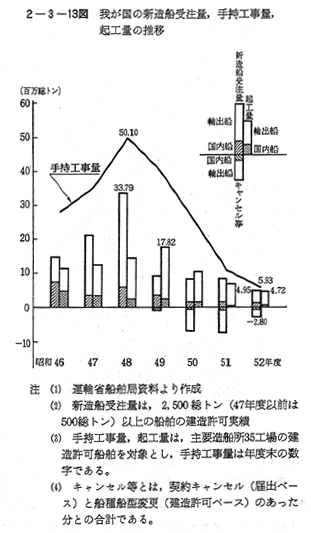
造船業の不況は受注面にそれが現われてから企業財務に及ぶまで若干タイムラグがあり,51年度の決算では受注量の減退に反し,かなりの好決算を示していたが,52年度には財務状況にもはっきり不況の影響が現われた。 〔2−3−14図〕は上場会社である主要造船10社の売上高と経常利益の推移をみたものであるが,売上高に占める新造船工事によるものの割合は49年度にほぼ4割を確保していたのに対し,52年度には約3割に落ち込み,新造船部門の不振が大きくなっており,また,52年度の経常利益は1,080億円と前難度比34.8%減となっている。中小の造船専業企業は,さらに深刻な影響を受けており,52年度には,23社が会社更生法等の適用申請をするなど,不況による経営不振が表面化している。
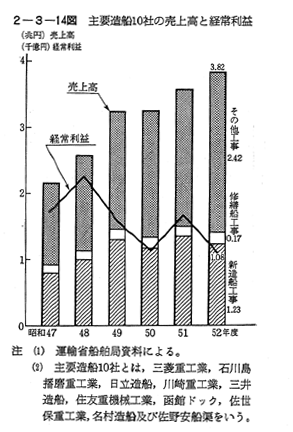
また, 〔2−3−15図〕のとおり,鋼造船工場の従業員数も最近は全般的に減少する傾向をみせている。
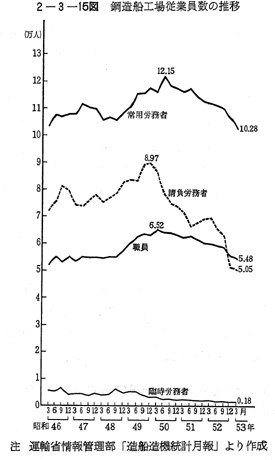
一方,先に述べた新造船需要の激減は,造船関連工業にも大きな影響を及ぼし,52年度にはタンカー関連機器,特に蒸気タービン・ボイラなどの生産の著しい減少となって現われている。その他の一般機器は,貨物船,ばら積船寺の中型船の建造隻数が確保されたため,前年に比べ横ばいか品目によっては一部増加したものもあったが,52年末には減少しはじめている。
|