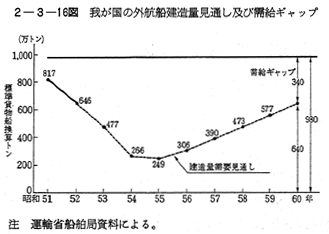|
3 我が国造船業の経営安定化方策
52年の秋以降特に急激に進行している円相場の上昇により,我が国の新造船受注量はさらに減少し,これに加えて船価の低落,既契約船のキャンセル,ドル建契約船の為替差損等が発生し,造船業の経営に新たな負担が加えられるとともに,他方,発展途上国の造船業の台頭がみられるなど我が国造船業界をとりまく環境は一段と厳しさを増している。このため,外航船の建造を主体とする5,000総トン以上の建造施設を有する造船業にあっては,大幅な需給の不均衡が長期的に継続するものと思われ,構造的不況の様相を呈している。
こうした状況の下で,53年5月10日に特定不況産業安定臨時措置法が成立し,同月15日から施行された。同法は特定不況産業について,計画的な設備の処理の促進等のため,設備廃棄等に伴って必要となる資金の調達を円滑化するための債務保証等の措置をとることにより,雇用の安定及び関連中小企業者の経営の安定に配慮しつつ,これら産業の不況の克服と経営の安定を図ることを目的としており,造船業も同法の対象業種の一つに掲げられている。
運輸省は,このような事態に鑑み,海運造船合理化審議会に対し,同法に基づく対策を適確に実施するための方策も含めて,「今後の造船業の経営安定化方策はいかにあるべきか」とする諮問を行った。これを受けた同審議会は7月14日,造船設備の処理等を骨子とする概ね次のような答申を行った。
① 今後の我が国の外航船建造量見通し及び需給ギャップ
我が国の外航船建造量(竣工ベース)は,55年まで減少を続け,以後緩やかに回復するものと思われるが, 〔2-3-16図〕のとおり,今後の経済成長率等を比較的高く予測した場合においても標準貨物船に換算して60年で640万トン程度と見込まれる。
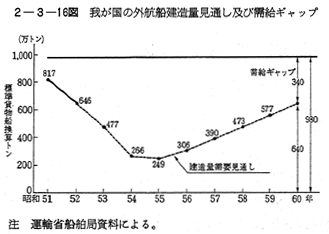
一方,現在5,000総トン以上の船舶を建造しうる船台又はドックを有する企業は61社でその年間建造能力は標準貨物船に換算して980万トン程度である。
従って,60年における需給ギャップは,標準貨物船換算トン数で340万トン程度と推定される。
② 設備の処理等
60年においてもなお過剰となる設備は早急に処理すべきであり,上記61社の現有設備能力を標準貨物船換算トン数で340万トン(現有能力の35%)程度処理することが必要である。
この際,中小の造船専業企業は総じて,金融,技術,営業等の面において弱体であり,その経営はますます苦しくなることが予想されるので,既存系列の強化,企業の集約化,経営の多角化の推進等を図る必要がある。
また,設備処理を行ってもなお当面の需給ギャップは解消されないので,過労競争回避のため操業調整を行う必要がある。
③ 設備処理等と併せて行うべき措置
設備処理等を円滑に行い造船業の経営安定化を図るために,特定不況産業安定臨時措置法に基づく特定不況産業借用基金による債務保証のみならず,適切な金融対策を早急に検討するとともに,仕事量の急激な落ち込みを緩和するため,造船部門の需要創出を図る必要がある。さらに,造船関係技術を活用できる分野を開拓し,積極的に事業転換を図っていく必要がある。
また,こうした対策を図ってもなお余剰労働力の発注が避けられない場合には,雇用保険法に基づく雇用安定資金制度等の充実,強化に努めるなど,雇用対策に十分配慮する必要がある。
このほか船主の倒産に伴う造船企業の連鎖倒産防止のための措置を講じる必要がある。
この答申を受けて,53年8月初めに総トン数5,000トン以上の船舶の建造施設を存する造船事業者の大部分のものからの申し出があったので,政府は8月29日にこれら造船業を特定不況産業安定臨時措置法による特定不況産業として指定した。このあと,同法に基づき運輸大臣は海運造船合理化審議会に諮り安定基本計画を定め,造船事業者はこの計画に従って設備処理を行うこととなっている。
設備処理は,原則として造船事業者の自主的努力によって行うものであるが,造船業の特殊性から事業場単位でこれを行わざるを得ない場合が予想され,特に造船専業度の高い中手以下の事業者にあっては自主的努力のみではその円滑な実施が困難な実情にある。このため,政府は,中手以下の造船事業者が事業場単位で設備処理を行う場合にその設備及び土地を買収する機関を設けることとし,第85回臨時国会に特定船舶製造業安定事業協会法案を提出するとともに,同協会の資本金20億円のうちの政府出資金10億円を53年度補正予算案に計上した。これらはいずれも同国会において成立したので,近く同協会を設立する運びとなっている。
また,上記答申に示された造船業の仕事量の確保に資するため,巡視船艇等の官公庁船の建造,内航船等の建造,経済協力による船舶建造及び船舶解撤事業の促進についても,53年度補正予算において所要の予算措置を講じている。
さらに,これら諸措置を講じてもなお大きな需給ギャップが見込まれるので操業調整を実施するほか,雇用保険法による雇用安定資金制度の指定業種及び特定不況業種離職者臨時措置法の特定不況業種に造船業等を指定し,労働者の雇用の安定等のための諸措置を講じてきているが,第85回臨時国会において成立した特定不況地域中小企業対策臨時措置法による造船業関連中小企業対策及び特定不況地域離職者臨時措置法による造船業関連地域の雇用対策についても,それぞれ所要の措置を講じることとしている。
|