|
(1) 四半期別にみた国内貨物輸送の動向
53年度の日本経済は,年度後半になるほど内需が力強さを増し,鉱工業生産も各四半期を通じて増加したが,国内貨物輸送もこのような経済の回復基調を反映して 〔1−1−5図〕のとおり順調に増加した。この結果,53年度は,トンキロで前年度比5.8%増となったが,この動向を更に四半期別にみることにする 〔1−1−6表〕, 〔1−1−7図〕。
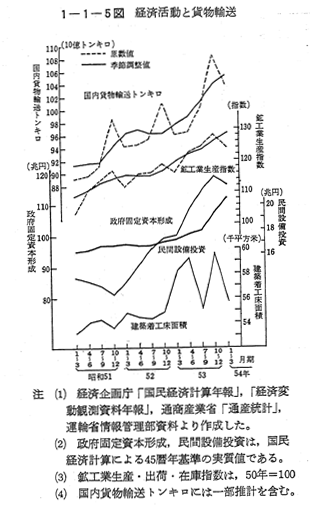
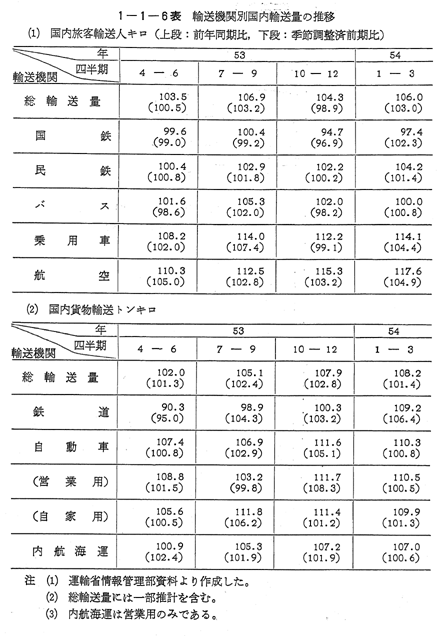
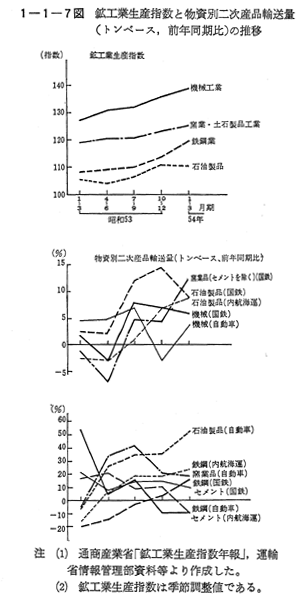
まず,53年4〜6月期には,堅調な消費や公共投資の前倒し執行等により,内航海運(営業用)が,砂利・砂・石材や木材等の建設関連資材を中心に微増となり,自動車がセメント,石油製品等の化学工業品等で輸送量を増加させたが,鉄道が,セメントや石油製品を除くほとんどの品目で減少となったため,国内貨物輸送量全体の伸びも小幅なものにとどまった。7〜9月期にも,引き続く公共投資の拡大や消費の堅調を背景に,石油・石炭製品工業の生産が,前期比でみて,減少から増加に転じたこともあり,石油製品,セメント,その他の窯業品,鉄鋼及び機械類の輸送が大幅に増加し,鉄道を含むすべての輸送機関で輸送量が増加した。10〜12月期には,公共投資や消費に加え,民間企業の設備投資が活発になったことから,工業生産は伸びを高めた。
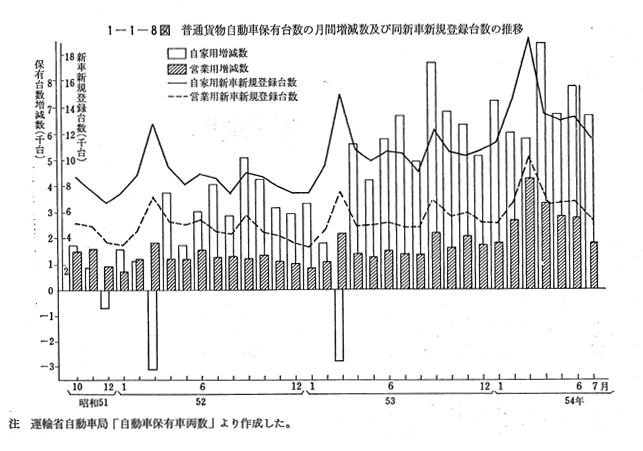
新車新規登録台数は前年同月比でみると,53年5月以降10%以上の増加を示すようになり,11月には32.1%の増加となり,ピークの54年1月には同55.4%増と大幅な伸びとなった。これには景気の回復に伴い輸送活動が活発になったことに加え,53年12月1日より施行された道路交通法の改正の影響もあるものと考えられる。この結果,53年度全体で普通貨物自動車保有台数は9万7千台増加したが,このうち53年12月から54年3月までの増加車両数は3万5千台であり,前年同期比では239.7%増と大幅なものとなった。
|