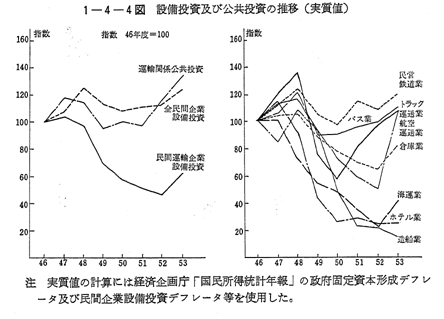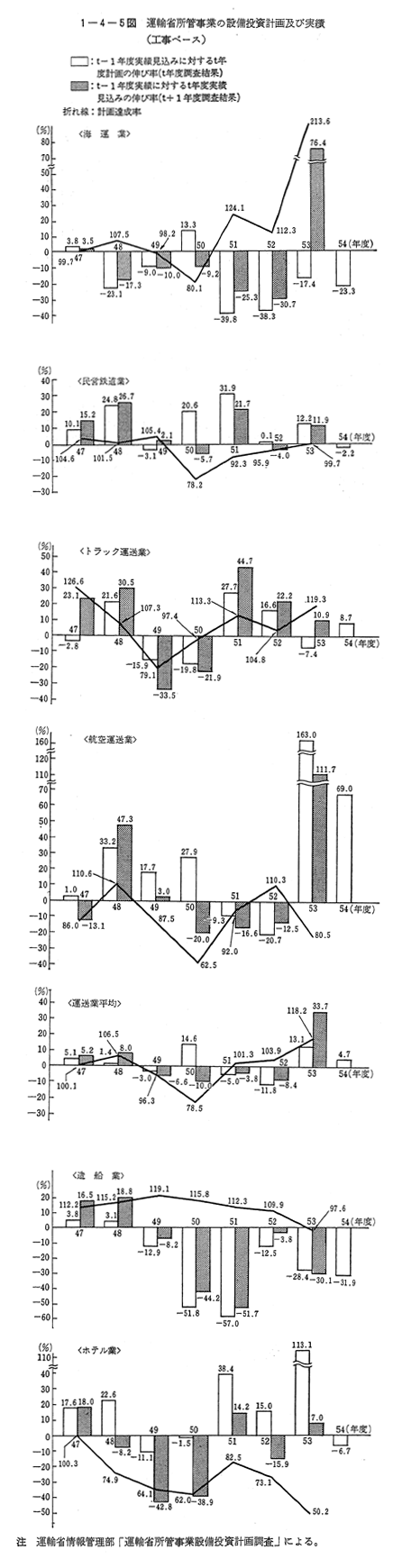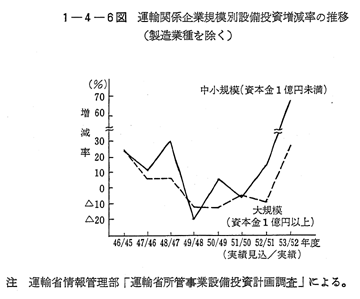|
1 設備投資実績及び計画の推移
運輸省所管事業設備投資計画調査により,民間運輸企業設備投資の投資実績(工事ベース)の推移を昭和46年度以降についてみてみると,名目で54年度(計画)にようやく46年度の水準に達する結果となっている。民間運輸企業設備投資のうち,運送業については46年度を100とした指数で117(54年度計画)とやや増加している。これに対して全民間企業設備投資及び運輸関係公共事業は名目ベースでは増加し,実質ベースではほぼ横ばいとなっており,石油危機後の民間運輸企業設備投資の回復が大幅に遅れていることがうかがえ,53年度は実質ベースでは46年度の6割程度という,結果になっている 〔1−4−4図〕。
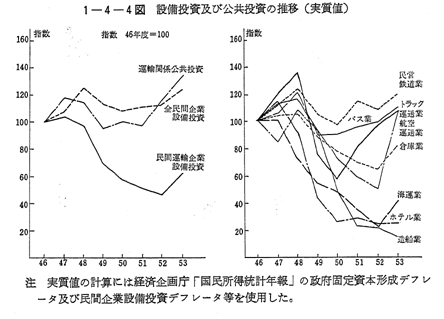
運輸省所管事業のうち主要なものについてみてみると,石油危機後大幅な減少傾向にあった航空運送業は,53年度及び54年度(計画)と大幅増加をみせており,航空輸送の好調及び52年度以降の収支状況の好転を反映した結果となっていると考えられる。
海運業については53年度は仕組船の買戻しという特殊要因もあり,6年ぶりの増加となったものの,54年度(54年2月時点の計画)では再び減少しており,依然として長期低落傾向に歯止めがかかっていない結果となっているが,54年度から利子補給等建造促進の施策が講じられることとなっており,相当の新船建造増が見通される。トラック運送業は主要産業のなかで最も変動の大きなものの1つとなっており,石油危機に際し激減したあと,急速に回復している。バス業,民営鉄道業はそれほど景気変動の影響を受けておらず,石油危機に際し若干変動を受けはしたものの,実質ベースでほぼ横ばいとなっている。ホテル業は48年度から50年度まで急激に減少したあと回復がみられず現在に至っている。造船業については,造船不況を反映し,他のほとんどの業種が増加に転じているにもかかわらず減少傾向に歯止めがかからずにいる。
主要な運輸省所管事業の設備投資計画及び実績並びに計画達成率の推移を工事ベースでみたものが 〔1−4−5図〕である。これによると,海運業は53年度の計画達成率が200を超えており,'きわめて例外的な結果となっているが,これは前年度の調査結果では設備投資の前々年度に対する伸び率がマイナスとなっていたにもかかわらず,53年度になり,国際通貨事情から仕組み船の買戻しを大幅に行う結果となったからである。民営鉄道業は50年度に計画達成率が低下したものの,それ以外の年度ではほぼ計画と実績が一致しており,設備投資の着実性を示している。トラック運送業は49年度に予想を上回る落込みを示し,石油危機をはさんで計画達成率を大きく低下させたが,51年度以降は絶えず実績が計画を上回る結果となっており,好調さを物語っている。航空運送業の設備投資は石油危機後低調であったが,53年度に大幅な投資計画がたてられ回復した。しかし,53年度の計画が大幅増加であったため,計画達成率は8割程度にとどまり未消化分が残った。石油危機後の造船業は,設備投資が絶えず大幅な減少を続け,その落込みの見通しがやや悲観的であったのか計画達成率は100を超える結果となっている。しかし,最近はほぼ計画と実績が一致する方向に収斂している。ホテル業は,47年度に計画と実績が一致した後,絶えず計画を大きく下回る特異な動きを示している。48,49,50年度は予想以上の落込みの結果,計画達成率も60〜70%となり,石油危機の影響と考えられるが,51年度以降は投資意欲が回復したにもかかわらず実績が伴わない結果となっており,53年度では計画段階では倍増であったにもかかわらず実績では微増にとどまり,計画達成率は50%となった。
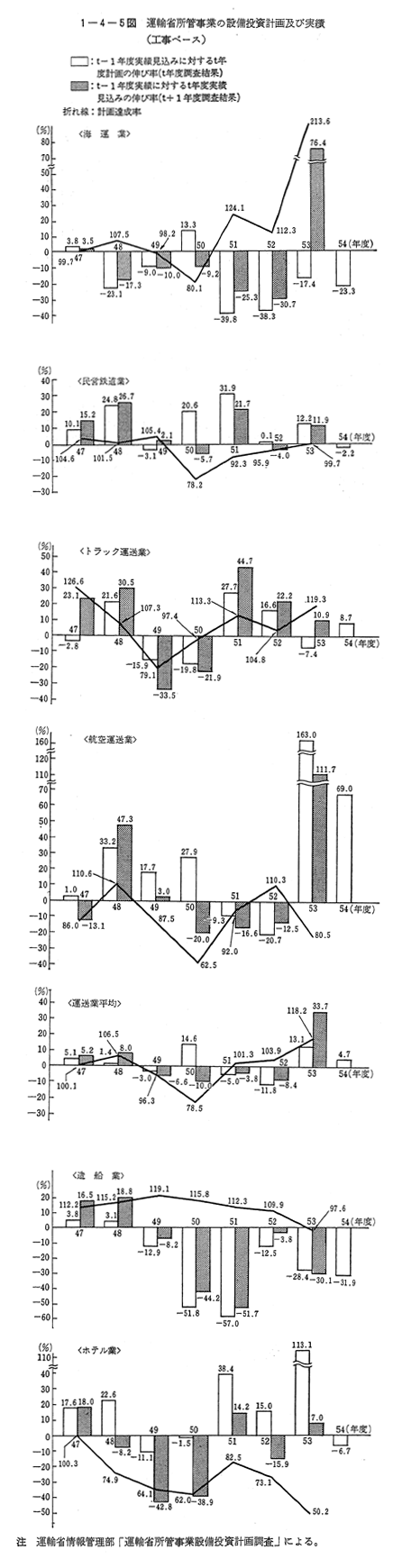
企業規模別に,運輸業の設備投資増減率の推移をみると,資本金1億円未満の中小規模の企業の設備投資の増加が大規模な企業より早く現われている 〔1−4−6図〕。これは,1つには資金需要の増大する好況期には,中小企業等の資金調達が困難な場合があり,また金利水準の変化に対する速い対応が可能な中小企業の設備投資が資金需要の少ない時期に相対的に多い傾向があるという金融的な理由が考えられるが,今回の回復局面においては既にかなり長い期間にわたり金融の緩和が続いていることを考慮すると,'むしろ中小企業の設備の規模が大企業に比べて小さいため,意思決定が早いこと等,中小企業の特性に起因する面が強いと考えられる。
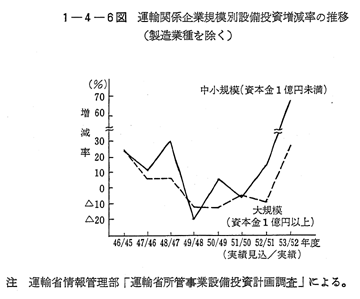
|