|
2 民間設備投資の動機
日本開発銀行が行った設備投資計画調査結果(54年度分,工事ベース,54年2月実施)によれば,54年度計画の投資動機を53年度と比較すると,製造業では,能力増強投資が27.0%から24.2%へと比率が低下しており48年度以降依然として減少傾向にある(同行調査結果によれば,48年度44.1%,49年度38.1%,50年度30.9%,51年度29.3%,52年度29.4%)。これに代って合理化,省力化投資が徐々にウエイトを高めてきており,48年度23.1%であったものが53年度24.2%,54年度28.7%となっている。非製造業は能力増強投資の比率が依然として高く,51年度以降は7割台を維持しており,他の投資動機は余り変化がない。また,経済企画庁の資料である「安定成長下への対応を進める企業の行動」に関する調査結果によれば,各企業が今後3年間で力を入れる設備投資分野は,製造業では省力化,合理化投資が第1位(37.8%)であり,非製造業では老朽設備取替投資が第1位(31.6%)であるが,省力化,合理化投資も25.7%,既存製品の能力拡充投資も19.5%とかなりのウェイトを占めている。同調査結果によれば,運輸・通信業についても非製造業全体とほぼ同じような構成比となっているが,研究開発投資があがっていないことが特色である 〔1−4−7図〕。
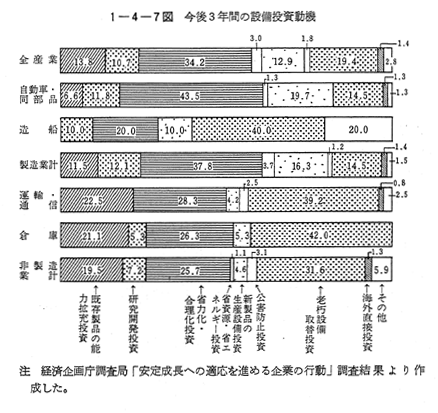
次に運輸省所管事業のうち主要なものについての設備投資の動機の動向を,51-54年度についてみたものが 〔1−4−8表〕である。これによれば外航海運業は能力増強投資から維持補修投資へとややウェイトを移す傾向がみられるが,内航海運業は能力増強型の傾向となっている。バス業は圧倒的に維持補修投資の占める割合が高い。他はあまり特徴がない。トラック運送業も,バス業と同様に維持補修投資の占める割合が約半分であるが,トラック輸送の好調等を反映して能力増強の占める割合も増加しつつあり,54年度(計画)では36.1%となっている。民営鉄道業は能力増強がややウエイトを落しつつあるも依然として半分を超えており,また,安全対策投資,サービス改善投資のウエイトが高くなってきていることも特徴的である。航空運送業は,輸送の好調を反映して圧倒的に能力増強投資の比率が高く,しかもその比率を増加させつつある。
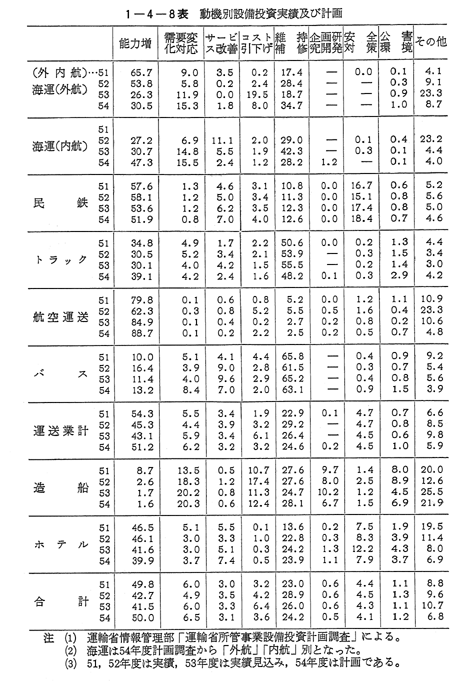
倉庫業では能力増強が51年度に比べて52年度は大幅にその比率を低下させたものの,54年度(計画)では再び約50%を占めるようになってきている。その他,維持補修投資も30〜40%を占めているが,需要変化に対応するための投資が他に比べて高いことも特徴的である。造船業は運送業部門に比べて投資動機がバラエティーに富んでいることが特徴的であり,運送業ではほとんどなかった企画研究開発投資,コスト引下げ投資,公害環境投資が常に一定の割合を確保していることと,不況を反映して能力増強投資が極端に少ないことが特記事項としてあげられる。ホテル業は他の業種に比べてサービス改善に力を入れているのが目立っている。
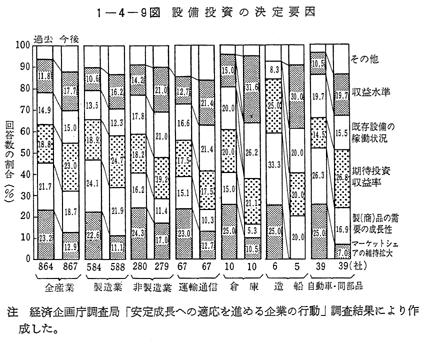
これを運輸・通信業でみると,過去については「マーケットシェアの維持拡大」(23.0%),「期待投資収益率」(17.5%),「既存設備の稼働状況」(16.6%)となっているのに対して,今後については,「既存設備の稼働状況」(21.4%),「収益水準」(21.4%),「期待投資収益率」(17.5%)の順となっている。全産業の場合と同様,運輸・通信業もより利益指向の意識が定着してきていると言える。造船業でみると,過去については「期待投資収益率」,「マーケットシェアの維持拡大」,「既存設備の稼働状況」が要因であったが,今後については「マーケットシェアの維持拡大」を要因とする回答がゼロであることが極めて特徴的である。
|