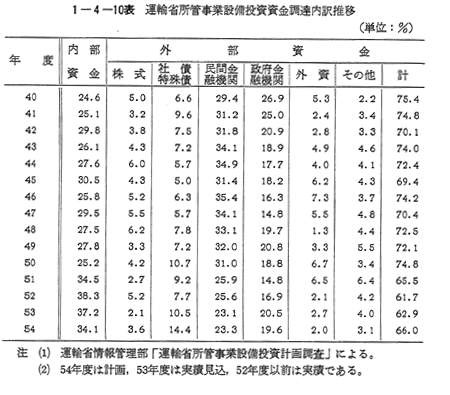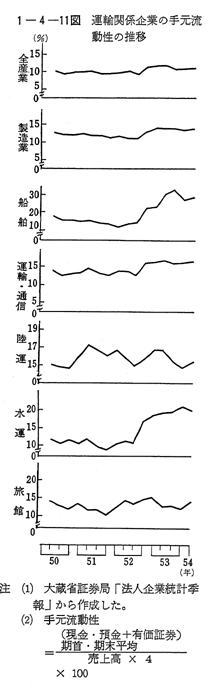|
3 設備投資資金調達
54年度(計画)にみられる設備投資拡大の動きは,高度成長期の設備投資拡大とは似て非なるパターンで「安定成長対応型」ともいうべき性格を備えており,それは資金調達面にも表われている。
高度成長時代は「借入金による設備拡張」が大勢を占めていた。金利を払っても,なお利益が出るほど需要はおう盛だったからである。ところが,石油危機後の需要後退で,金利は企業にとって重荷になり,企業は減量経営の一環として,借入金の返済につとめてきた。この結果,設備投資の資金調達における内部資金の比率が相当高いウエイトを占めるようになった。
運輸省所管事業設備投資計画調査(この調査では資金調達内訳は,いわゆる純増ベースとは異なり,借入金の返済分を控除していない段階でとらえている。)によれば,運輸省所管事業全業種合計では 〔1−4−10表〕のとおり,内部資金が40年代においてはほぼ20%台であったものが,51年度以降は30%台に上昇しており,安定成長下における内部資金比率の上昇という一般的傾向がここでもみられる。運輸省所管事業全業種合計で特徴的なことは,政府金融機関からの借入比率が高いことであり,交通関係事業のいわゆる公益性を反映した結果となっている。また,民間金融機関からの借入比率は,47年度以降減少傾向にあり,特に51年度以降は30%を割り,25%から23%と徐々にそのウエイトを低くしてきている。株式については一般的な傾向が見出せないが,社債・特殊債については53年度,54年度とそのウエイトを高めており,開銀調査の53年度,54年度の傾向と一致している。
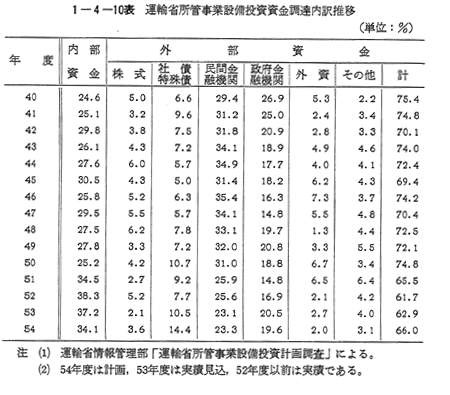
運輸省所管事業のうち主要業種についてみると,運送業ではバス事業,トラック事業が内部資金比率が高く,海運業,民営鉄道業,航空運送業といった大企業の多い分野では内部資金比率が相対的に低くなっている。しかも成長産業である航空運送業では内部資金比率が,52年度に比べ54年度(計画)では半減している。その他,構造不況業種である造船業ではその内部資金比率を高め,減量経営に努力している跡がみうけられるが,ホテル業,倉庫業では40年代後半に比べて50年代は内部資金比率が低下しており,一般の傾向と異なるところが特徴的である。
政府関係金融機関の比率が高いものは,海運業,民営鉄道業であるが,倉庫業,ホテル業においても近年そのウェイトを急速に上げつつある。その他,運輸省所管事業の特徴的なことは,民営鉄道業,航空運送業における社債・特殊債のウェイトの高いこと,航空運送業,造船業における外資のウェイトが他の業種に比べて高いことがあげられる。安定成長下において企業の資金事情が好転していることは,内部資金比率の上昇という傾向とともに企業の手元流動性の上昇傾向からもうかがえ 〔1−4−11図〕,運輸関係については,陸運関係を除き,概ね,手元流動性が上昇傾向にある。
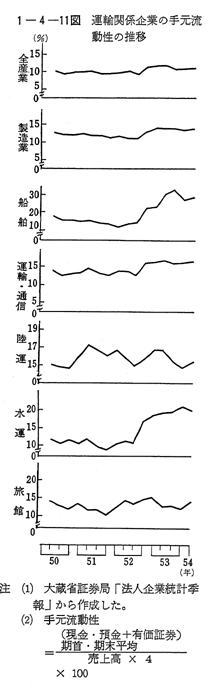
|