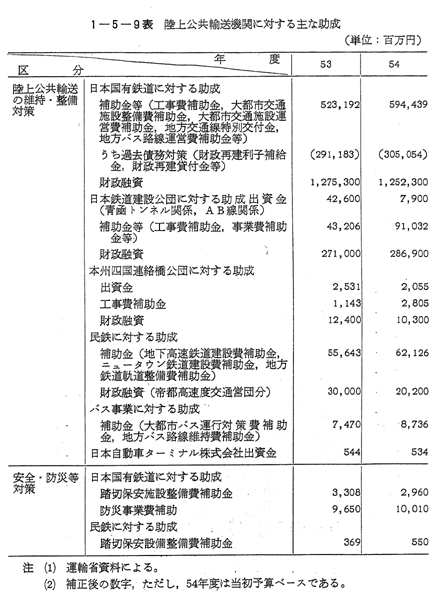|
4 運賃及び助成
53年度においても各種の運賃料金の改定が実施されたが,これらの改定率は物価,人件費の安定等も寄与し,一般的に前回の改定率を下回っている。
運輸事業の経営は,能率的な経営を前提とする適正な原価に見合った運賃,料金収入により維持されることが原則であり,運輸事業者自らの絶えざる合理化努力による生産性向上により吸収しきれない人件費,物件費等の費用については運賃改定により補っていく必要がある。さもなければ,公共輸送機関の経営が悪化することにより,サービス水準の低下や必要な設備投資の遅れをもたらすなど,その役割を果たしえない結果となる。のみならず,ひとたび経営に破綻をきたした場合には,その建直しには必要以上の費用を必要とする。将来とも良好な輸送サービスを維持していくためには,上記原則にのっとり,運賃問題に適時適切に対処することが必要である。
この場合,最近の各種輸送機関相互間の競争の激化等に鑑み,運賃制度の検討も必要であり,国鉄の全国一律運賃制度の問題鉄道,航空,自動車等の異種輸送機関相互間の運賃のあり方の問題,通勤・通学定期割引をはじめとする各種の割引制度の見直しの問題等につき,きめ細かな制度の検討が必要である。
一方,国民経済,国民生活の要求に応えて輸送サービスを確保するためには運賃規制と同時に様々な公的助成措置が必要である。
例えば,①過疎現象とモータリゼーションの進行によって需要が減退している地域において地域住民の足を確保する上で不可欠な地方路線の維持,②資本の懐妊期間が長く,かつ,交通空間のひっ迫,地価の上昇,環境費用の増大等から膨大な施設建設費を要する新幹線や都市交通等の社会経済の発展の基盤となる施設の整備,更には,③大都市周辺部のニュータウンや郊外の大住宅団地,工業団地等の開発に伴う将来の需要増にそなえて先行的な輸送手段の確保,等の場合について,種々の助成がなされており,陸上公共輸送機関に対する53年度の助成額及び54年度の予算額のうち主なものは 〔1-5-9表〕のとおりとなっている。
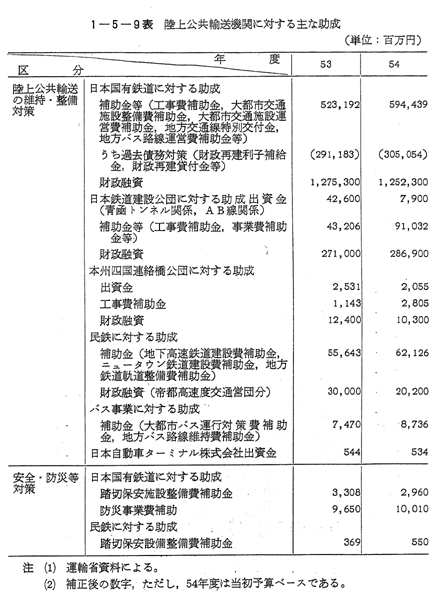
このように,国民生活の安定充実のために財政が果たしている役割は大きいが,今後とも,住みよい地域社会を作るため,定住圏整備の基盤的役割を果たす地域交通について,地域社会の中心都市の都市交通の整備改善を進めるとともに,都市と農山村とを一体とした交通網の整備を推進する必要がある。このため,大都市及び地方主要都市においては,都市機能の維持を図るとともに,エネルギー,環境'空間等の制約条件に適切に対処するため,地域の実情に応じ都市高速鉄道やバス等の大量公共輸送機関を計画的に整備する必要がある。また,農山村その他の地域においては,当該地域の中心都市との関連を考慮しつつ,地域住民の安定的な足の確保という見地から,地方バス,地方鉄道,離島航路離島航空路等の公共輸送を維持し,改善するための施策を推進するとともに,地方・離島港湾,離島空港等の整備を図る必要があり,今後とも必要に応じて適切に安定的かつ計画的な措置を講じていく必要がある。
|