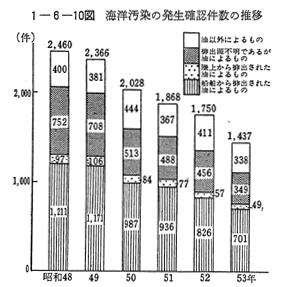|
2 海洋汚染の現況と対策
(1) 海洋汚染の現況
港湾及び沿岸海域を含む公共用水域の水質測定結果によると,カドミウム等の有害物質の環境基準はほぼ達成されている。有機汚濁の指標であるCODの環境基準の達成状況ば,海域では水域数で76.9%で前年度を0.3%上回っている。方,海洋汚染の発生について海上保安庁が確認した件数は, 〔1−6−10図〕に示すとおり48年以降減少傾向にある。このように海洋の汚染状況は,排出規制や海域における監視・取締体制の強化等もあって総体的に改善の傾向にあるが,なお,内湾及び内海のような閉鎖性水域においては水質の状況は必ずしも十分ではないので,今後さらに改善に努める必要がある。なお,海上保安庁が53年に実施した廃油ボールの実態調査によれば,依然として南西諸島等黒潮流域において廃油ボールの漂流,漂着が多いが,従来廃油ボールによる汚染の少なかった日本海等においても量的に多いところが出はじめた。
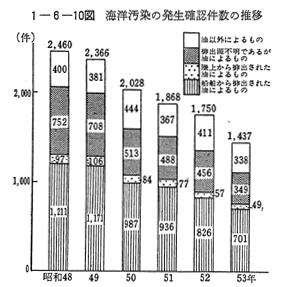
(2) 海洋汚染防止対策
「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」等に基づき種々の海洋汚染防止対策を講じているが,その第一として海洋の汚染因子である油及び廃棄物の排出について規制しており,この規制を担保するためビルジ排出防止装置の備付けの義務付け,廃棄物排出船の登録等の措置がとられている。また,船舶内において生じる油性バラスト等の廃油を処理するための廃油処理施設,海洋性廃棄物の処理施設,廃棄物を埋立処分するための廃棄物埋立護津の整備を図っている。
第二には,タンカー等の船舶及び沿岸の石油関係施設から油が流出した場合に対処するため,タンカー及び油保管施設等には,オイルフェンス,油処理剤及び油吸着剤の備付けを義務付けているほか,タンカー所有者に対する油回収船等の配備の義務付けを図っており,更に各港湾等において油回収船の配備その他資機材の備蓄をしている。二のほか海洋汚染の防除事業として,港湾区域内では有害物質等を含む堆積汚泥の俊傑事業等,港湾区域内及び一般海域においては浮遊ごみ及び浮遊油の回収事業を実施しており,54年度より瀬戸内海において底質浄化に係る海洋環境整備パイロット事業の実施設計調査に着手した。
第三として,これらの義務付けの実効と規制の励行を確保するため,海上保安庁は引き続き海上公害関係の資機材の整備,分析鑑定機能の充実等監視・取締体制の強化を図っている。
更に,海洋汚染は全地球的な環境問題であることに鑑み,積極的に国際協力を推進する必要がある。主に陸上で生じた廃棄物の海洋への投棄を規制するための条約として,1972年の海洋投棄規制条約があるが,これは75年8月30日に発効し,加盟国数も79年10月15日現在43か国に及んでいる。我が国としてもその批准・国内法化を図るための準備作業を進めているところである。
近年,タンカーからの油の流出による海洋汚染が国際的問題となっており,73年にすでに海洋汚染防止条約が採択されていたところであるが,77年3月アメリカ大統領は,新たにタンカーの安全及び汚染防止の強化に関する声明を発表した。これを受けて,政府間海事協議機関(IMCO)において検討が行われ,78年2月「1973年の海洋汚染防止条約に関する1978年議定書」が採択された。本議定書は,先の条約を強化し,一定のタンカーに分離バラストタンク(SBT),原油洗浄方式(COW)またはクリーンバラストタンク(CBT)等を義務付けようとするものであり,我が国としてもこれを早期に批准し,国内法化するために検討を進めているところである。
海洋においては,交通,漁業,海底資源の採取,レクリエーション等広汎な利用がなされており,今後さらにその利用・開発の増加が予想される。このため,その利用・開発の影響が広範囲に及ぶという海洋の特殊性を考慮し,広域的,長期的視点に立脚して海洋の利用・開発と海洋環境の保全との調和を図る必要がある。
|