|
3丂変偑崙宱嵪偵偍偗傞僄僱儖僊乕廀媼偺摦岦
丂丂変偑崙偺僄僱儖僊乕徚旓検偼,愇桘姺嶼偱387昐枩僩儞(徍榓52擭搙)偱偁傝 乲俀亅侾亅侾侽恾乴,僄僱儖僊乕嫙媼偵偍偗傞愇桘偺愯傔傞妱崌偼,変偑崙堦師僄僱儖僊乕偺74.6%偱偁傞(52擭搙愇扽14.8%,悈椡4.8%,尨巕椡20%,偦偺懠3.8%,乽憤崌僄僱儖僊乕摑寁乿)丅愇桘偼僈僜儕儞,寉桘,廳桘摍偺愇桘惢昳偲偟偰捈愙巊梡偝傟傞傎偐偵,揹椡,搒巗僈僗摍偲偟偰傕娫愙揑偵巊梡偝傟,揹椡偺敪揹検偺栺63.8%偼愇桘偵埶懚偟偰偄傞丅変偑崙偺庬椶暿僄僱儖僊}嵟廔廀梫峔憿傪晹栧暿偵傒傞偲 乲俀亅侾亅侾侾恾乴,堦師僄僱儖僊乕偺慖戰壜擻惈偺偁傞揹椡偵偍偄偰偼,峼岺嬈晹栧,柉惗晹栧偺妱崌偑崅偄偺偵偔傜傋偰,僈僜儕儞.,寉桘偲偄偭偨捈愙徚旓偝傟傞愇桘惢昳偵偍偄偰塣桝晹栧偺妱崌偑崅偄偙偲偑傢偐傞(塣桝晹栧偱僈僜儕儞偼99%傪,寉桘偼64%傪徚旓偟偰偄傞丅)丅
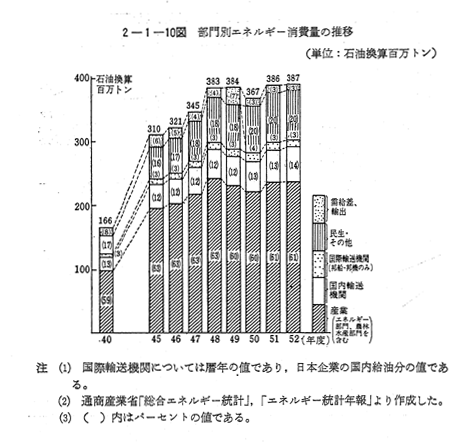
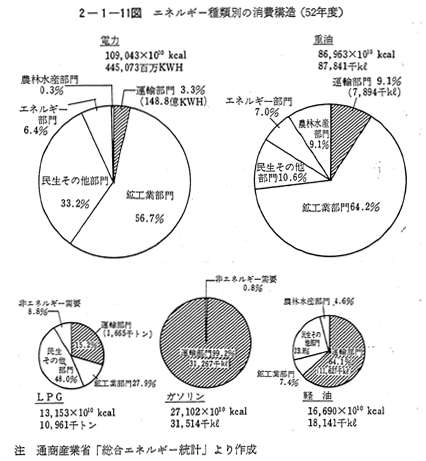
丂丂徍榓54擭6寧偵搶嫗偱奐嵜偝傟偨庡梫崙庱擼夛媍偵偍偄偰偼,変偑崙偺60擭偺桝擖愇桘偺栚昗偵偮偒乽1擔摉傝630枩僶乕儗儖偐傜690枩僶乕儗儖(擭娫栺3.65壄Kl乣4.0壄Kl偵憡摉偡傞丅)偺娫偺斖埻傪挻偊側偄悈弨傪嵦梡偡傞丅擔杮偼,偙偺栚昗傪掕婜揑偵専摙偟,偐偮,帪乆偺恑揥媦傃惉挿尒捠偟偵徠傜偟偰偙傟傪堦憌柧妋側傕偺偲偟,傑偨傛傝掅偄悢抣偵嬤偯偔偨傔偵,愡栺,棙梡偺崌棟壔媦傃戙懼僄僱儖僊乕尮偺擬怱側奐敪傪捠偠偰,愇桘桝擖傪嶍尭偡傞傛偆嵟慞傪恠偔偡乿偙偲偑崌堄偝傟偰偍傝,怴宱嵪幮夛7僇擭寁夋偵偍偄偰傕,60擭搙偵偍偗傞僄僱儖僊乕廀媼偼,尨桘姺嶼偱5..85乣60壄Kl偲尒捠偟偑棫偰傜傟,愇桘桝擖検(桝擖LPG傪娷傓丅)偼,3.65乣4.0壄Kl偲尒捠偟偑棫偰傜傟偨(宱嵪婇夋挕帋嶼抣)丅傑偨,54擭8寧偵偼,憤崌僄僱儖僊乕挷嵏夛(捠彜嶻嬈戝恇偺帎栤婡娭)廀媼晹夛偵偍偄偰乽挿婜僄僱儖僊乕廀媼巄掕尒捠偟乿偺拞娫曬崘偑側偝傟偨 乲俀亅侾亅侾俀昞乴偑,摨曬崘偵傛傟偽,宱嵪惉挿棪傪52擭搙乣60擭搙擭棪6%庛,60擭搙乣65擭搙擭棪5%掱搙,65擭搙乣70擭搙擭棪4%掱搙偲偟,徣僄僱儖僊乕棪傪60擭搙偵偼12%掱搙,65擭搙偵偼15%掱搙,70擭搙偵偼17%掱搙(偄偢傟傕48擭搙婎弨)偲偟偨応崌偵偍偗傞僄僱儖僊乕偺廀梫偼,愇桘姺嶼偱,60擭搙偵偼5壄8,000枩Kl掱搙,65擭搙偵偼7壄噄掱搙,70擭搙偵偼8壄1,000枩Kl掱搙偵側傞傕偺偲偟偰偄傞丅
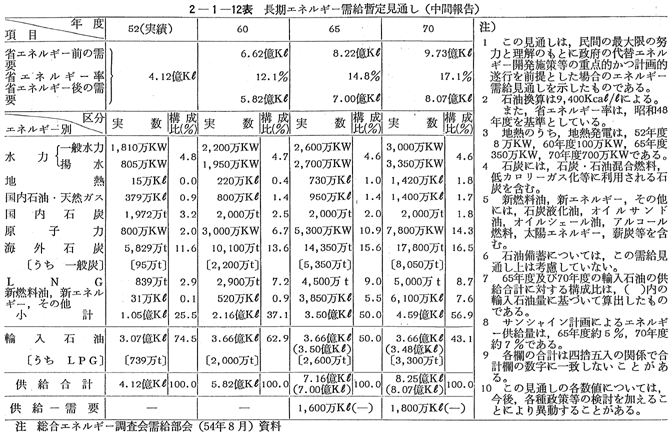
丂丂偙傟傜偺尒捠偟偼偄偢傟傕変偑崙偺愇桘桝擖偵偮偄偰愇桘婋婡慜偺傌乕僗偱偺検揑奼戝偑偱偒側偄偲偟偰偍傝,挿婜揑偵傒偨応崌偵偼,桝擖検偺憹壛偑傎偲傫偳婜懸偱偒側偔側傞帠懺傕峫偊傜傟,変偑崙宱嵪偵偍偗傞僄僱儖僊乕廀媼忣惃偼崱屻傑偡傑偡尩偟偔側傞偙偲偑梊憐偝傟傞丅
|