|
2 貨物輸送の概況
54年度の我が国の貿易活動をみると 〔1−1−8図〕のとおり,円安基調が続くなかで輸出は各四半期を通じて好調に伸び,数量ベースで前年度比6.1%増(53年度は5.6%減)となった。一方,輸入は,原油価格の相次ぐ値上げや海外原材料高により金額ベースでは増加が続いたものの,数量ベースでは次第に横ばいとなり,年度計では前年度比で53年度9.8%の増加のあと,5.8%の増加にとどまった。
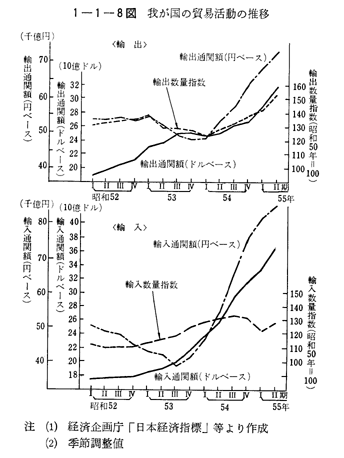
第1節に述べたように,54年度の日本経済は好調な輸出と堅調な民間設備投資を主因に拡大を続けたが,個人消費は年度後半に伸び悩みとなり,年度末には公的固定資本形成も大幅減となった。このような経済の動きは,各四半期の貨物輸送活動にどのように反映されたであろうか(以下,原則として前期比による。) 〔1−1−9図〕。
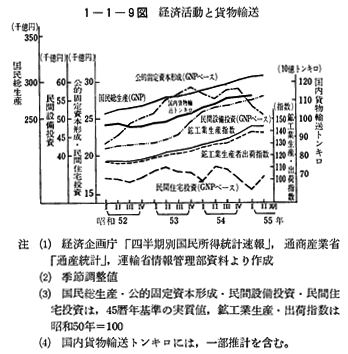
まず,54年4〜6月期,7〜9月期には,経済の着実な拡大の下で,実質GNPの伸びを上まわるテンポで総輸送トンキロは増加したが,1〜3月期,4〜6月期と公共事業が抑制されたこともあって,鉄道はセメントの減少等からマイナスを続け,自家用自動車も4〜6月期は低い伸びにとどまった。10〜12月期,1〜3月期は経済が輸出の好調な伸びに支えられて拡大したことから,総輸送トンキロの伸びは実質GNPの伸びを下まわるようになり,特に内航海運は,原油の2次輸送の減少を主因にマイナスに転じ,鉄道も10〜12月期までマイナスを続けた。一方,生産,出荷が依然増加を続けるなかで,営業用自動車は堅調な増加を続け,年度後半の総輸送トンキロ増加の主役となったが,個人消費が伸び悩みをみせるにつれ,生活関連物資の輸送が多い路線トラックは,次第に前年同月に対する伸び率が鈍化していった。
|