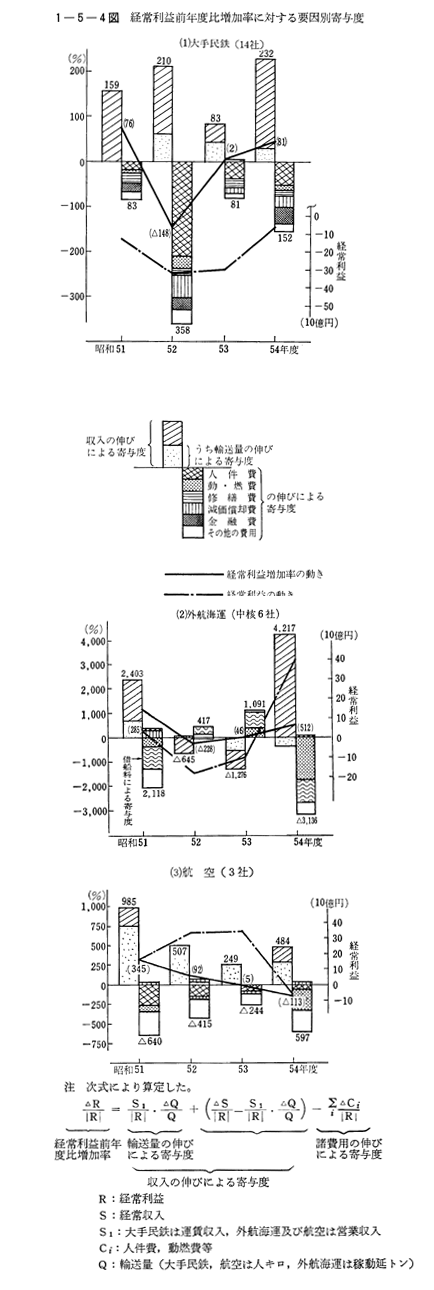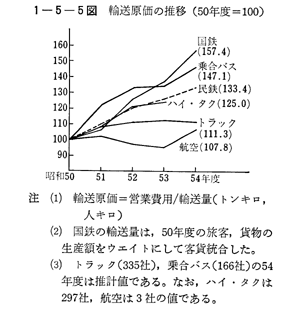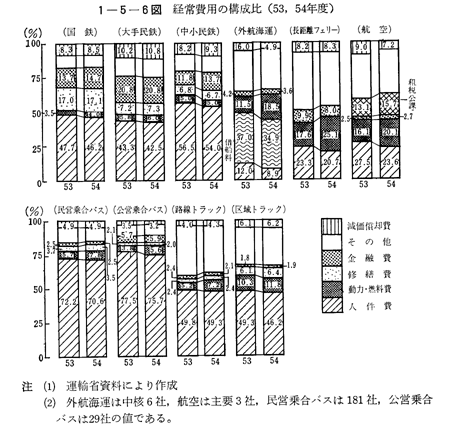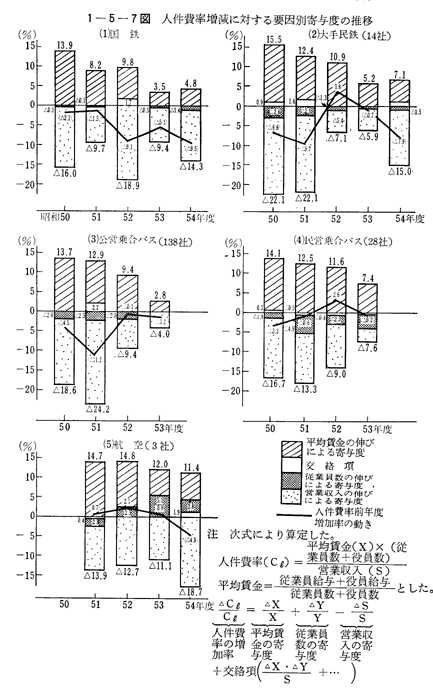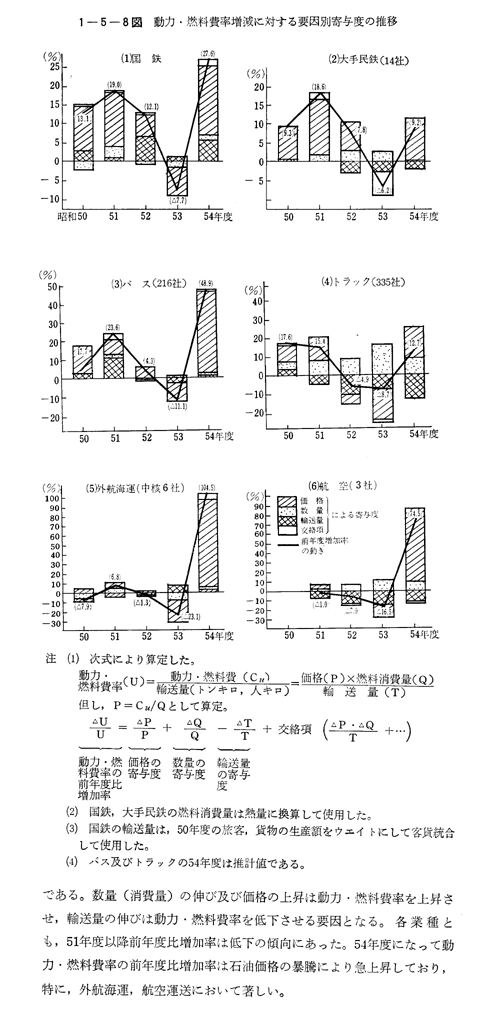|
4 経営状況の分析−コスト分析を中心として
(1) 経常収支の動向
〔1−5−4図〕は,大手民鉄(14社),外航海運(中核6社)及び航空運送(主要3社)について,経常収支の前年度比増加率に対する要因別寄与度をみたものである。各業種とも,ここ数年経常収支の変動が激しいことから,各要因の寄与度が大きく変化している。
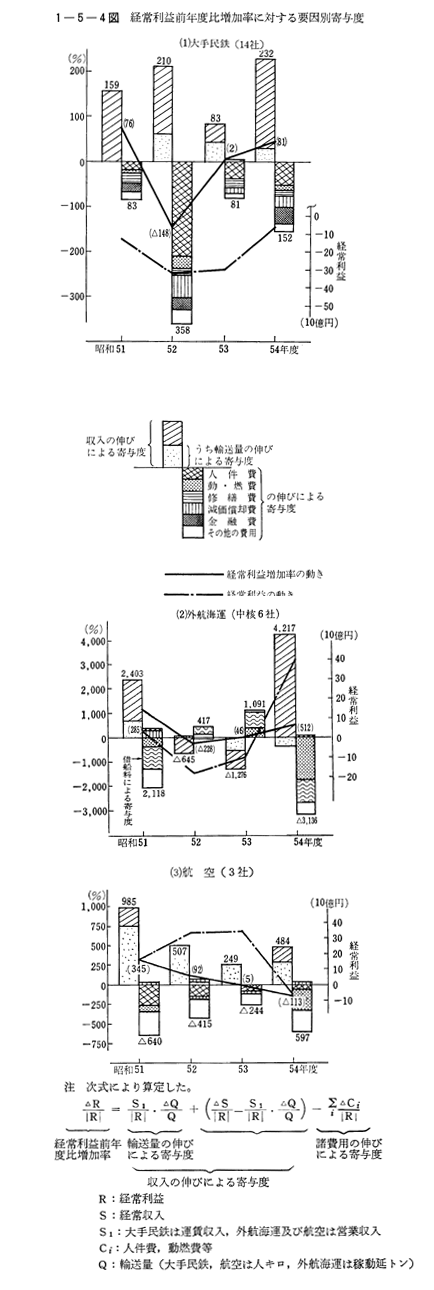
大手民鉄は,50年末の運賃改定が寄与して51年度やや回復したが,52年度は人件費を中心とする諸経費の伸びが大きく寄与して赤字幅を拡大した。53年度は,動力・燃料費の伸びがマイナスになり,人件費,金融費の伸びも緩やかであったことにより,経常利益は回復の気配をみせた。54年度は,金融費,動力・燃料費の大きな伸びにもかかわらず,54年初の運賃改定が寄与して赤字幅を大きく縮小させた。
外航海運は中核6社でみると,51年度は減価償却費,人件費,修繕費が減少する等減量経営が効果をあげるとともに,輸送量(稼動延トンによる)も伸びて黒字に転じたが,52,53年度と市況の低迷による減収が続き,2年連続の経常費用の縮小にもかかわらず赤字が続いた。なお,借船料は,51年度増加のあと52,53年度と2年連続して減少している。54年度は,輸送量の減少,燃料費の大幅増にもかかわらず運賃市況の好転により経常利益は黒字になった。
航空運送は,主要3社とも50年度は赤字であったが,51,52年度は輸送量の伸びによる収入の伸びが順調に推移し,また,減価償却費,金融費が減少する等費用の伸びが緩やかであったことから,経常利益の伸びは順調であった。しかし,53年度以降収入の伸びに対し費用の伸びが大きくなり,54年度は燃料費を中心とする費用の大幅増が寄与して赤字に転落した。
(2) 費用の動向
〔1−5−5図〕は,輸送原価(単位輸送量当たりの営業費用)の推移をみたものである。航空運送は,輸送量の順調な伸びにより52,53年度と減少したが,54年度は燃料費を中心とする費用の増加により急上昇した。他の業種はいずれも上昇の傾向にあり,特に国鉄は輸送量の減少を反映して伸び率が高い。運輸事業の費用構成においては,一般に人件費のウエイトが高く(54年度で全産業10.7%,製造業14.1%に対し運輸・通信業30.7%,(大蔵省「法人企業統計年報」)),減価償却費,修繕費,動力・燃料費のウエイトも高いことが特徴である。
〔1−5−6図〕は,経常費用の費目別構成比を53,54年度についてみたものである。各業種に一般的な傾向として,人件費の割合が低下し,民営鉄道を除き動力・燃料費の割合が急上昇している。
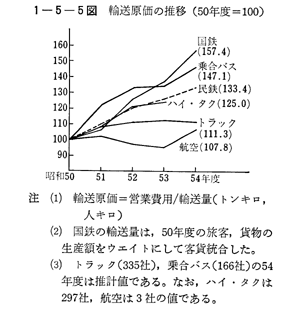
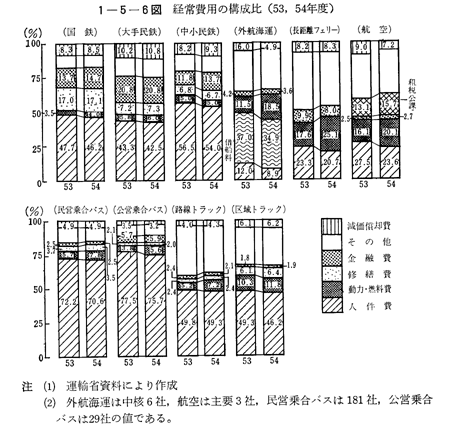
ア 人件費率の動向
〔1−5−7図〕は,人件費率(単位営業収入当たりの人件費)の前年度比増加率に対する要因別寄与度をみたものである。平均賃金の伸び及び従業員数の伸びは人件費率を上昇させ,営業収入の伸びは人件費率を低下させる要因となる。国鉄は,営業収入の伸びが平均賃金の伸びを上まわり,従業員数の減少も寄与して人件費率は低下の傾向にある。大手民鉄は,50,51年度の営業収入の大幅増と従業員数の減少が寄与して低下したが,52年度は営業収入の伸び悩みにより上昇した。53年度以降,平均賃金の伸びの鈍化と営業収入の伸びが寄与して再び減少に転じている。公営乗合バスと民営乗合バスでは,いずれも従業員数の減少が高い割合で寄与しているが,公営に比べて民営の方が営業収入の伸び悩みから人件費率の減少幅が小さい。航空運送では,51年度から53年度まで人件費率が上昇していたが,54年度は営業収入の伸びが寄与して減少に転じている。
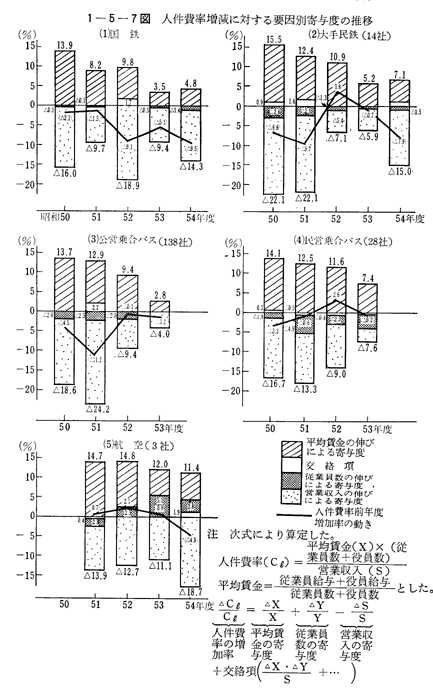
イ 動力・燃料費率の動向
〔1−5−8図〕は,動力・燃料費率(単位輸送量(トンキロ,人キロ)当たりの動力・燃料費)の前年度比増加率に対する要因別寄与度をみたものである。数量(消費量)の伸び及び価格の上昇は動力・燃料費率を上昇させ,輸送量の伸びは動力・燃料費率を低下させる要因となる。各業種とも,51年度以降前年度比増加率は低下の傾向にあった。54年度になって動力・燃料費率の前年度比増加率は石油価格の暴騰により急上昇しており,特に,外航海運,航空運送において著しい。
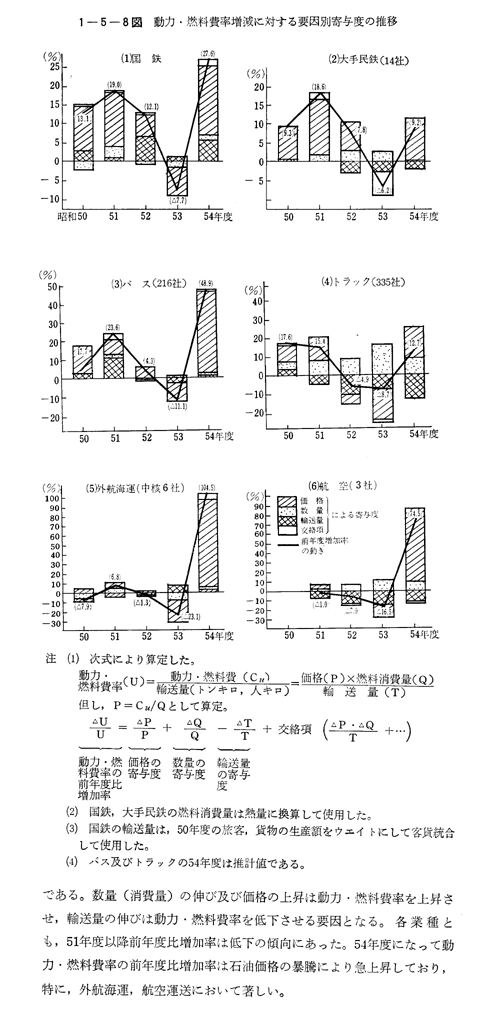
|