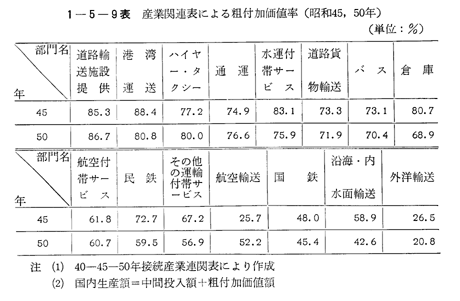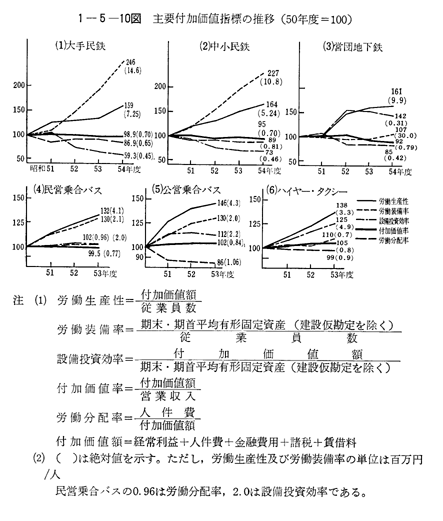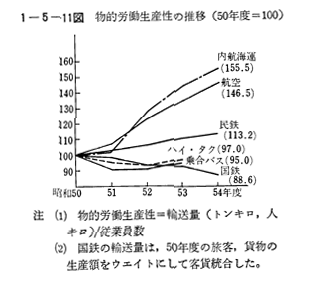|
5 生産性の動向
運輸部門の国内生産額を40-45-50年接続産業連関表(50年価格)でみると,40年6.75兆円,45年11.11兆円,50年12.53兆円と推移している。また,粗付加価値額を国内生産額で割った粗付加価値率をみると,運輸部門は商業・金融部門,農林水産部門等と並んで中間投入率が低く,したがって,粗付加価値率が高いという特徴を持っているが,40年57.1%,45年65.1%,50年58.6%と推移しており,45年から50年にかけて低下していることが注目される。これは,エネルギー部門,商業・サービス部門等への中間投入額が増加したことと営業余剰がマイナスに転じたことによるものである。 〔1−5−9表〕は,同産業連関表により45年,50年の運輸の各部門の粗付加価値率をみたものである。運輸部門の平均値より低い部門は外洋輸送(外航海運),沿海内水面輸送,国鉄,航空輸送であるが,外洋輸送及び沿海内水面輸送の粗付加価値には用船によるものが含まれていないことに注意を要する。国鉄は営業余剰がマイナスであること,航空輸送では航空付帯サービス業等への投入額が大きいことにより,粗付加価値率が低く表われている。航空輸送は,例外的に45年から50年にかけて粗付加価値率を大きく伸ばしているが,これには間接税及び社会保険料の増加が大きく寄与している。なお,産業連関表における粗付加価値には,減価償却費は含まれるが,金融費用・賃借料が他部門への投入として付加価値構成要素から除外されていることにも注意を要する。
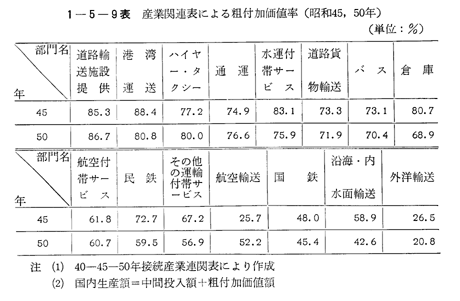
次に,各事業の財務諸表により陸上旅客輸送部門の50年度以降の主要付加価値指標の推移をみてみる 〔1−5−10図〕。
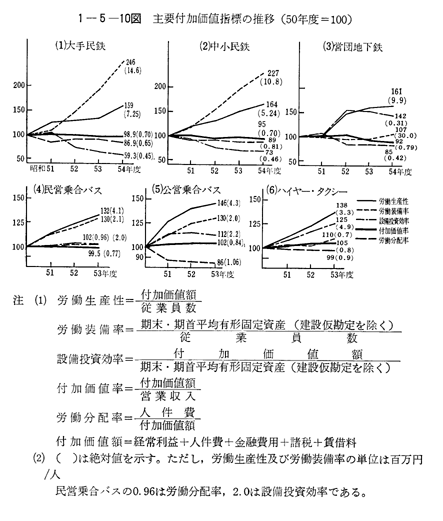
労働生産性(従業員1人当たりの付加価値額)は,各部門とも順調に上昇しているが,民営鉄道各部門で特に著しい伸びを示しいる。これには,従業員数の減少と経常収支の赤字幅の縮小が大きく寄与している。
民営鉄道部門について他の指標をみると,営団地下鉄を除いて労働装備率(従業員1人当たりの有形固定資産)の伸びが著しく,設備投資の充実がうかがえる。一方,設備投資効率(単位有形固定資産当たりの付加価値額)は悪化しており,付加価値を高めるためにより大きな固定資産が必要になったことがうかがえる。営団地下鉄の52年度における労働生産性及び設備投資効率の大幅上昇は,経常収支が黒字に転ずる等付加価値額が大幅に上昇したことによるものである。
労働分配率(単位付加価値額当たりの人件費)は,各部門とも人件費の伸びが付加価値を構成する他の費目の伸びより比較的緩やかであることから低下している。
民営乗合バスと公営乗合バスについてみると,いずれも従業員数の引き続く減少と付加価値額及び有形固定資産の増加により,労働生産性及び労働装備率が上昇している。労働分配率は,民営が横ばい,公営が低下の傾向にあるが,いずれも経常収支の赤字が続いていることにより絶対値が非常に大きいことが特徴である。
ハイヤー・タクシーでは,労働生産性と設備投資効率が順調に上昇している。労働装備率と付加価値率も緩やかな伸びを示しているが,労働分配率はやや低下の傾向にある。また,ハイヤー・タクシーは,陸上旅客輸送部門中労働生産性が最も低く,設備投資効率は最も高い。
各輸送機関の物的労働生産性(従業員1人当たりの輸送量)は, 〔1−5−11図〕のとおりである。国鉄は,輸送量の減少率が従業員数の減少率を上まわって年々低下の傾向にある。一方,民鉄は,輸送量の漸増に従業員数の漸減が相乗的に作用して年々上昇の傾向にある。乗合バスは,国鉄と同じ要因により51年度低下したが,その後輸送量の減少に歯止めがかかりやや持ち直している。ハイヤー・タクシーでは,従業員数は年々増加しており,輸送量が52年度まで漸減したことにより低下してきたが,53年度に輸送量が増加し持ち直している。内航海運では,従業員数が51年度以降減少しており,輸送量の伸びとの相乗効果により著しく上昇している。航空運送では,従業員数は51年度に減少した後増加に転じているが,輸送量の好調な伸びにより年々上昇している。
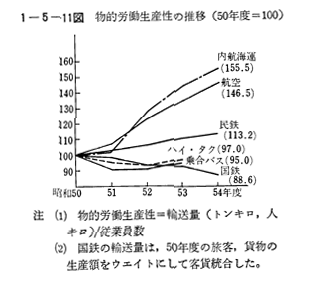
|