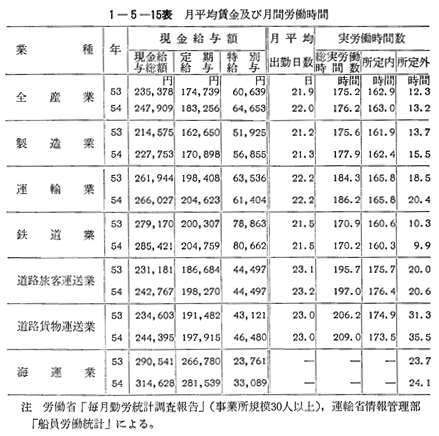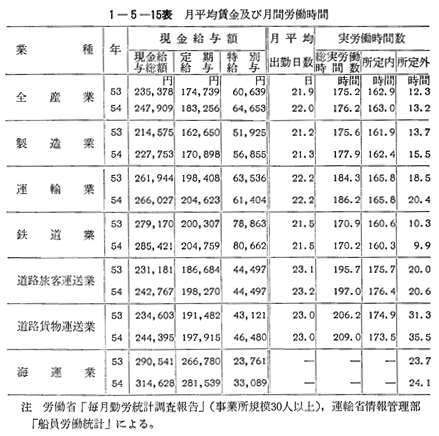|
2 賃金及び労働時間の現状
54年春の賃金交渉は,企業収益の改善,雇用失業情勢の停滞,消費者物価の安定という経済環境の下で行われた。労働省の調べによると,54年の賃上げ結果は,民間主要企業では単純平均で賃上げ額9,959円,賃上げ率6.0%,中小企業ではそれぞれ8,321円,6.5%と,いずれも前年の実績をやや上まわった。
現金給与総額の動きを「毎月勤労統計調査」(労働省)によりみると,54年における調査産業計の平均月間現金給与総額は24万7,909円で,前年比6.2%増(抽出替によるギャップ修正済)となり,前年の伸び率を下まわったが,実質賃金は前年比2.5%増と前年並みの伸びとなった。産業別にみると,建設業が7.8%増と最も大きな伸びを示したのに対し,運輸・通信業では,特別給与の伸びが低かったこともあり,現金給与総額の伸び率は前年を下まわる3.8%増(53年5.1%増)となり,調査産業大分類の中で最も低い伸び率であった。運輸事業における業種別の現金給与総額は, 〔1−5−15表〕のとおりとなっている。
「屋外労働者職種別賃金調査報告」(労働省)によると,54年8月における陸上運送業の1日当たり賃金は,大型貨物自動車運転手の9,860円が最も高く,職種計では9,010円であった。伸び率でみると,荷造手が前年比11%の上昇で最も高く,職種計では6.1%の上昇となっており,前年の7.3%を下まわった。港湾運送業の1日当たり賃金は,デッキマン(起重機運転工に合図を送り,その操作を指図する作業に従事する者)の1万2,340円が最も高く,職種計では1万640円であった。伸び率は職種計で5.5%の上昇となっており,前年の上昇率と同じ水準であった。
労働時間の動きを前述の「毎月勤労統計調査」によりみると, 〔1−5−15表〕のとおりとなっており,54年平均の月間総実労働時間は,調査産業計で176.2時間と前年に比べて更に増加した。所定内労働時間は前年並みの水準であったが,所定外労働時間は,調査産業計で132時間と大幅に増加した。月間平均出勤日数は,調査産業計で22.0日で,ほぼ前年並みの水準であった。運輸省所管業種では,月間総実労働時間,所定外労働時間のいずれも道路貨物運送業で最も高くなっており,54年はそれぞれ209.0時間,35.5時間と前年を上まわった。月間平均出勤日数では,道路旅客運送業の23.2日が最も高くなっており前年を上まわった。
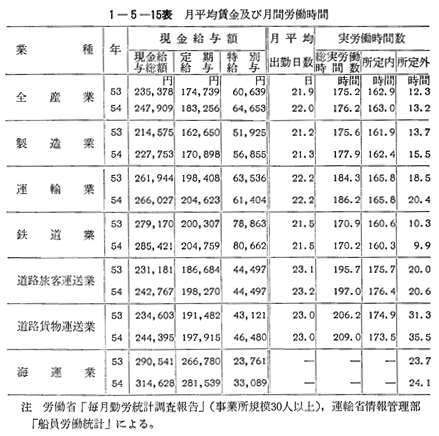
海上労働者については,54年は所定外労働時間で月平均24.1時間となっており,道路貨物運送業に次いで高い水準であり前年を上まわった。
前述の54年6月における屋外労働者の調査でみると,陸上運送関係では,大型貨物自動車運転手の1日当たり労働時間は9.6時間と最も長くなっており,職種計では9.3時間と前年に比べて0.1時間減少した。1か月平均労働日数は,職種計で23日であった。港湾運送関係では,1日当たりの労働時間は,職種計で8.6時間となっており,労働日数は,はしけ長(はしけに乗り組み,その航行,積荷の保全等に従事する者)が24日と最も長く,職種計では22日となっており,前年と変っていない。
「賃金労働時間制度総合調査」(労働省)により,54年の週休2日制の普及状況をみると,常用労働者数30人以上の規模の企業のうち実施している企業の割合は,調査産業計で全体の46.1%であったのに対し,運輸・通信業では27.3%と低くなっている。
労働時間の短縮は,基本的には週休2日制の普及,有給休暇の取得促進,過重な超過勤務時間の是正等を進めることにあるが,一方で出勤率や能率の向上によって労働生産性の水準を高めるとか,あるいは企業にとっては省力化,合理化投資を促すことになろう。
|