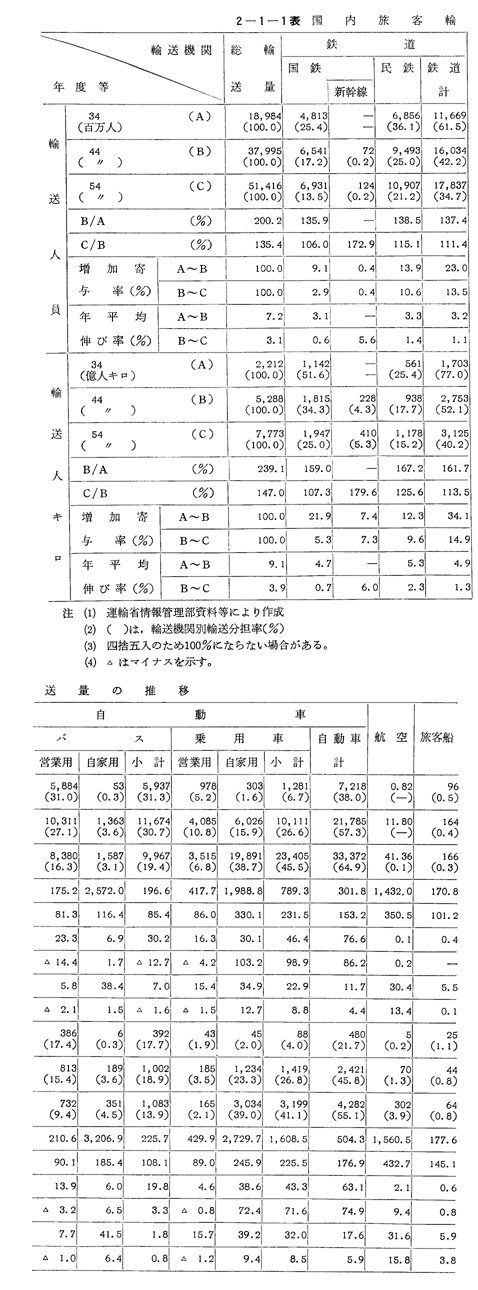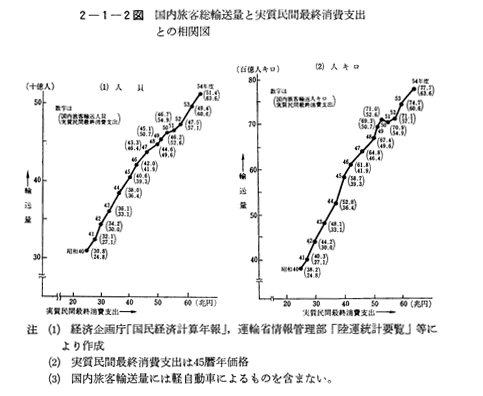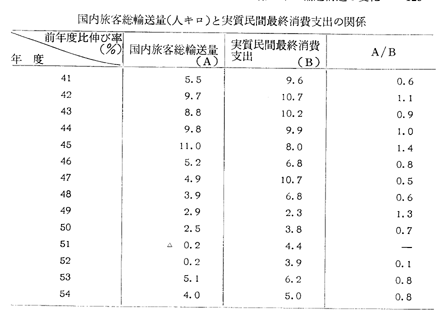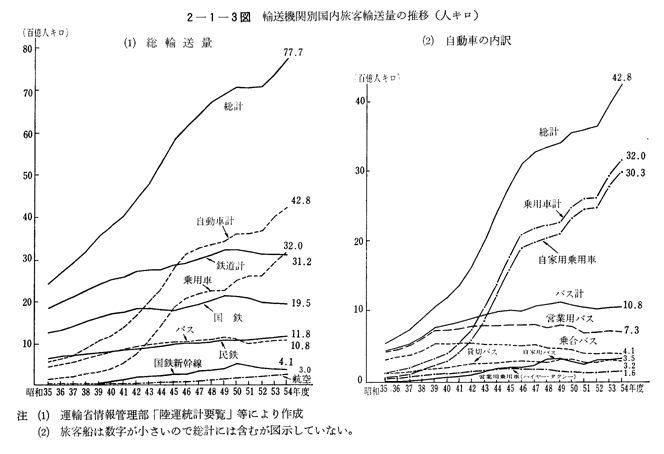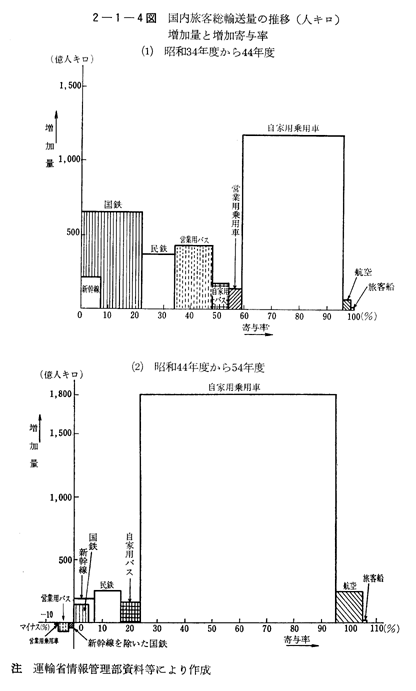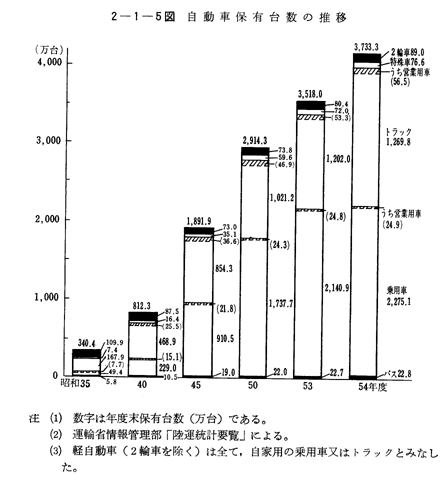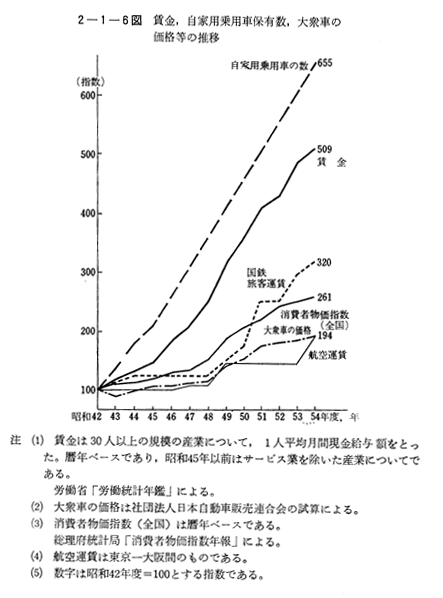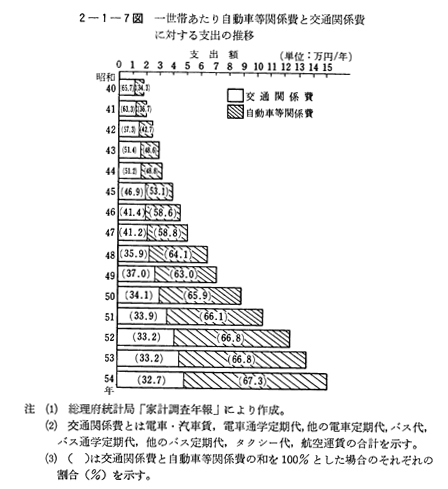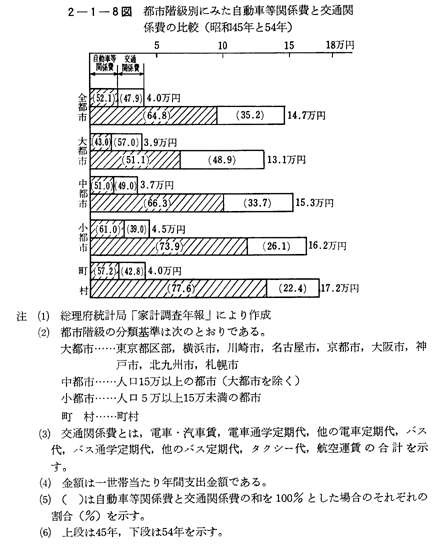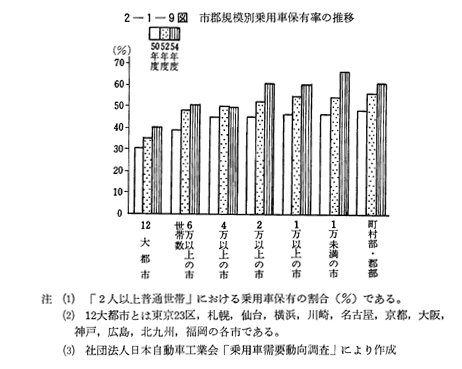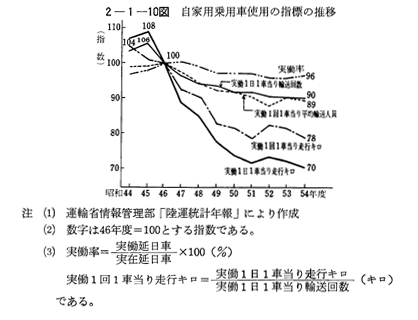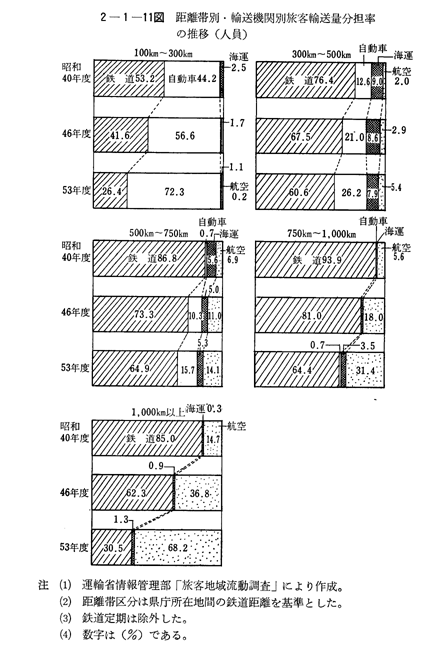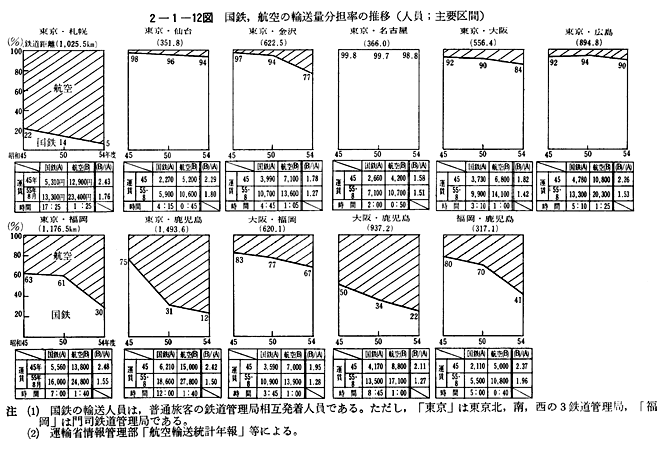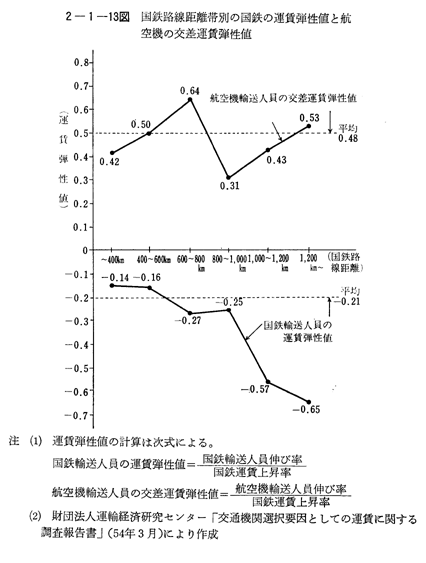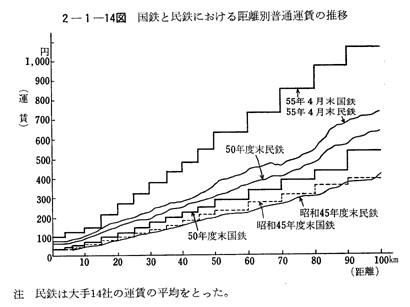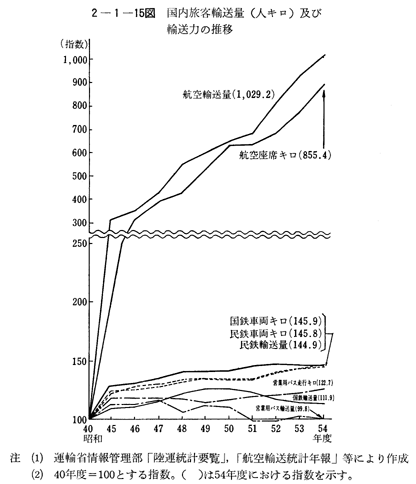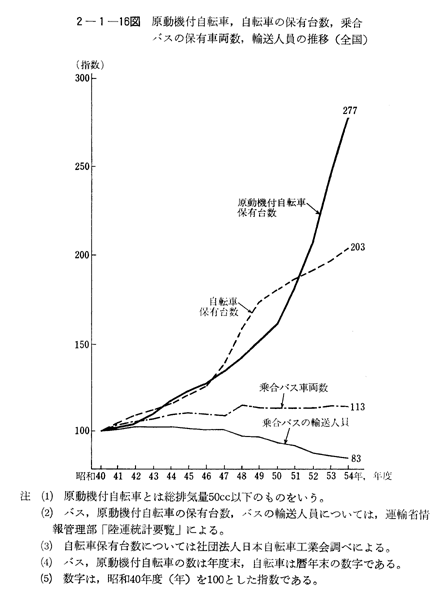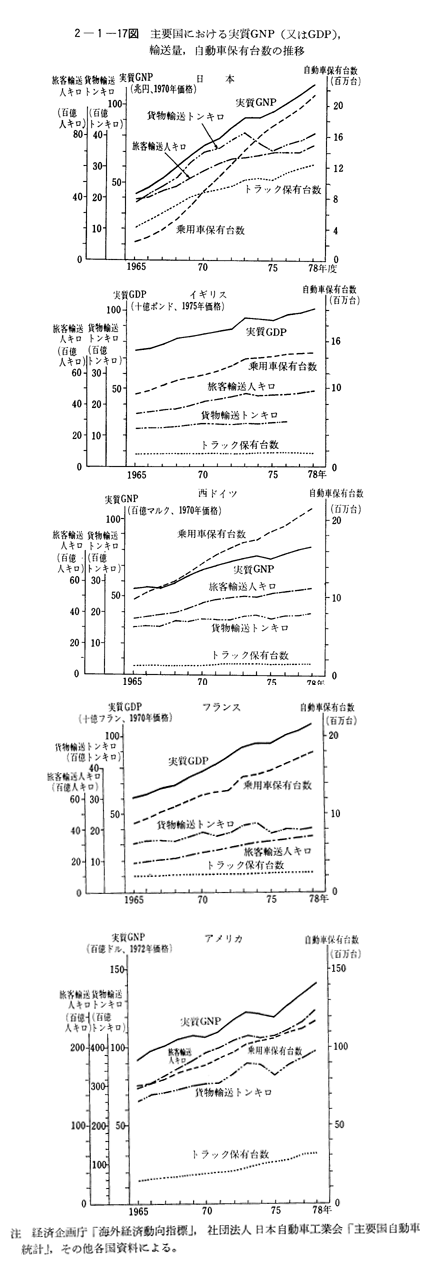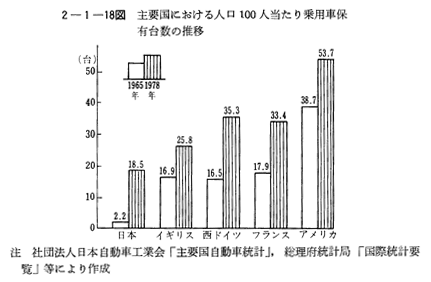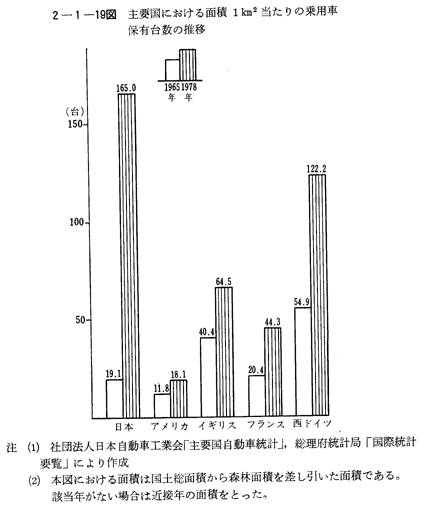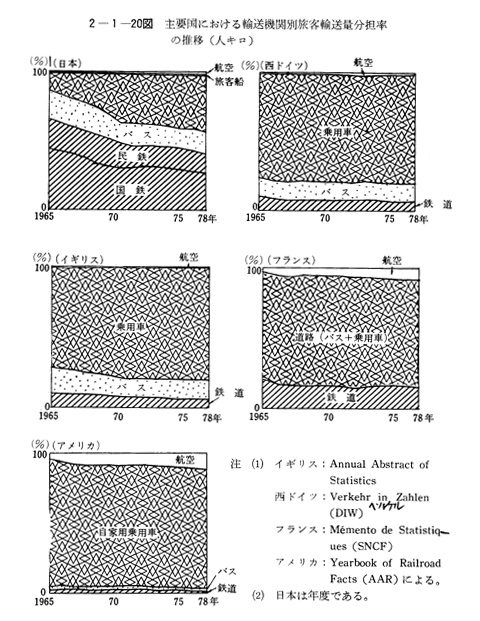|
1 国内輸送
(1) 輸送需要の動向
1970年代の国内旅客輸送は,昭和48年の第1次石油危機を契機とする経済不況,消費者物価の高騰,家計の実質所得の停滞等経済と生活環境の悪化の中に,大きく停滞し,その後安定経済成長への移行に伴い,53,54年度と回復の途を歩んでいるものの量的拡大のテンポは鈍化している。 〔2−1−1表〕のとおり,1960年代においては,国内旅客総輸送量は輸送人員,輸送人キロとも2倍強になったのに対し,70年代は,輸送人員は約1.4倍,輸送人キロは約1.5倍の拡大であった。
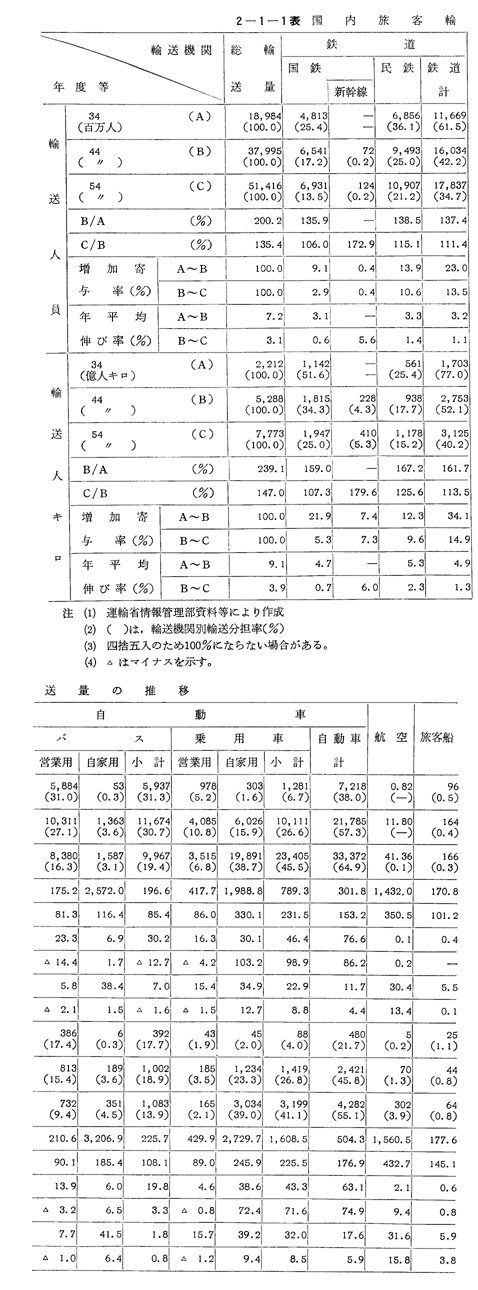
70年代の輸送動向は,昭和48年の第1次石油危機を境いに分かれるが,44〜48年度の年平均伸び率が輸送人員4.1%,輸送人キロ6.2%であったのに対し,48〜54年度は輸送人員,輸送人キロとも2.4%と伸び率が下り,特に,51年度は戦後,統計が整備されて以来初めて輸送人キロの対前年度比がマイナスとなった。しかし,第1次石油危機後の景気回復と物価安定を主軸にした経済政策が次第に効果をあげ,53年末からの第2次石油危機による物価上昇等国民生活への影響はあったものの,個人消費は底堅く,国内旅客総輸送量は,53,54年度と輸送人キロで前年度比5.1%,4.0%とそれぞれ伸びてきている。国内旅客総輸送量(人キロ)と実質民間最終消費支出との関係をみると, 〔2−1−2図〕のとおり,51,52年度と実質民間最終消費支出の伸びに対し,輸送量は横ばいとなったが,53,54年度と国内旅客総輸送量の実質民間最終消費支出に対する弾性値はいずれも0.8で,両者の伸びの関連が密接となってきている。
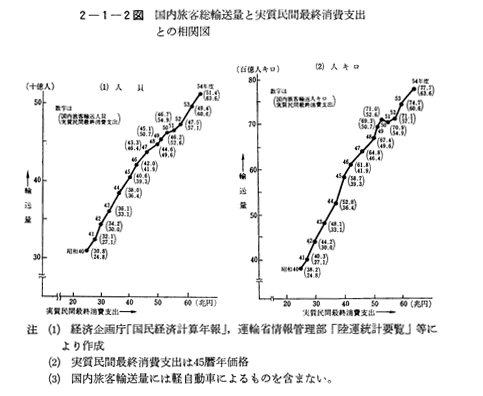
1970年代における各輸送機関の輸送量(人キロ)の増減をみると 〔2−1−3図〕のとおり,航空約4.3倍,乗用車約2.3倍,旅客船約1.5倍,民鉄約1.3倍,バス8.1%増,国鉄7.3%増となっているが,営業用バスとハイヤー・タクシーはいずれもおおよそ10%減少している。70年代の国内旅客総輸送量は,モータリゼーションの急速な進展の中心となっている自家用乗用車の輸送量とほとんどパラレルに増加しており, 〔2−1−4図〕のとおり,自家用乗用車の国内旅客総輸送量に対する増加寄与率は60年代の38.6%から72.4%に増え,その増加に最も大きな影響を与えている。
また,70年代においては民鉄が9.6%,航空9.4%,国鉄5.3%とそれぞれ国内旅客総輸送量の増加に寄与しているが,60年代に比べ増加寄与率は,航空が大幅に増え,国鉄と民鉄が減少し,バス,タクシー・ハイヤーがマイナスとなっているのが目立っている。
このような国内旅客輸送の量的拡大とともに,国民生活の向上を背景に輸送構造の変化が進んだ。
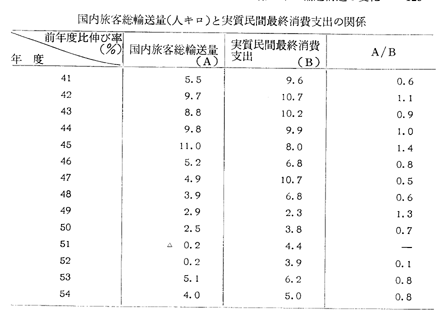
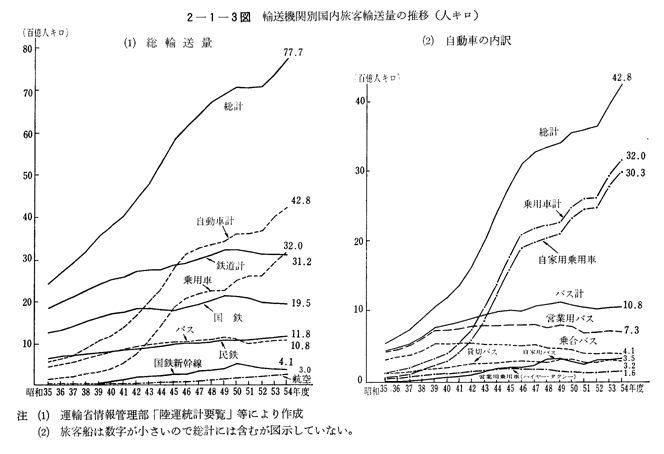
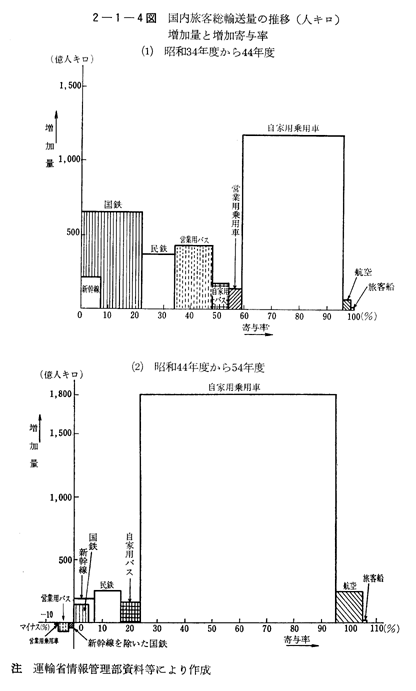
(2) 国民生活の向上と輸送構造の変化
70年代においては,国民の生活水準の向上と生活意識の変化を大きな要因として,国民全体のモビリティが一層増大したが,このために,自家用乗用車と高速道路,新幹線,航空等は重要な役割を果した。一方,特に地方においては,自家用乗用車を利用できる者と利用できない者のモビリティ格差が,公共交通の後退と関連し大きな問題となった。
70年代に入って国民の生活水準は,量的拡大から質的向上に向っており,生活意識も多様化し,物やサービスに対する高度化志向といった変化が目立ってきた。この10年間に国民1人当たりの所得は約3.8倍,190万円(昭和54年)に達し,欧米諸国の水準に仲間入りした。また,勤労者1人当たりの労働時間は,44〜54年の間に月間7%短縮され,大企業を中心に週休2日制が採用される等,欧米諸国に比べるとまだまだ働き過ぎるといわれるものの,国民の生活時間における自由時間の配分が高まり,余暇が増大している。生活意識の面からも,物の購入を重視した生活態度から,レジャー・レクリエーションを積極的に楽しみ,余暇生活を充実させる志向が強まり,しかも,より高級な物や質の高いサービスを個人の好みに応じて選択する傾向にある。
こうした国民の生活水準の向上,余暇の増大や生活意識の変化を背景として,国民の観光旅行は,飛躍的に増加してきた。しかも,1970年代を通じてその内容にも,団体旅行から家族旅行への変化,旅行目的の多様化,利用交通機関としての自家用乗用車の急増,画一的な旅行から個性的な旅行を求めるようになったこと等の変化がみられる。
旅行その他いろいろな目的の移動のための輸送機関の選択についても,経費の面からだけでなく,いかに速く,快適に,しかも徒歩が少なく目的地に到達できるか,といった輸送サービスの質の面が大きな要素となっている。快適に,いつでも機動的に,戸口から戸口に到達できる私的交通機関としての自家用乗用車や都市間,地域間の交通時間を著しく短縮した航空,新幹線への利用者の選択性向が高まり,この10年間に,輸送構造は大きく変化した。
その第1は,急速なモータリゼーションの進展に伴う全国的な自家用乗用車の普及である。自動車の国内旅客総輸送量(人キロ)に占める分担率は昭和44年度45.8%であったが,46年度50%を超えて鉄道をしのぎ,54年度55.1%に増加し,特に自家用乗用車の分担率は54年度39.0%に達している。 〔2−1−5図〕は自動車保有台数の推移を示したものである。自家用乗用車は,この10年間に約3.2倍に増加し54年度末2,250万2,000台となり,総自動車保有台数(3,733万3,000台)の60.3%を占め,国民約5人に1台当たりの普及となっている。このように自家用乗用車の普及が急速に進んだ理由としては, 〔2−1−6図〕のとおり,所得の向上により自家用乗用車の相対価格が低下し,その購入,維持が容易になったこと,快適性,機動性,随意性等において鉄道,バス等公共交通機関にない長所をもつこと,自家用乗用車を所有することは行動範囲を拡大し生活上便利であること,大都市のみならず地方においても都市化が進み生活が広域化したこと,道路整備が進んだこと,運転免許人口が急速に増加したこと等があげられる。
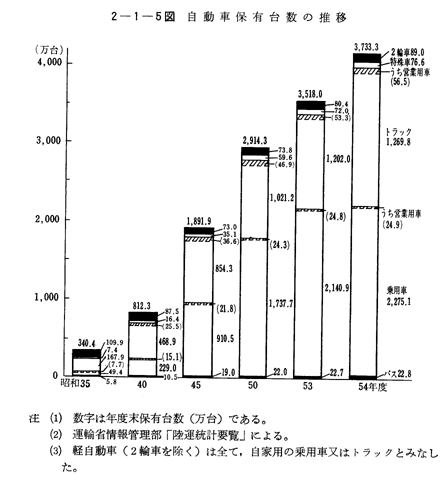
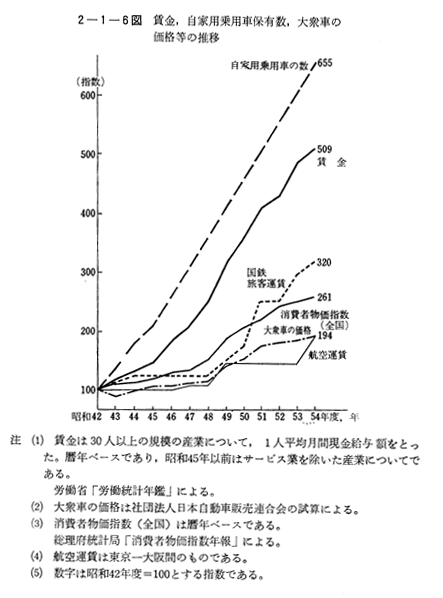
自動車運転免許人口は,54年6月で4,000万人の大台を超え,54年12月末現在,免許適令人口(16才以上)に占める免許所有者の割合は,男が約1.4人,女が約3.8人,全体で約2.1人に1人となっている。また, 〔2−1−7図〕は家計に占める1年間の鉄道,バス等交通関係費と自動車等関係費の推移をみたものである。45年から54年にかけて鉄道,バス等交通関係費は約2.6倍に伸びたのに対し,自動車等関係費は約4.8倍に伸びており,この傾向は 〔2−1−8図〕のとおり,大都市よりも小都市,町村部において著しい。これは, 〔2−1−9図〕のとおり,小都市,町村部における自家用乗用車の普及が,大都市よりもここ数年著しく進行していることを裏付けるものといえよう。
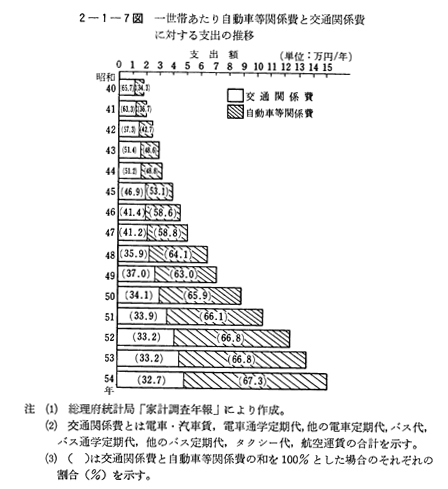
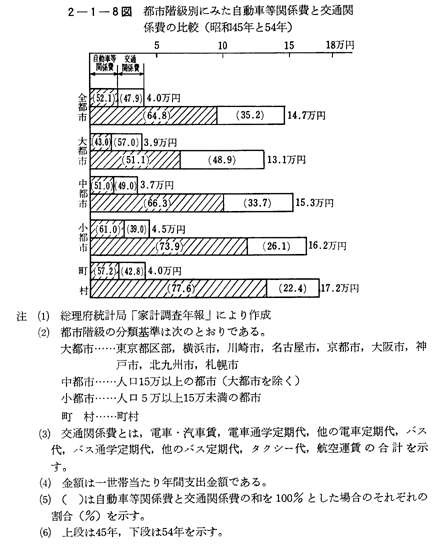
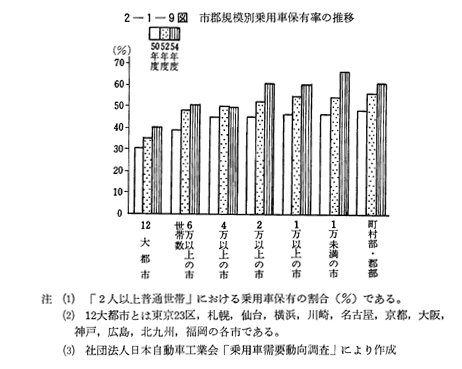
なお,この自家用乗用車の保有台数の年平均伸び率は44年度末から48年度末,48年度末から52年度末の4年間,52年度末から54年度末の2年間で比較すると,それぞれ21.0%,11.1%,5.6%と急速に低下して来ている。また,自家用乗用車使用の指標の推移をみると, 〔2−1−10図〕のとおり,実働率,走行キロ,輸送回数,輸送人員とも45年度頃から低下する傾向にあり,特に実働1日1車当り走行キロは,54年度では46年度に比べおおよそ30%も減少している。
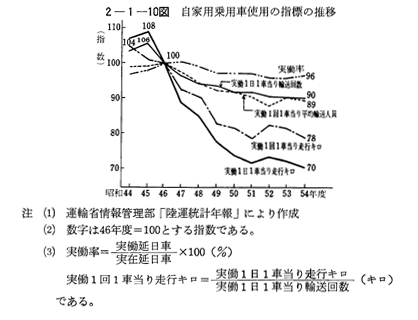
しかしながら,国内旅客総輸送量の増大の原動力となっている自家用乗用車の輸送量の伸び率は,46年度以降52年度まで増勢を弱めたものの,53,54年度と前年度比で12.5%,8.3%と伸びを回復しており,今後とも国内旅客総輸送量の増加に,自家用乗用車の保有の増加,利用の程度如何が大きな影響を与えることとなろう。一方,自家用乗用車の急速な普及により,都市では交通混雑を生じ,乗合バス,路面電車の運行効率が低下するとともに,事故,公害が問題となり,また,地方では過疎化とも相まって,国鉄,地方中小民鉄,乗合バス等公共交通機関の輸送需要の低下のため,経営が困難な路線が増加するとともに,それらを廃止,縮小せざるを得ない状況が続いている。
こうしたことから,地方ではシビルミニマムとしての公共交通の確保が大きな問題となっている。
輸送構造の変化の第2は,鉄道輸送量の減少である。国内旅客総輸送量に占める各輸送機関の分担率の推移をみると, 〔2−1−1表〕, 〔2−1−3図〕のとおり,鉄道は人キロで44年度52.1%を占めていたが,54年度には40.2%に減少し,34年度の分担率の半分近くに低下した。このうち,国鉄は49年度をピークに連続して輸送量が減少し,輸送分担率(人キロ)は,49年度31.1%から54年度25.0%に低下した。50年3月に博多まで開通した新幹線も50年度をピークに輸送量は減少し,分担率は50年度7.5%から54年度5.3%に低下している。
また,国鉄は 〔2−1−11図〕のとおり,すべての距離帯にわたって,その分担率を低下させてきている。500キロメートル以下,特に100キロメートル〜300キロメートルの近距離においては,自動車の進出が目立つ。500キロメートル以上の中・長距離においては航空の進出がめざましく,例えば,主要区間における国鉄と航空の分担率の推移をみても 〔2−1−12図〕のとおり,国鉄は,新幹線区間についてみると優位に立っている区間が多いが,「東京-福岡」間では航空のシェアが大きい。また,「東京-鹿児島」,「東京-札幌」等の区間では,航空が優位に立っている。
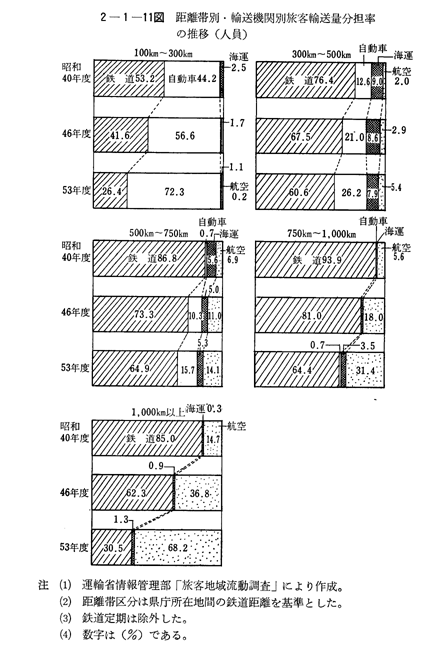
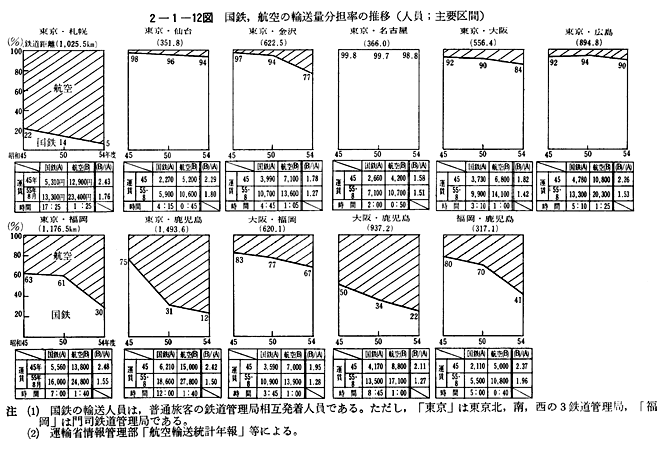
こうした長距離・海越え及び山岳越え輸送における国鉄の比重の低下は,高速性に優れた航空の競争力強化(大型機の導入やジェット機就航路線・空港の整備,更に生産性の向上により運賃引上げ率が小幅であったこと等)が影響し,航空への需要のシフトが起っているためと考えられる。
加えて,国鉄は,51年11月の運賃改定(改定率50.4%)等の一連の運賃改定により,価格競争力を低下させたことが指摘される。
例えば, 〔2−1−13図〕は51年11月の国鉄の運賃改定の影響をみるため,51年第1四半期(運賃改定前)と52年第1四半期(運賃改定後)の2時点で,国鉄と航空が競合している区間の往復輸送人員の増減量により,運賃弾性値を試算したものである。試算時点での国鉄と航空の輸送人員の増減を前提とすると,国鉄運賃が10%アップすると国鉄の輸送量は2.1%減少し,逆に航空は4.8%増加することになる。
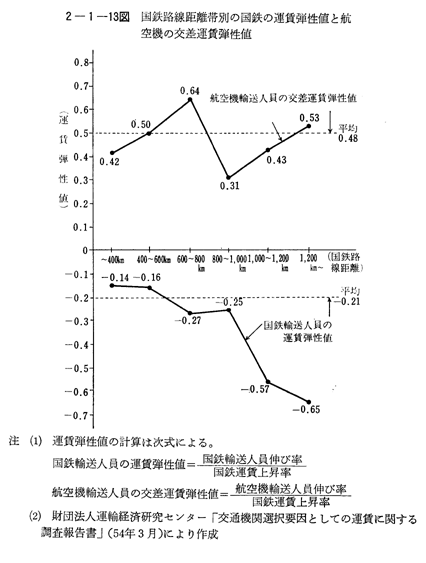
また,都市圏の通勤・通学輸送を分担する大手民鉄と運賃を比較しても 〔2−1−14図〕のとおり,45年度末に比べ55年4月末では全距離帯にわたり国鉄が高くなった。このように,国鉄の価格競争力の低下は輸送量減少の一因となっている。
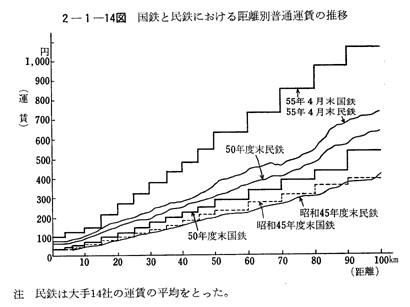
更に, 〔2−1−15図〕のとおり,航空,民鉄に比べ,国鉄は営業用バスと同様,輸送力と輸送量の乖離が年々拡大しつつあることも大きな問題である。
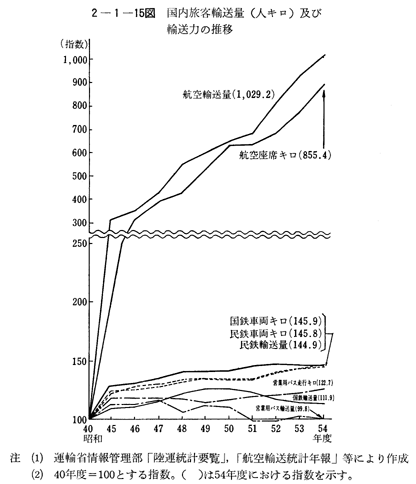
次いで,民鉄は,大都市圏における通勤・通学輸送を主体とした輸送需要の増大により,人キロでみるとここ10年,年平均2.3%の率で輸送量を伸ばしてきているが,国内旅客総輸送量に占める分担率は44年度17.7%から54年度15.2%に低下した。
第3は,利用者のいわゆる「バス離れ」の進行である。バスの国内旅客総輸送量(人キロ)に占める分担率は,44年度18.9%から54年度13.9%に低下した。特に,営業用バスは,54年度9.4%に減少し,34年度の17.4%に比べるとほぼ半減した。そのうち,鉄道の代替的・補完的な,ないし地方によっては唯一の公共交通機関である乗合バスは,輸送人員では43年度,輸送人キロでは47年度をピークに減少傾向が続いている。
これは,都市においては,過密化の進行,モータリゼーションの進展による道路交通混雑の激化等交通環境の悪化のため,乗合バスの走行速度が低下するとともに定時性の確保が困難となり,バスに対する信頼性低下による利用者のバス離れが進んだためである。加えて,市街地の外延化が急速に進み,需要が分散したために,走行キロ当りの輸送人員の低下傾向が続く一方で,人件費,燃料費等諸経費の高騰もあり,バス事業の経営は悪化の一途をたどっている。このため,バス輸送サービス改善の立ち遅れを招くとともに経営改善を図るための運賃改定とあわせて,自家用乗用車等への利用者のバス離れが一層進むという悪循環を繰り返している。また,地方においても,人口の流出による過疎化の進行に加え,都市に比べ公共交通機関のサービス水準が低いため,モータリゼーションの進展が都市以上に進行し,バス等の輸送需要が大幅に減少したことがあげられる。
第4は,航空の著しい発達である。航空の国内旅客総輸送量に占める輸送分担率(人キロ)は34年度0.2%,44年度1.3%,54年度3.9%と着実に拡大してきている。輸送量は,この10年間に約4.3倍(年平均伸び率15.8%)と驚異的に増大し,54年度は302億人キロになった。54年度の輸送人員は4,136万人で,1年間に国民のうちおおむね5人に2人は航空機を利用している計算になり,長距離輸送の分野では,最も便利な輸送機関としてますます国民生活への定着が進んでいる。最近の輸送状況をみると,49年度,50年度と前年度比伸び率は,48年の第1次石油危機後の不況,山陽新幹線の開業等の影響により鈍化したが,その後は再び増勢を強めしかも近距離区間よりも中・長距離の利用者が増加し,特に51年11月の国鉄運賃改定後は,観光客等のレジャー客を中心に再び年平均伸び率で13.1%(52年度から54年度)と上向きとなった。
航空が,このように著しい発達をみた原因ないし背景として次のように考えられる。まず,利用者サイドにおいては,生活水準の向上による輸送サービスの高度化指向,時間価値の上昇による旅行時間短縮効果の大きい高速輸送機関の選好性の増大,所得水準の上昇による航空運賃の相対的割安感と国鉄運賃との運賃格差の縮小等が考えられる。また,供給サイドにおいては,機材の大型化等効率化・合理化の促進により長期間据置き後の運賃の引上げ率が比較的小幅にとどまったことや,安全性,定時性の確保や増便によるサービス水準の向上,地方空港のジェット化,航空路線網の拡充等があげられる。
その他,1970年代の輸送について特記すべき動向として, 〔2−1−16図〕のとおり自転車,バイクの著しい増加がある。健康づくり,環境重視のバイコロジー運動を背景に,手軽にしかも低廉に利用できる自転車は,48年頃から全国的に急速に増え,54年末で自転車は約5,000万台(44年に比べ約1.8倍)に,また,運転操作が簡単で価格的にも手頃なバイクは,54年度末約880万台(44年度に比べ約2.4倍)に達している。これらは,鉄道駅,バス停留所へのアクセスとして,通勤,通学,買物や業務等のために広く利用されており,国民の日常生活のためのモビリティ向上に貢献している。しかし反面,無責任な放置による駅周辺の交通混雑や美観上の問題,交通事故の増加等の問題が生じており,また,乗合バスに対しては,自転車利用の増加による利用客の減少といった少なからぬ影響を与えている。
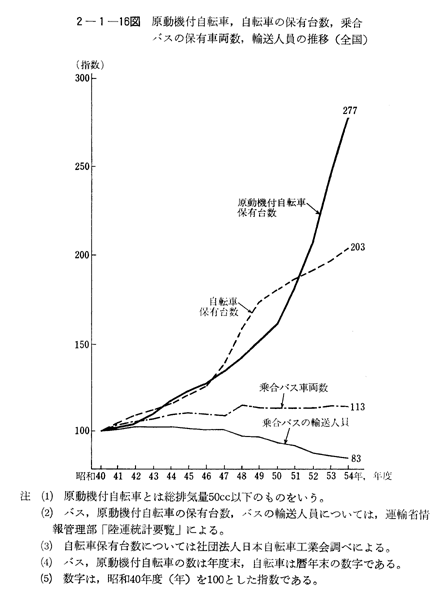
(3) 我が国の輸送構造の特色
〔2−1−17図〕は,我が国,イギリス,西ドイツ,フランス,アメリカの実質GNP(又はGDP),輸送量,自動車保有台数の推移を示したものである。まず,旅客輸送量をみると,各国の地形や地勢,面積,産業や都市の配置等の違いもあり,一律の比較は困難であるが,輸送人キロで1978年では,我が国は7,475億人キロと西ドイツ(5,594億人キロ)を超え,イギリス4,836億人キロ,フランス3,460億人キロに比べおよそ1.5〜2倍程度であり,アメリカの24,819億人キロに比べおよそ1/3程度である。また,65年から78年までの輸送人キロの伸び率をみると,我が国は約2倍になっているのに対し,イギリス約1.5倍,フランス約1.9倍,アメリカ約1.7倍,西ドイツ約1.5倍程度となっており,我が国の旅客輸送が欧米諸国よりも大きく伸びたことが分る。また,乗用車保有台数においても,各国とも実質GNP(又はGDP)以上の増加をみているものの,特に我が国が約9.6倍と高く,今や世界第2位の自動車保有国となり,いかにモータリゼーションが急速であったかを示しているといえよう。また, 〔2−1−18図〕は1人当たり乗用車保有台数を比較したものであるが,これによれば我が国は国際的にみて欧米諸国の保有水準に到達しつつあり, 〔2−1−19図〕のとおり,国土総面積から森林面積を控除した面積当りでは,欧米諸国よりはるかに高い保有台数となっている。
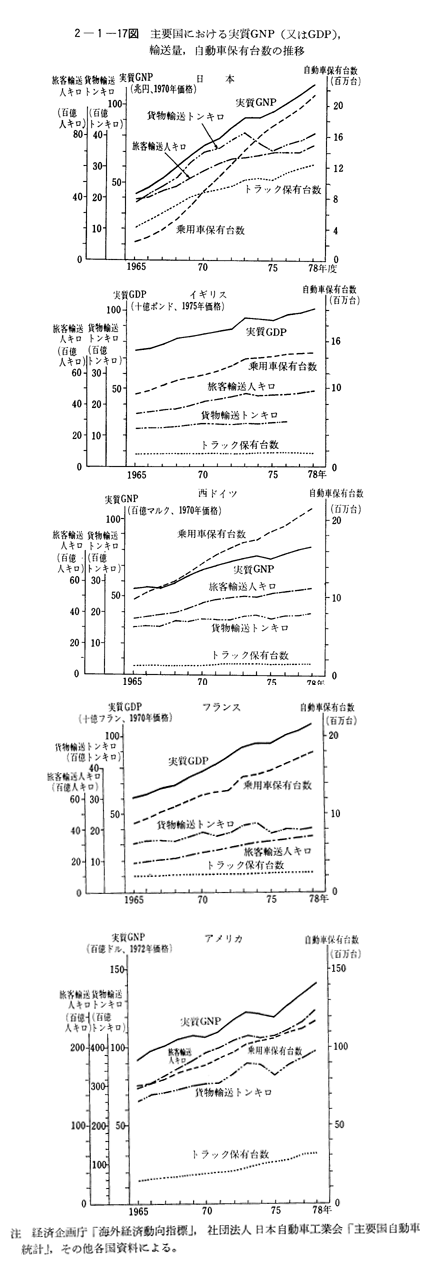
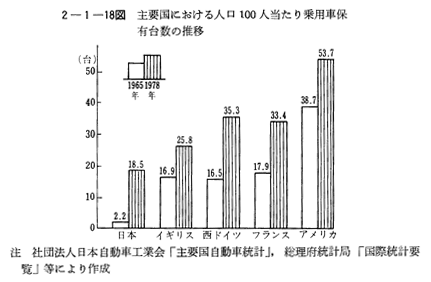
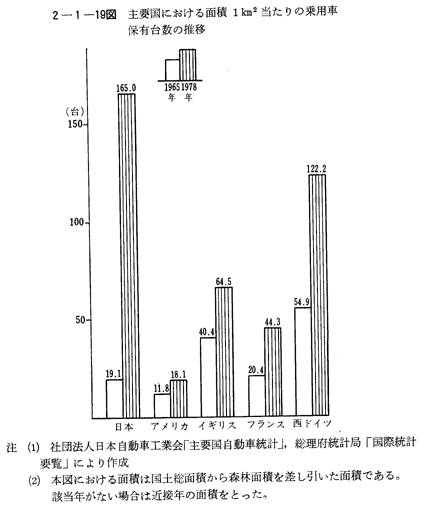
〔2−1−20図〕は,輸送機関別旅客輸送分担率(人キロ)の推移をみたものである。我が国は,欧米諸国に比べ,急速なモータリゼーションの進展にもかかわらず,大都市圏や主要幹線沿いの鉄道旅客需要が多いため,なお鉄道の分担率が高く,バスを含めると公共交通機関の比重が非常に大きい。これに対し,欧米諸国では,65〜78年の間に乗用車は高水準に普及し,航空,鉄道,バス等公共交通機関との輸送分担も大きく変化する状況にはないと考えられる。アメリカでは乗用車と航空中心であり,イギリス,西ドイツ,フランスでは乗用車を主体に鉄道とバスで補完する輸送構造となっている。また,比較的国土の広いフランスでは航空の比重が高まりつつあり,細長い国土をもつ我が国も,同様の傾向を次第に示しつつある。
完全な車社会になっている欧米諸国においては,エネルギー,環境,安全,交通混雑等の面から「自動車交通量を減らし,住み良い街づくりを」(BETTER TOWNS WITH LESS TRAFFIC)を実現するために,自家用乗用車の都心部乗り入れ制限,歩行者道路の拡大,公共交通機関の利便の増大等,自動車交通対策が交通政策の最重点課題として展開されている。
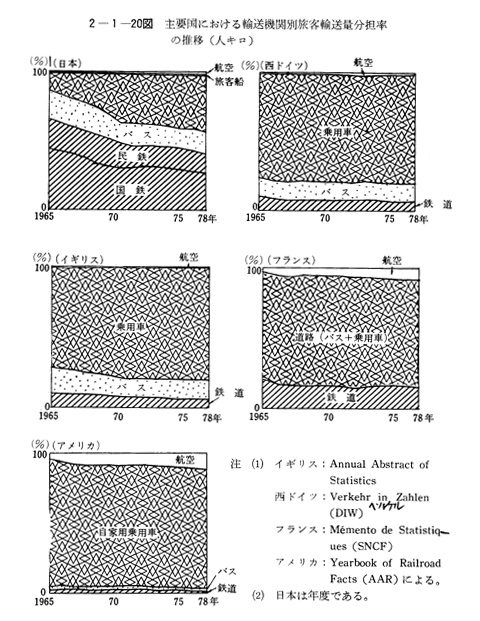
我が国においても,自家用乗用車が国民のモビリティを高め,日常生活,レジャー等のために便利な輸送手段として国民に定着しているが,一方,事故,公害,交通混雑等自家用乗用車のもたらす弊害の是正,省エネルギーの推進,シビルミニマムとしての公共輸送の確保が,国民生活,国民経済にとって重要な課題となっている。このため,公共交通機関と自家用乗用車の適切な輸送分担,そしてその対策について,地域の事情を踏まえ,地域全体のモビリティが向上し,自家用乗用車を利用できる者と利用できない者とのモビリティ格差が改善される方向で検討する必要があろう。
|