|
1 国鉄をめぐる輸送需要の推移国鉄は,昭和24年に公共企業体として発足して以来,基幹的輸送機関として我が国経済の復興と高度成長に大きな役割を果たしてきた。30年代前半においては,経済の高度成長に伴い,国鉄の輸送量は旅客,貨物とも順調に伸び,後半においては貨物は伸び悩んだものの旅客については引き続き順調な伸びを示した。このため,30年代を通じて,幹線系における輸送力のひっ迫をいかに打開するかが問題となり,東海道新幹線をはじめとして主要幹線と大都市交通線における輸送力の整備増強に全力を挙げた。 一方,我が国の輸送構造は,戦後期から復興期に至る鉄道依存型の交通体系の時代から,高度成長期を通じ,我が国の経済社会の進展のなかで,資源の海外依存,臨海型の産業立地,石炭から石油へのエネルギー変革等の産業構造の変化及び自動車輸送や航空輸送等他の輸送機関の急速な発展により,多様な輸送機関が相互に競争する時代へと変化していった。こうした事情は,40年代に入り国鉄の輸送動向に顕著な影響を与えるようになった。 まず,貨物輸送については,国内貨物総輸送量が年々増加するなかで,国鉄の輸送量は30年代後半から40年代前半において550〜600億トンキロで横ばい傾向となり,国内貨物総輸送量(トンキロ)に占めるシェアは,35年度約39%から45年度約18%へと半減するに至った。更に,40年代後半以降,ストライキによる荷主の信頼の低下等の影響も加わり,45年度624億トンキロをピークとして減少傾向へと転じた。近年に至りようやくこの減少傾向が緩み,400億トンキロ強で停滞しているが,そのシェアは10%を割り込むまでに至っている。 次に,旅客輸送については,49年度2,156億人キロまで伸びたものの,その伸びは国内旅客総輸送量の伸びに比し相対的に低いものにとどまり,50年度以降減少傾向へと転じ,近年においては2,000億人キロを下まわっている。この間,国鉄の輸送量のシェアは,35年度51%であったものが45年度32%,54年度には25%へと低下した。国鉄旅客のうち,定期旅客は42年度848億人キロをピークに減少傾向を示し,40年代後半以降は横ばいないし微増傾向を続けている。また,普通旅客については,高度成長に伴う高速化指向から優等列車に対する需要は比較的順調な伸びを示してきたが,全体としてはその伸びがやや鈍化し,50年代に入ると,石油危機後の国内旅客総輸送量の全般的な伸びの停滞に加え,航空輸送等他の輸送機関との競争の激化等により減少傾向に転じ,54年度の普通旅客輸送量は1,159億人キロとピーク時の50年度1,393億人キロに比べて17%減となっている 〔2−2−1図〕, 〔2−2−2図〕。
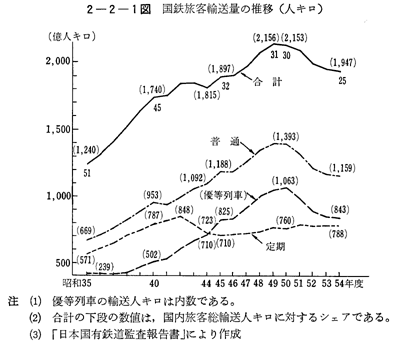
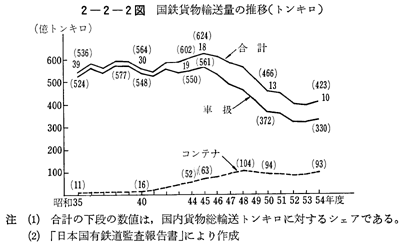
また,地方交通線の輸送量は,その減少傾向が著しく,40年代以降モータリゼーションの進展等に伴い引き続き減少を続け,54年度の輸送量は44年度と比べると,旅客は25%減,貨物は61%減という状況となっている 〔2−2−3図〕。
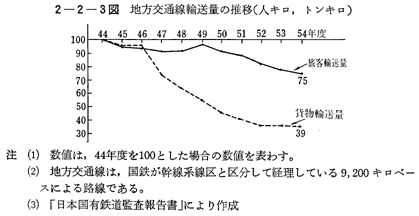
|