|
3 1980年代に持ち越された隘路打開
以上,70年代における航空輸送需要の急増への対応について,空港整備と新機材の投入による輸送力の増強とを二本の柱として,その概要をふり返って見た。いずれの分野においても,相当以上に精力的な努力が行われてきたことは数字の上からも明らかであるが,供給面とりわけ空港整備面における隘路は,今日なお大きく残されており,そのため,航空に対する国民の期待が十分満たされているとはいえない状況である。
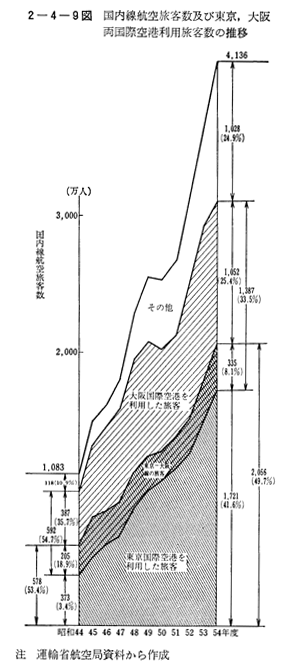
〔2−4−10図〕は,ここ10年の両空港の国内線発着回数の推移を示したものである。両空港とも,発着旅客数の急増にもかかわらず,空港能力や騒音問題の制約により,航空機の発着回数は頭打ちとなり,大阪ではむしろ減少している。このギャップは,これまでのところ,新機材の導入等による輸送力の増強によって埋められてきたが,このような対応も既に限界に達してきている。
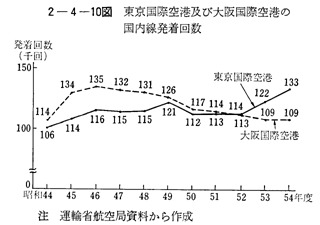
また,ジェット化の現況を空港数,路線数,旅客数の三点から見たのが 〔2−4−11図〕である。全旅客の80%以上がジェット機を利用している一方で,ジェット化空港,ジェット化路線は全体の半分に満たない姿となっている。実際,ジェット機の就航には2,000メートル級,国内線大型ジェット機の就航には2,500メートル級の滑走路が必要であるが,現在の我が国空港の平均滑走路長は1,810メートルに過ぎず,未だその平均水準はジェット機の就航可能な水準に到達していない。こうした制約等から,輸送力の増強に極めて有効なジェット化路線の設定も,足踏みを強いられざるを得ない状況である。
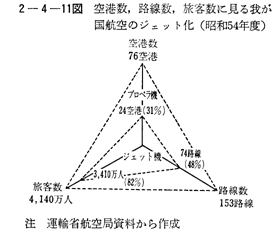
一方,国際航空については,今後我が国が諸外国との交流を一層進めて行く上で,空の玄関の間口は十分広いものであることがのぞまれようが,開港以来1本の滑走路で運営されている新東京国際空港,新規乗入れや増便はほとんど不可能な事情にある大阪国際空港等,現在の空港事情は極めて不満足である。
|