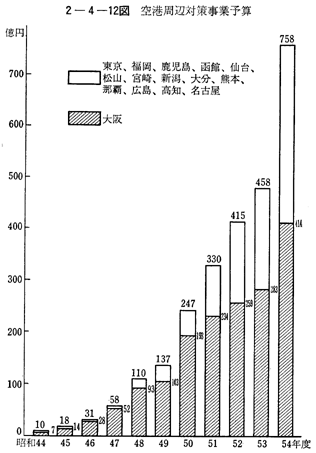|
4 積極化を進めた空港環境対策
この10年間における航空輸送の増大,そしてそれに深く関連するジェット機の運航回数の増加は,国民に対し高速,快適かつ利便に富んだ輸送手段を提供したが,その反面,空港周辺地域の住民に大きな影響を及ぼす航空機騒音問題を引き起こした。
とりわけ,空港周辺の市街化が進んでいた大阪国際及び福岡の両空港については,周辺住民の間に深刻な影響があり,昭和44年から51年にかけて,それぞれの周辺住民から夜間飛行の差止め,損害賠償等を請求内容とする訴訟が提起され,また,大阪国際空港については,48年から51年にかけて,公害等調整委員会に対し,同空港の廃止,損害賠償等を求める調停が申請された。
運輸省においては,30年代後半以降,既に東京及び大阪の両国際空港において,便数及び発着時間を規制し,42年には,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律を制定して,同法に基づき教育施設等防音工事,移転補償等を行う等各種の対策を実施してきていた。
48年,環境庁は,公害対策基本法に基づき,航空機騒音に係る環境基準(専ら住居の用に供される地域にあっては70WECPNL(加重等価平均感覚騒音レベル),その他の通常の生活を保全する必要がある地域については75WECPNL)を示し,その達成については,基準設定日においてジェット化されていない空港については53年末までに,同日においてジェット化されている空港については53年末までの中間改善目標を掲げた上で,最終的には58年末までに(東京国際空港,大阪国際空港及び福岡空港については58年末以降可及的速やかに)達成することとした。
運輸省としては,環境基準の設定を機に,その達成を第一義的行政目標としてより一層の努力を続けることとなった。
空港環境対策は,発生源対策,空港構造の改良,空港周辺対策の3つに大きく分けられる。
発生源対策としては,50年に航空法の改正により航空機の騒音基準適合証明制度を導入し,騒音が一定基準以下でなければ原則として飛行が禁止されることとし,また,従来のジェット機に比べて騒音の低いエア・バスを幹線を中心に就航させるとともに,急上昇方式,ディレイドフラップ方式,カットバック方式,優先滑走路方式等の運航方式の改善,前述の便数・発着時間の規制を実施してきた。
空港構造の改良としては,空港の拡張に当たって滑走路の方向,位置等を変更して人家密集地の上空をなるべく航空機が飛行しないようにしたり,空港そのものを海上に造る(46年設置の大分空港及び50年設置の長崎空港)等の措置を実施してきた。
空港周辺対策としては,42年制定の前記法律に基づき,教育施設等防音工事及び共同利用施設整備の助成並びに移転補償を実施してきたが,49年の同法改正により民家防音工事助成及び緩衝緑地造成を追加し,以後逐次,制度拡充を行い,特に54年度からいわゆる全室防音に取り組む等これらの周辺対策を推進してきた。民家防音工事については延べ4万世帯余について実施している。特に,空港周辺の市街化が進んでいる大阪国際,福岡の両空港については,49年の同法改正によりそれぞれ空港周辺整備機構を設立して,空港と調和のとれた周辺地域整備を推進している。
また,53年には,特定空港の周辺地域(航空機騒音障害防止地区)内における住宅等の建築制限,これに伴う損失補償等について定める特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法が制定され,現在,新東京国際空港が特定空港として指定されている。
これらの空港周辺対策の推進を予算面からみれば, 〔2−4−12図〕のとおり,44年度の10億円から54年度の758億円に飛躍的に増加し,54年度には空港整備特別会計予算の38%を占めるに至っている。このうち,特に大阪国際空港の占める比重は高く,44年度から54年度までの環境対策予算額の65%を占めている。このような空港環境対策予算額の増加に応じるための財源として,50年にはジェット機の離着陸に対する特別着陸料制度を設けた。
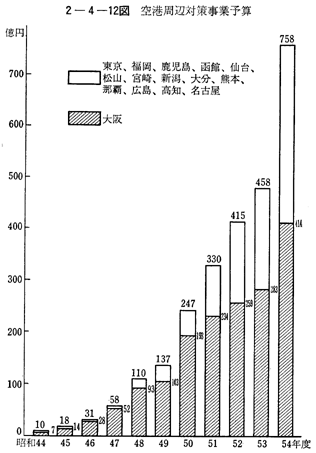
また,空港関係地方公共団体の行う空港対策に充てうる自主財源を強化するために,47年度から関係市町村に対する航空機燃料譲与税を発足させるとともに,54年度からはこの航空機燃料譲与税を関係都道府県に対しても譲与することとし,54年度の譲与税額は総額で90億円となっている。
これらの諸対策の推進により,53年末には前記環境基準の中間改善目標がおおむね達成されるに至った。54年以後も,最終改善目標の達成をめざし鋭意努力が続けられている。
|