|
1 世界経済の概況世界経済は,再び石油危機の厳しい試練にさらされた。第1次石油危機の後遺症から脱し,新たな成長軌道に乗りつつあった世界経済は,1980年に入り,78年以来の段階的かつ大幅な石油価格上昇,いわゆる第2次石油危機の波紋が広範化する中で漸次後退色を深め,各国は経済パフォーマンスの悪化に苦悩した。 世界のGNPの約6割を占める先進国経済は79年中かなりの成長を維持したが,80年に入り石油価格高騰に伴うデフレ効果と引締め政策による相乗的影響から,景気は停滞局面に入った 〔1−1−1図〕。発展途上国では二極化がみられる。すなわち,産油国が石油収入に潤い,総じて順調な景気拡大を続けた一方で,非産油国経済は,第2次石油危機の直接的影響に加え,先進国経済の景気停滞に伴う輸出の伸び悩み等から成長鈍化,インフレ悪化,経常収支赤字の拡大という三重苦(トリレンマ)に陥った。
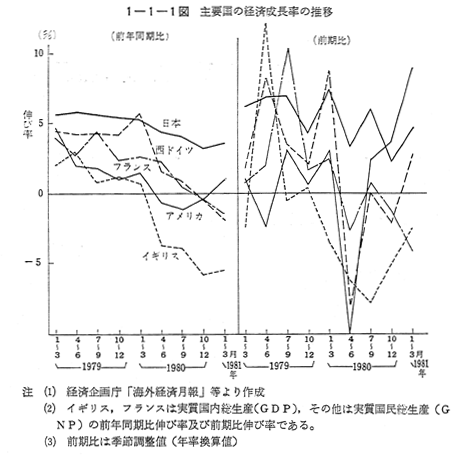
先進主要国の動きを追ってみよう。79年中実質所得の伸び悩みにもかかわらず景気後退を免れたアメリカ経済は,80年1月をピークとして急速に下降した。すなわち,80年4〜6月期の実質GNP成長率は前期比年率9,9%減と戦後最大の落ち込みをみせ,更に鉱工業生産も2月以降5か月連続して減少した。夏以降,景気は一応上昇軌道に乗ったが,その足どりは極めて緩やかである。西欧では,79年下期に他国に先がけ下降局面に突入したイギリス経済が,春には一段と下降テンポを早めた。また,西ドイツ,フランス等の諸国は80年1〜3月期まで順調に景気拡大を続けたが,4〜6月期には下降に転じ,実質経済成長率は前期比年率で西ドイツが8.0%減,フランスが2.7%減となった。
|