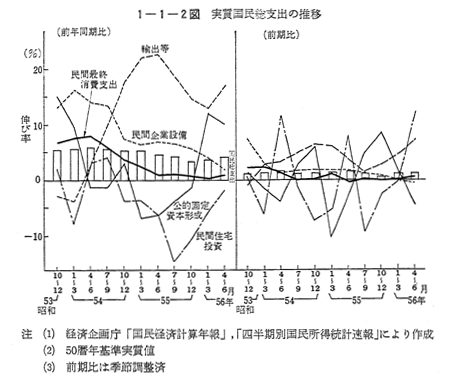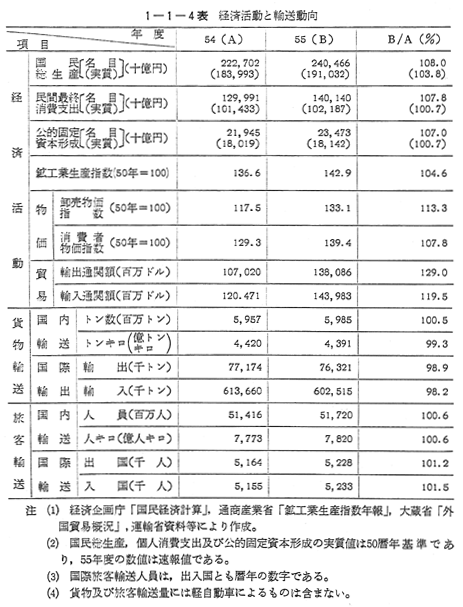|
2 日本経済の概況
第2次石油危機のもたらした厳しい世界経済情勢のなかで,我が国経済は,先進国中最も高い経済成長率を維持するなど比較的良好なパフォーマンスを示した 〔1−1−1図〕。しかし,第2次石油危機の影響に対して厳しい対応を迫られたことは我が国も例外ではない。すなわち,昭和55年度の日本経済は,原油価格の大幅値上げに伴う産油国への大規模な所得移転により,第1次石油危機を上まわる実質所得の停滞が生じ,経済の拡大テンポは鈍化するとともに,最終需要面等で跛行性が目立った。
前年の卸売物価高騰は,55年に入って消費者物価に波及しはじめた。ホーム・メイド・インフレは避けられたが,2月以降,消費者物価は対前年同月比8%台の上昇率をほぼ一貫して続けた。
こうしたなかで,最終需要面では個人消費支出,民間住宅投資,公共投資が停滞する一方で,民間設備投資,輸出は増勢を鈍化させながらも堅調に推移し,景気を支える役割を果した 〔1−1−2図〕。
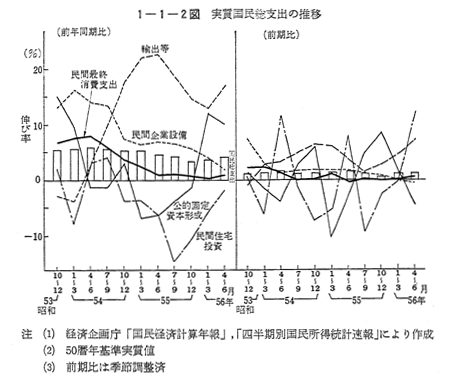
まず,個人消費支出(GNPベース,実質)は,対前年度比0.7%増と54年度の同5.0%増を大きく下まわった。これは,労働分配率がほぼ不変だった結果,デフレ効果が第1次石油危機に比べ,家計部門に,より強く現われたことによる。しかし,前回のような消費性向の急低下が生じなかったことが消費の落ち込みを緩和し,停滞にとどめ得る要因となった。
民間住宅投資は54年度中から既に減少傾向にあったが,55年度には更に落ち込み,対前年度比9.5%減と49年度(同16.3%減)以来の減少を示した。その動向を新設住宅着工戸数でみると,対前年度比18.3%減の121万戸にまで落ち込み,第1次石油危機直後の水準(49年度は126万戸)を下まわった。これには,住宅建設費,土地価格の高騰と実質所得の伸び悩みによる住宅取得能力の低下が影響している。
これに対して民間設備投資は,対前年度比5.8%増と54年度の10.1%増に比べ伸びは鈍化しながらも堅調に推移した。前回の石油危機では設備投資は減少し,景気下降の要因となったが,今回は労働分配率の上昇が企業収益を圧迫するという事態は生じず,設備投資は堅調で景気を支える役割を担った。しかし,産業別,企業規模別には跛行性が目立った。すなわち,非製造業の伸びの鈍化に対し製造業は伸びの高まりを見せたこと,製造業の中でも素材型産業に比し加工型産業の伸びが顕著だったこと,大企業の好調さに対し中小企業は年度後半から停滞したこと等である。
公共投資は54年度に引き続き抑制された。しかし,景気停滞色の浸透に伴い,総合経済対策(55年9月)において執行抑制が解除されたため,下半期には増加に転じた。
次に,輸出入を見ると,輸出(GNPベース,実質,対前年度比17.1%増)は54年度(同12.8%増)を上まわる高い伸びを示した。数量ベースでみても,円高と欧米諸国経済の後退のなかで,7〜9月期以降増勢を鈍化させながらも高水準で推移した 〔1−1−3図〕。その主因は国際競争力の強い機械の高い伸びにある。一方,輸入(数量ベース)は,55年初めに大きく落ち込んだ後,円高と景気停滞という相反する要因からジグザグに推移した 〔1−1−3図〕。

以上のような最終需要の跛行性に呼応して,供給サイドの動きにも跛行性が生じた。すなわち,第1に,大企業の業況が年度後半にかげりをみせながらも全体として好調に推移したのに対し,中小企業は大企業に比し消費財,建設財関連業種の比重が高いため消費の停滞,住宅投資の落ち込みは中小企業の収益悪化を招いた。第2に,産業別にみても,鉄鋼,化学等の素材型産業は在庫調整による生産活動の停滞が目立ったのに対し,機械等の加工型産業では輸出の高い伸びと設備投資の著しい増勢により生産は拡大した。
56年度に入って,我が国経済は第2次石油危機によりもたらされた景気のかげりから次第に脱却しつつある。物価は安定を取り戻し,石油危機による実質所得の停滞も解消するなかで,個人消費,住宅投資にも回復の兆しが見られる。しかしながら,依然として業種別,規模別に跛行性が見られ,景気回復の足どりは緩慢である。
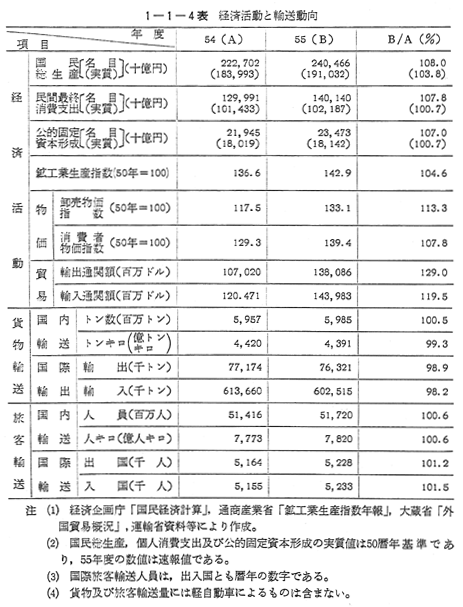
|