|
1 これまでの国鉄経営の概況第2次世界大戦により壊滅的打撃を被った我が国経済は,昭和20年代において戦後の混乱期を経て着実な復興を遂げた。このなかで,国鉄は戦中の酷使により輸送力が低下していたとはいえ,経済復興期における中心的な輸送機関として,大きな役割を担った。 30年代に入ると我が国経済は高度成長期を迎え,これに伴い各輸送機関はその輸送量を増大させた。国鉄も,旅客輸送においては順調に輸送量が増加し,幹線系を中心に輸送需要が輸送力を上まわる状況が続いた。貨物輸送においては輸送力が逼迫する状況にはあったものの,国内総輸送需要の伸びを支えた臨海立地型の重化学工業の発展及び輸送需要の質的変化をもたらした大衆消費社会の到来により,内航海運及び自動車の発展と相まって,他の輸送機関に対する優位性は次第に失われた。更に,石炭から石油へのエネルギー革命による石炭輸送需要の減少の影響も加わり,30年代後半に至り,運賃が比較的低位に据え置かれていたにもかかわらず,国鉄の貨物輸送需要は伸び悩みの傾向となった。 このような状況の中で,国鉄は,老朽化した設備の更新と東海道新幹線の建設等の幹線輸送力の増強を推進することにより対応し,30年代を通して積極的な設備投資を行った。 この間,国鉄の収支は比較的安定した状況にあったが,30年代後半における貨物収入の伸び悩み,設備投資に伴う資本費負担の増大等により,39年度には単年度赤字を生ずるに至った。 40年代前半には,引き続く経済の高度成長により国内総輸送需要が伸びる中で,30年代後半から進んでいた旅客輸送におけるモータリゼーションの進展と貨物輸送における自動車,内航海運の発展に起因する輸送構造の変化は,更に顕著なものとなった。 国鉄の輸送量をみると,旅客輸送においては,所得水準の上昇に伴う旅行需要の伸びや産業,経済の発展等により新幹線を中心に優等列車(特急・急行)の輸送量が比較的順調な伸びを示したほかは,優等列車の旅客を除く普通旅客は40年度を,定期旅客は42年度をそれぞれピークとして漸減傾向に転じた。また,貨物輸送においては,物流革新に対応してコンテナの輸送量が順調な伸びを示したものの,貨物の大部分を占める車扱の輸送量は伸び悩み,全体では微増したにすぎなかった。 国鉄は,このように競争が激化する輸送市場の中で,輸送力の増強と輸送施設の近代化を積極的に進めることとし,30年代を上まわる設備投資を行うとともに,既に輸送需要に伸び悩みの傾向がみられた貨物輸送についても輸送力の増強を続けた。 この間,40,43,44の各年度に運賃改定を実施したが,国鉄の収支は赤字が続き,41年度には利益積立金を取り崩して繰越欠損金を生じた。 このような国鉄の経営悪化に対処するため,44年5月,日本国有鉄道財政再建促進特別措置法(以下「財政再建法」という)が制定され,①経営の近代化,合理化,②工事費補助を中心とする国の助成の強化等を内容とする第1次国鉄再建対策が実施されることとなった。 しかし,40年代後半には,国鉄の旅客輸送量は引き続く優等列車の輸送量の伸びと地域旅客輸送におけるモータリゼーションの影響が一段落したこと等により,全体として堅調な伸びを示していたものの,経費の増大のなかで,適時適切な運賃改定ができなかったことにより収入が伸び悩んだため,それまで黒字基調であった旅客部門の収支は47年度以降急激に赤字基調に転落した。また,貨物輸送においては,40年度以降の運賃の据え置きにもかかわらず,輸送量が45年度をピークとして減少し,経費の増大と相まって,貨物部門の収支は大幅に悪化した。 この結果,国鉄の収支は46年度には償却前赤字を生ずることとなり,48年9月には財政再建法が改正されて,第2次再建対策が実施されることとなった。しかしながら,第1次石油危機等による人件費及び物件費の高騰並びに設備投資に伴う資本費及び赤字に伴う支払利子の増加により経費が急激に増大する一方,収入が伸び悩んだことにより国鉄の収支はますます悪化を続け,50年度においては9,000億円を超える赤字を生じ,累積赤字は3兆円を超えるに至った。 このため,政府は,50年12月「日本国有鉄道再建対策要綱」の閣議了解を行い,①2兆5,404億円の過去債務の棚上げなど国の助成措置の強化,②51年度名目50%の運賃改定,③経営の合理化の推進等を内容とする第3次再建対策を講ずることとした。その後,対策の一層の推進を図るため,52年1月に上記閣議了解を修正する「日本国有鉄道の再建対策について」が閣議了解され,これに基づいて国有鉄道運賃法が改正され,運賃改定制度の弾力化が行われた。 一方,第1次石油危機以降,我が国経済が安定成長へと移行したことを反映して,国内総輸送需要は旅客,貨物とも伸びが鈍化した。特に国鉄については,49,50,51各年度の運賃改定,航空輸送の著しい発展,高速道路の相次ぐ開通等により,それまで比較的順調な伸びを示していた優等列車の輸送量が,50年度をピークとして減少傾向に転じたため,旅客輸送量全体もほぼこれと同じ幅で減少し,また,貨物輸送量も引き続き減少傾向となっている。 このような輸送需要面における厳しい状況の中で,国鉄の収支は,運賃改定による増収,国の助成の強化等が図られたが,その後も毎年度8,000億円を超える赤字を生じ,55年度には約1兆円の赤字となるなどその経営はまさに危機的状況に陥っている 〔1-4-1図〕, 〔1-4-2図〕, 〔1-4-3表〕。
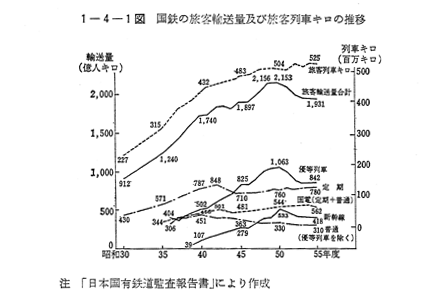
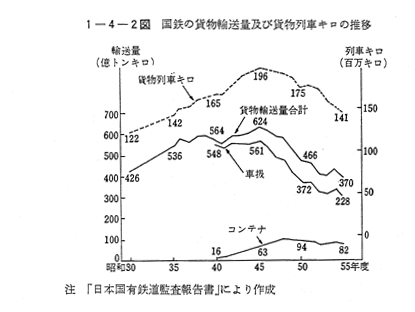
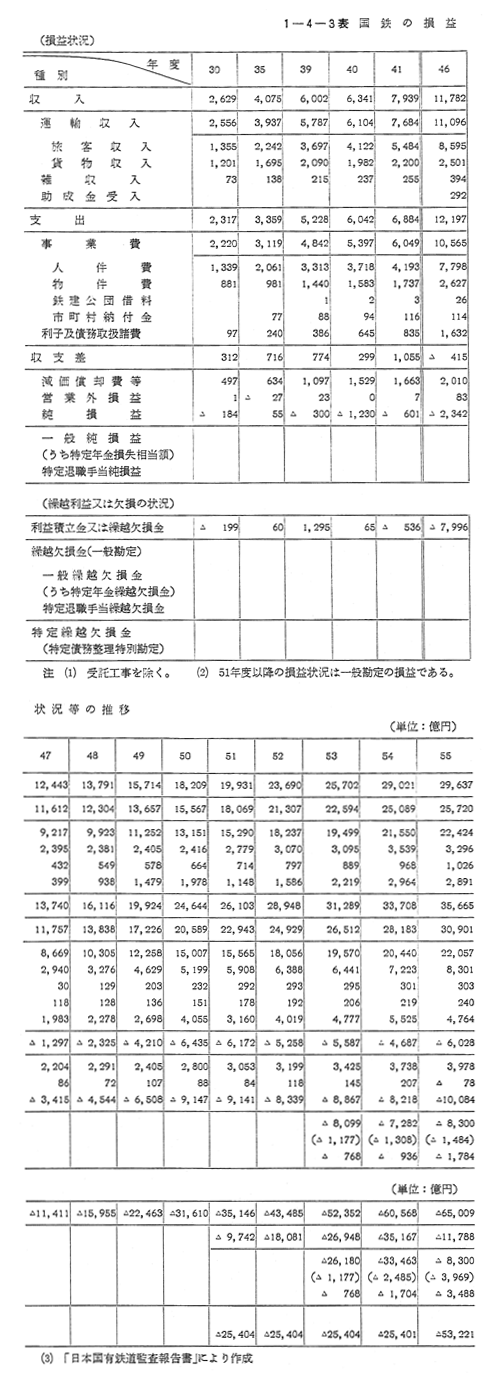
|