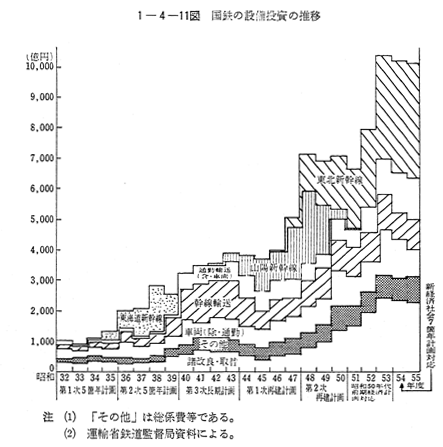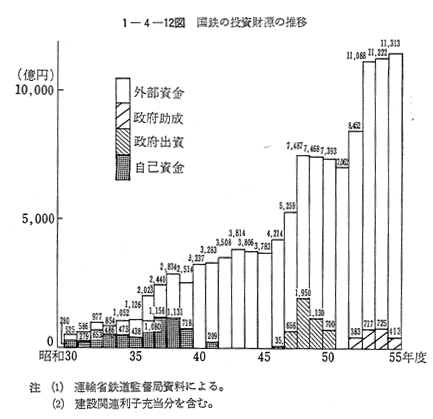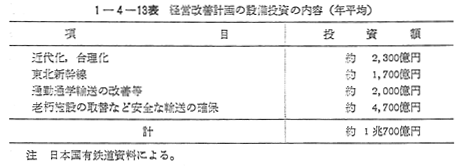|
3 設備投資
設備投資は,国鉄の経営活動の物的な基盤を確立する役割を担っている。膨大な施設を必要とする鉄道事業においては,設備投資の妥当性如何が長期にわたってその経営の動向を左右することとなる。経営改善のために設備投資の果たす役割は大きいが,一方,設備投資に伴う資本費負担の増大は経営を圧迫する大きな要因となる。したがって,設備投資は,長期の経営見通しに立脚して計画的に行うこととするとともに,経営状況,輸送需要の動向等に適合するよう柔軟に行う必要がある。
従来,国鉄の設備投資は長期計画に基づいて行われてきた。
30年代においては,第1次及び第2次5箇年計画に基づき,老朽資産の取替え,輸送力の増強,輸送方式の近代化等が重点的に行われた。特に東海道本線における輸送力の逼迫を抜本的に解消するため,東海道新幹線の建設が行われた。貨物輸送については,30年代後半になると輸送量が伸び悩むようになったが,引き続き積極的な設備投資が行われた。こうしたなかで,投資財源に占める外部資金の比率は上昇し資本費負担が増大したことも一因となって,39年度には単年度赤字を生じた。しかし,引き続く経済の高度成長の中で輸送需要は大きく伸びるものと予測されたこと等を背景として,40年度からは第3次長期計画に基づき,特に輸送力の逼迫していた大都市圏の通勤輸送対策,幹線を中心とした輸送力の飛躍的増大及び保安設備の強化が重点的に行われた。しかし,全体としては,30年代後半からの輸送構造の変化が旅客輸送にも現われはじめ,また,貨物輸送量の横ばい傾向が続いたため,この計画における需要予測を旅客,貨物とも大幅に下まわった。
40年代前半の赤字経営下での積極的な設備投資に伴う資本費負担の急増も大きな要因となり,国鉄の収支は悪化を続けたため,44年度から第1次再建対策が実施され,今日に至るまで,設備投資も再建対策の一環として進められており,その重点化が図られている。投資項目ごとの推移をみると,第1次再建対策期間中は,新幹線投資を除く設備投資は圧縮されたものの投資総額は増えた。第2次再建対策への移行後も新幹線投資は増大を続け,それ以外の設備投資はほとんど実質的には減少している。設備投資が全体として抑制されているなかで,45年度以降,諸改良取替投資額が急増し,特に近年,40年前後に投資された設備の取替期に入っているため,設備投資の機動性を発揮する余地は極めて限られてきている 〔1−4−11図〕, 〔1−4−12図〕。
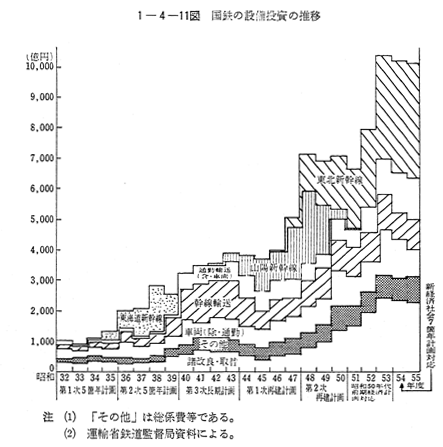
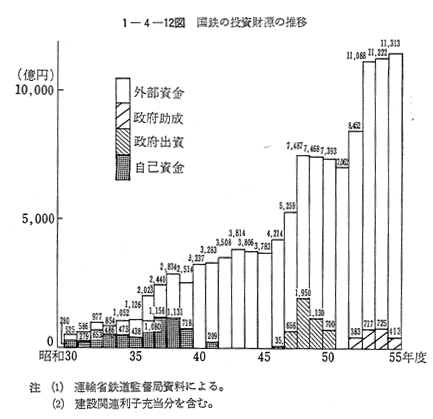
今回の経営改善計画においては,設備投資のための資金の大部分を借入金に依存している現状のため,国鉄経営に与える影響を考慮し,計画期間中の投資規模を現状程度に抑制することとしている 〔1−4−13表〕。
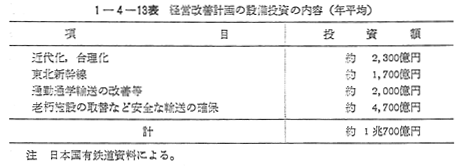
|