|
1 最近の国際エネルギー情勢第1次石油危機後暫く緩和傾向にあった石油市場は,1978年秋から79年春にかけて進行したイラン革命を契機に再び混迷の度合いを強め,やがて第2次石油危機へと発展した。革命前は,石油輸出国機構(OPEC)の原油の2割近くを供給していたイランは,78年12月末に原油の輸出を停止し,石油市場には大きな供給不足が生じた。国際石油情勢は一時緊迫化したが,消費国の備蓄の取り崩し,サウジアラビアの増産,季節的な需要の下降,消費抑制対策の進行もあって需給は徐々に均衡し,80年に入ってもこの状態は続いた。 しかし,このような原油需給の均衡状況下においても,原油価格は,イラン革命初期における需給の逼迫要因をはじめ量や価格の面での先行き不安も影響して,79年初頭から80年までの1年間に約2倍になった。その後,先進消費諸国の脱石油化が進展し,需給が緩和傾向に移ってゆくなかでも石油価格は上昇を続けた 〔1−5−7図〕。
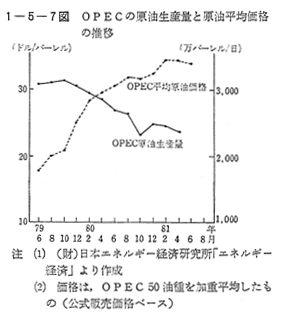
80年9月,イラン・イラク紛争の本格化により,両国からの石油の輸出は完全に停止し,国際石油需給は再び逼迫化するかにみえた。これに対し,国際エネルギー機関(IEA)では,備蓄の取り崩し,スポット原油の高値買い自粛等を含む5項目の基本的対応策をたて,戦争に起因する原油価格の高騰の回避に努めた結果,サウジアラビアの増産もあり,また,消費国が景気の低迷期であったことから,石油需給は逆に緩和傾向を示した。
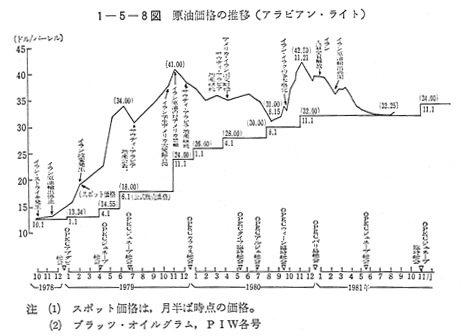
81年下半期においても石油の供給過剰が続いているが,従来より石油の需給は緩和と逼迫を繰り返しており,今後も中長期的には産油国の資源温存政策の強化や発展途上国における石油消費の増大等による石油需給の逼迫が十分予想されるところである。したがって,消費国においては,一時的な石油市場の動向に左右されることなく,省エネルギー,石油代替エネルギー導入等の施策を強力に推進してゆく必要があろう。
|