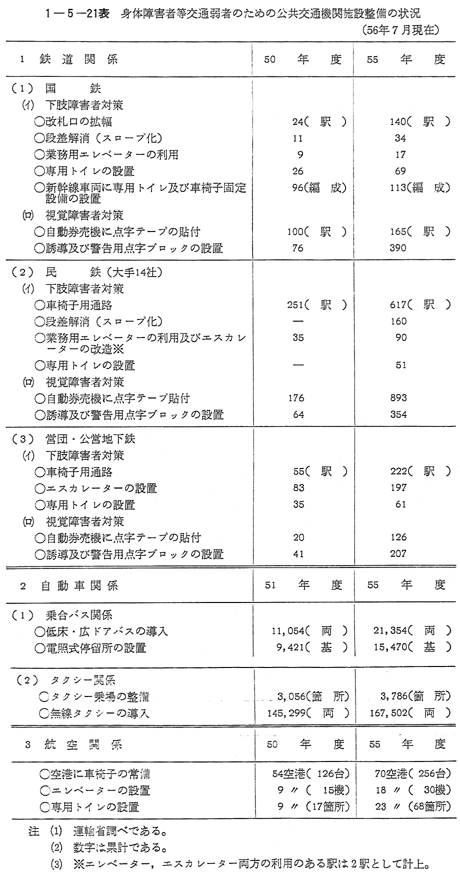|
2 運輸における交通弱者対策の現状
高齢看,身体障害者等の交通弱者対策としては,輸送機関の利用を困難としている要因の除去が必要である。運輸省においては,各交通事業者等に対し,旅客輸送サービス改善対策の一環として身体障害者等にも配慮した対策を講ずるよう指導を行っており,これらによる関係施設整備の状況は 〔1−5−21表〕のとおりである。
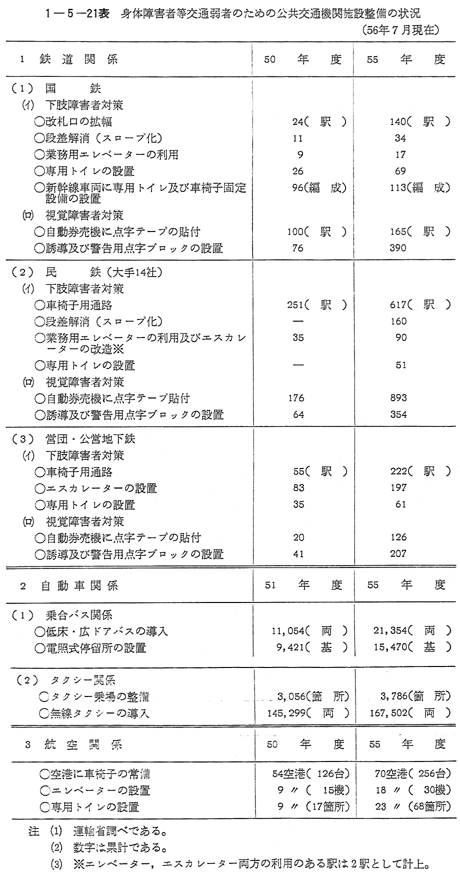
まず,鉄道関係については,改札口の拡幅,段差解消(スロープ化),身体障害者用トイレの設置,自動券売機に点字テープの貼付,誘導及び警告用点字ブロックの設置等を行っている。次に,自動車関係については,乗合バスに低床・広ドアバスの導入,停留所に電照式ポールの設置,タクシー乗場の整備,無線タクシーの導入等を行っている。また,航空関係については,空港に車椅子の常備,エレベーターの設置,身体障害者用トイレの設置等を行っている。
また,昭和50年度から55年度までの進捗率を各施設別に見ると,鉄道関係における改札口の拡幅(車椅子電通路の設置),誘導及び警告用点字ブロックの設置等について数倍の改善が見られる一方,エレベーターの設置など物理的・空間的,また経済的制約の大きい施設の改善は総体的に低い。また,各輸送機関別の改善率を見ると,航空関係,民鉄等に比し,国鉄の改善が遅れている。
以上の施設整備のほか,運用面においても配慮がなされており,鉄道,乗合バスにおける優先座席(シルバーシート)の設定,車椅子使用者及び盲導犬を連れた視覚障害者の安全かつ円滑な乗車の実施等について一定の前進を見ている。
運輸における今後の交通弱者対策としては,高齢者,身体障害者等の交通弱者を特殊なサービスを要する者として位置付けるのではなく,社会における身体障害者等の存在を当然の前提として,交通施設を含めた社会のインフラストラクチャーが形成されねばならないとする,いわゆるノーマライゼーションの考えに基づき,その社会参加を確保していく観点から対策を進める必要があり,運輸行政の課題の一つとなっている。このためには,交通弱者が安全かつ身体的に負担の少ない方法で移動が可能となるよう配慮した施設整備を進めるとともに,交通弱者に適切な援助がなされるよう接客に携わる交通従事者に対する教育を徹底するほか,一般旅客の理解と協力を得ることも肝要であり,関係者と協力の上,啓発・広報等に努めることが重要である。
|